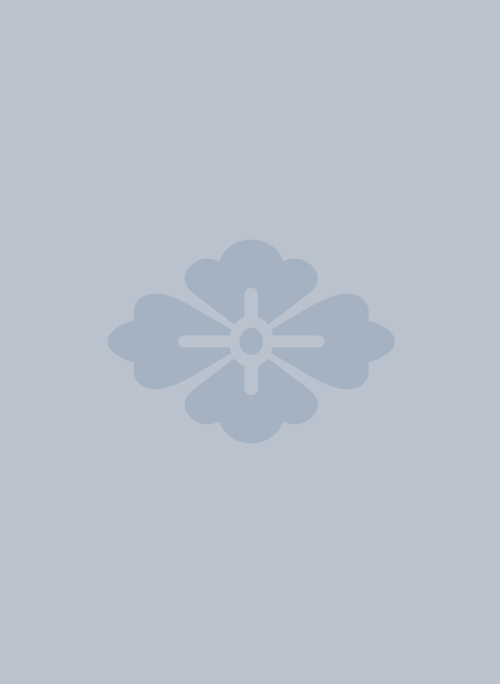「よくも、まあ、それだけの罪を思いつく。
僕の義理の父王よ。
……そんなに僕が、怖いのか?」
「なに! 何を言うか!!」
王は、激昂して、その指をキアーロにつきつけた。
「口の聞き方に気をつけよ!
今述べた数々の罪状により、そなたを死罪にすることも可能なのだぞ!?」
「……僕が並みの貴族であれば、の話だろう?」
余裕しゃくしゃくと、返すキアーロの言葉に、王の激怒は、増した。
「大きな口を叩けるのは。
そなたが、何をしても許される立場だと思っているからか?」
「……」
「しかし、それは、そなたの思い込みにしか、過ぎぬ」
言って王は、歪んだ微笑みを見せた。
「そなたにでも出来る責任の取り方と言うものがあろう?
例えば。
未だ世界を探しても見つからぬ、雨神の扉を開く魔法使いの探索とか。
あるいは。
……そなた自身が、雨神の生け贄となるとか」
「……つまり。
この騒ぎのあと始末は国外追放か、死罪だと?」