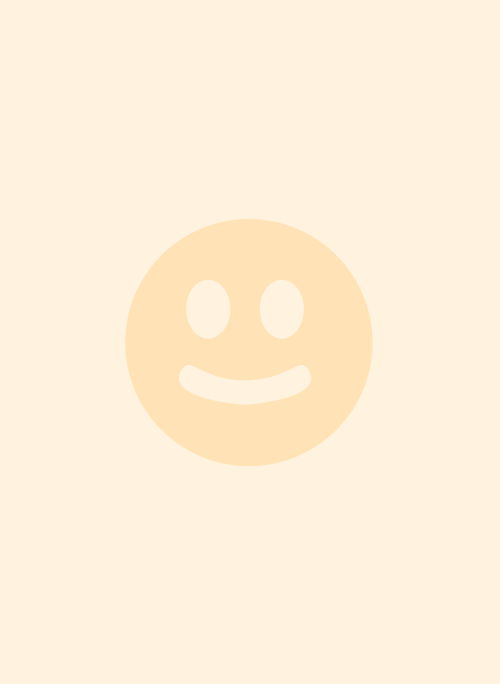烏帽子をとり、髷を外す。
赤毛の混じった茶髪が、薫風に煽られて揺れた。
肩より下の辺りで、定期的に無造作に髪を切ってしまっているので、周りの貴公子のように伸ばしっぱなしにするわけではない。
そういえば。
(あいつは・・・この髪色がいいと言うてくれたような)
思い出したように考えるが、すぐ我に返った。
首を勢いよく左右に振る。
「・・・すまん、莢」
―まだ、お前のことを忘れることが叶わない。
―こんな外道に覚えていてもらっても、お前は、嬉しくないだろうに・・・。
もし文を書いてそれが莢に届くのならば、そう書いて送ってやりたい。
どんなに罵られたっていい。
どんなに悲しまれたっていい。
どんなに周りから非難されてもいい。
ただ、莢に自分の中にある言葉を伝えたかった。
莢を忘れることができぬ事を、謝りたかったのだ。