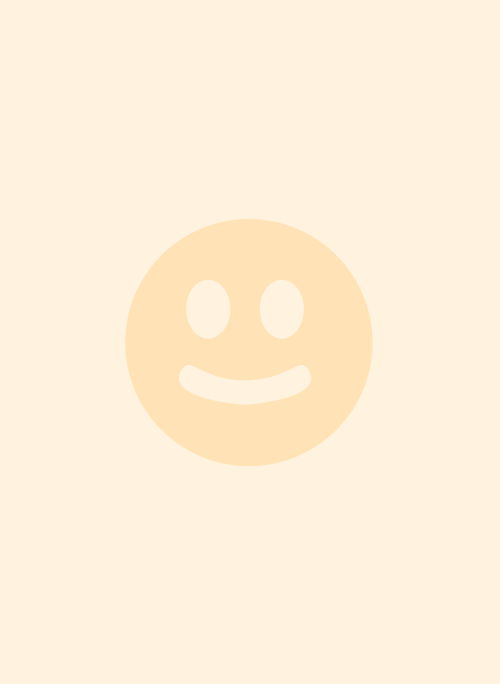晴也はすぐ横の窓側に屯した女子生徒たちに一瞥をくれた。
「ねえ、あの子たちって、さっきからなに騒いでんの?」
前の席にいる細川(ほそかわ)に問うてみる。
椅子の背に腕を出して振り返った細川は、黄色い小声で騒ぎ立てる女子生徒たちを煩わしげに眺めた。
そして彼女らの視線の先にあるのだろうものを窓から見、
「あれだよ」
と三階の渡り廊下を示した。
晴也も窓から、緑色のシートが敷き詰められた渡り廊下を見つめる。
渡り廊下の中心辺り、荒々しくも端正な容貌の男子生徒が、柵に背中を預けて、タッチ式の携帯電話を触っている。
漆黒の黒髪を肩まで伸ばし、左頬には傷でもつけたのか湿布が貼られていた。
「知ってる?道麻(とうま)先輩、あの左頬の怪我って、喧嘩でついた奴らしいよ」
「あれでしょ、悪メンってやつ。ちょーかっこいいんだけどっ」
「王子様もいいけど、やっぱりヤンキーだよねえ」
完璧な超人などいない。
彼女ら曰くの「王子様」のような人間は、数百、数千人に一人くらいしか生まれてこないだろう。
分かっているだろうに、女子の理想とは天よりも高い。
彼女らは、あたかもそんな人間が、そこらじゅうに存在しているかのような口振りである。
「女子って、ああいうののどこに惹かれるんだろうなあ」
「知らね」
晴也が言葉にした疑問を軽くはねのけ、細川は大欠伸をかました。
「どうせ、イケメンだから、とかいう理由だろ。携帯小説の読みすぎなんだよ。ああいう喧嘩ばっかの奴にはさ、ろくな未来はないね」
細川の舌端が火を吐く。しかし正論である。ろくでなしに進む道はない。
「同感……。頭がよくたって、内心は絶対よくならないだろうなあ。喧嘩してると」
晴也も細川の意見には賛成だ。
細川の酷評は、その道麻という先輩の容姿に対しての嫉妬心も含まれているのだろうが、晴也の場合は現実的に考えての、酷評だった。
「部活には所属してるみたいだけど、部員もあの人だけらしい」
「そんなんで成り立つのか?部活ってのは」
「どうだろうな。教師も教師で、廃部のはの字さえ言わないんだってよ」
いまいち謎な不良生徒である。晴也は不思議で仕方がない。
「もしかして、親の七光りとか」
「さあな。しかも不思議なことに、あの先輩、去年は出席簿は皆勤だったらしいし。しっかりしてんだか荒れてるんだか」
そうか、だから少なからず教師からの評価もそこまで酷くなかったのか。晴也はそう納得するのだった。
「まあ、出席は大事だよ。入試とか就職とかでも、出席日数の多少で優劣が決まることだってあるんだから」
「秀才の基準でだろ、それ」
入試の話はこりごりだ、とばかりに細川が両手で耳を塞ぐ。確かに、晴也は秀才の基準で言ったかもしれない。