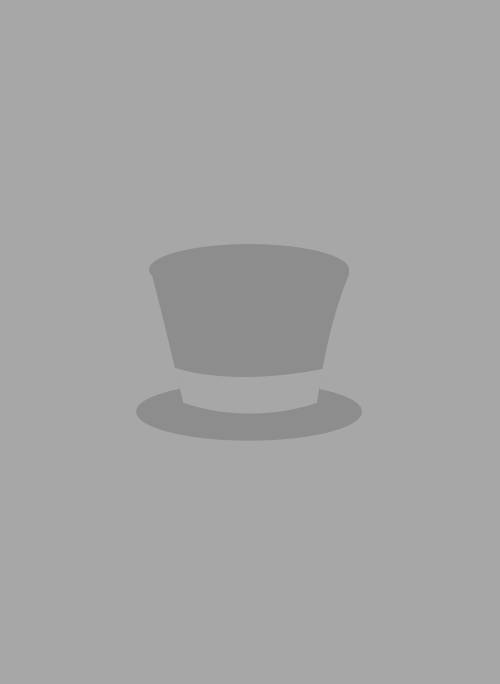部屋に戻ると達郎は目を閉じて寝転がっていたが、あたしが缶コーヒーを差し出すと目をあけた。
「レミ」
あたしの顔を見て達郎はつぶやいた。
「なんか怒ってないか」
「気のせいよ」
ぴしゃりとはね返した。
子供じみた嫉妬心を見抜かれてたまるか。
達郎はそれ以上追求しようとはせず、受け取った缶コーヒーを胸のあたりで抱き抱えるようにして再び目を閉じた。
達郎には変な癖がある。
事件を推理する時、必ず缶コーヒーを手にするのだ。
なんでもはじめて事件を解決した時、たまたま缶コーヒーを手にしていたそうで、それ以来癖になっているらしい。
達郎が目をあけた。
いつもなら聞こえる乾いた音はしなかった。
達郎は缶コーヒーを開けずに、冷えたそれを額にあてた。
熱さまシートの代わりか?
「レミ」
そう呼び掛けた声には張りが戻っていた。
横になったまま、未来を見通すような視線をこちらに向ける。
「ちょっとお前好みの話をするぞ」
「レミ」
あたしの顔を見て達郎はつぶやいた。
「なんか怒ってないか」
「気のせいよ」
ぴしゃりとはね返した。
子供じみた嫉妬心を見抜かれてたまるか。
達郎はそれ以上追求しようとはせず、受け取った缶コーヒーを胸のあたりで抱き抱えるようにして再び目を閉じた。
達郎には変な癖がある。
事件を推理する時、必ず缶コーヒーを手にするのだ。
なんでもはじめて事件を解決した時、たまたま缶コーヒーを手にしていたそうで、それ以来癖になっているらしい。
達郎が目をあけた。
いつもなら聞こえる乾いた音はしなかった。
達郎は缶コーヒーを開けずに、冷えたそれを額にあてた。
熱さまシートの代わりか?
「レミ」
そう呼び掛けた声には張りが戻っていた。
横になったまま、未来を見通すような視線をこちらに向ける。
「ちょっとお前好みの話をするぞ」