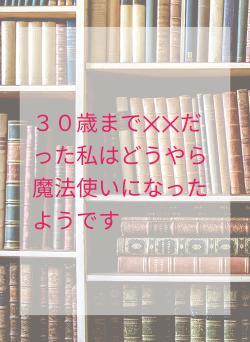崩れたのはシミができていた部分だけだったから、思ったよりも瓦礫の片づけは簡単だった。
といっても、ドアを開けるのに邪魔になる部分を横に移動させただけ。
「よし、開けてみよう」
さすがに緊張しているようで、元浩が上ずった声で言った。
「懐中電灯とか、いらないの?」
愛奈が後ろから元浩に声をかける。
「調理室の明かりが入るから大丈夫だろ」
元浩はそう言うと、さび付いたドアノブに手をかけた。
あたしは祈るように胸の前で手を組み、ゴクリと唾を飲み込んだ。
どうか、中になにもありませんように。
自然とそんな風に願っている自分がいた。
そしてチラリと調理室のドアへ視線を向ける。
あれだけ大きな音が響いたのに、まだ誰も様子を見に来ない。
誰か……来て。
そんな願いもむなしく、ギィィィとさび付いた音を響かせながら、ドアは開いてしまったのだった。
といっても、ドアを開けるのに邪魔になる部分を横に移動させただけ。
「よし、開けてみよう」
さすがに緊張しているようで、元浩が上ずった声で言った。
「懐中電灯とか、いらないの?」
愛奈が後ろから元浩に声をかける。
「調理室の明かりが入るから大丈夫だろ」
元浩はそう言うと、さび付いたドアノブに手をかけた。
あたしは祈るように胸の前で手を組み、ゴクリと唾を飲み込んだ。
どうか、中になにもありませんように。
自然とそんな風に願っている自分がいた。
そしてチラリと調理室のドアへ視線を向ける。
あれだけ大きな音が響いたのに、まだ誰も様子を見に来ない。
誰か……来て。
そんな願いもむなしく、ギィィィとさび付いた音を響かせながら、ドアは開いてしまったのだった。