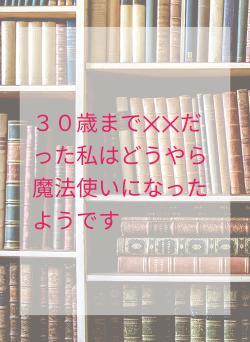外に出ることはできない。
助けも来ない。
それがわかったあたしたちは、澪の死体に目をやらないよう、みんな俯いた状態で椅子に座っていた。
こんな異様な空間にいると、澪の死体が動き出すんじゃないかという怖い妄想までしてしまう。
あたしは小刻みな震えが止まらない自分の体を抱きしめた。
「大丈夫か?」
そう聞いてくれたのは旺太だった。
旺太の顔色はもう戻っていて、あたしの隣に座った。
「うん……」
あたしは少し無理をして笑顔を浮かべた。
優しい旺太に心配はかけたくない。
けれど、震えは止まらなかった。
「嫌じゃなかったから、おいで」
旺太はそう言い、あたしに向かって両腕を開いた。
助けも来ない。
それがわかったあたしたちは、澪の死体に目をやらないよう、みんな俯いた状態で椅子に座っていた。
こんな異様な空間にいると、澪の死体が動き出すんじゃないかという怖い妄想までしてしまう。
あたしは小刻みな震えが止まらない自分の体を抱きしめた。
「大丈夫か?」
そう聞いてくれたのは旺太だった。
旺太の顔色はもう戻っていて、あたしの隣に座った。
「うん……」
あたしは少し無理をして笑顔を浮かべた。
優しい旺太に心配はかけたくない。
けれど、震えは止まらなかった。
「嫌じゃなかったから、おいで」
旺太はそう言い、あたしに向かって両腕を開いた。