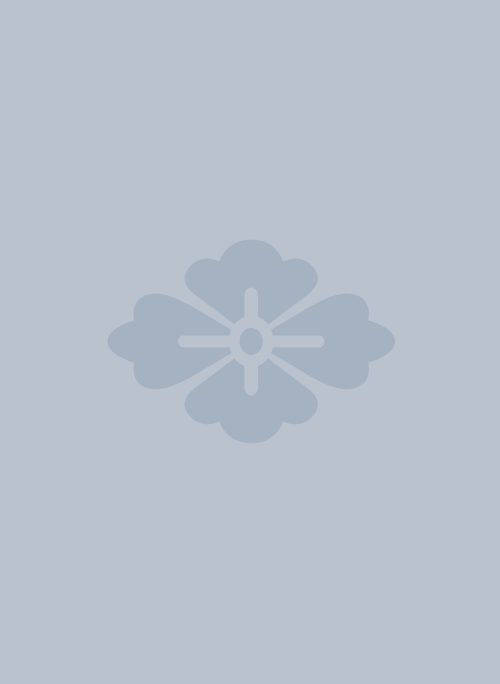その辺から、何だか惟道の周りが一気に華やかになった。
一人が勇気を出して誘うと、我も我もとなるのか、結構な数の女子が惟道目当てに群がるようになった。
群がる、といっても別に営業フロアが華やかになるわけではない。
行き帰り、主に帰りにいろんな女子に掻っ攫われる。
惟道も、それを嫌がるでもなく、かといって楽しんでいるようでもない。
その日一番に誘った者に、素直について行く、といった感じなのだ。
真砂のように声をかけるのすら躊躇われるほどの恐ろしい空気でもないし、清五郎のように軽くかわすわけでもないイケメンは、格好の標的となっているようだ。
「~~~ったく~~~っ! 何だってのよ、皆」
パックジュースを啜りながら、ゆいが機嫌悪そうに言う。
相変わらずお昼時になると、惟道は掻っ攫われ、今日もいない。
全女子社員から誘われているのではないか、と思うほど、毎日毎日違う人に誘われているようだ。
実際はいちいち覚えていないので、二回目、三回目の人もいるかもだが。
「一番初めに目を付けたのはあたしだってのに。ていうか惟道くんも、もうちょっとあたしに気を遣ってくれてもいいんじゃないの?」
「何で?」
「だってあたしが一番に手に入れたってのに。それに、仕事中だって常に傍にいるのはあたしなのよ?」
仕事中は深成の傍にもいるが。
確かに最近は基本的なことよりも専門的なことが増えてきて、ゆいの指導を仰ぐほうが多くなっているが。
「そりゃ一番近くにいるかもだけど、それはほんとに『いる』だけじゃない」
「惟道くんのモテ道を開いたのはあたしなのよっ?」
「……まぁ確かに、ゆいちゃんが初めに誘ったのがきっかけと言えなくもないけど」
「他の女に渡すために、モテ道を開いたわけじゃないのにっ」
「だったらもう、ゆいちゃんがちゃんと『付き合って』って言えばいいじゃない」
あきが言うと、ゆいは、拗ねたように口を尖らせた。
「いい大人が、何でそんなことわざわざ言わないといけないの。やることやったんだから、付き合ってるもんだと思ってた」
あ、やっぱり、と内心思ったが、とりあえず黙っておく。
確かにそれなりの歳になったら、付き合うスタートというのはわかりずらい。
学生とかのように、畏まって交際を申し込む、ということがないからか。
しかも大人だからやることやったら付き合ってる、とも言えるし、大人だからこそ付き合ってなくてもやることはやる、とも言えるのだ。
「う~ん、まぁ……惟道くんの場合は、そういうのって付き合う付き合ってないに関係ないような気もするしねぇ」
「そうだね。付き合ってるからって、彼女を大事にするってタイプでもなさそう」
深成もうんうんと頷く。
ここも真砂と大きく違う点だろう。
「ていうか、惟道くんて短期だから、そろそろ終わりなのよね。辞めちゃう前に、がっちり捕まえておかなくちゃ」
「え、もう?」
「初めから三か月って言ってたし」
なるほど、もっとも忙しい年度末だけの臨時バイトだったわけだ。
すでに二か月が過ぎている。
「何か……。結局全然何もわかんないままだな」
ここまで人となりがわからない人間がいただろうか。
持っているものは強烈なのに、人そのものはいまだ何もわからない。
もうちょっと打ち解けられたらいいのに、と思いつつ、午後からの仕事に集中していると、ぺろんとメールが入った。
清五郎からだ。
<少し人数に余裕のある今のうちに、資料室の整理をしようと思う。定時後で悪いが、集まれますか?>
宛先は、真砂・深成・あき・惟道。
ちろ、と上座を見ると、真砂はまだメールを開いていないようだ。
「課長。清五郎課長からメールが入ってるけど」
声をかけると、一瞬だけ顔を上げ、真砂はメールを開いた。
「あきちゃんは? 今日大丈夫?」
「うん」
深成の問いに答えながら、あきは少しきょろ、と周りを見た。
捨吉はいないし、千代も今日はいない。
使いやすい者を選んだのだろう。
一課の者にも声をかけるのだから、真砂も入れたのか。
二課のほうを見てみると、普通に惟道の横にゆいがいる。
何故ゆいには声をかけないのだろう、と思い、ゆいの予定表を見てみると、丁度定時の少し前から外出予定が入っていた。
一人が勇気を出して誘うと、我も我もとなるのか、結構な数の女子が惟道目当てに群がるようになった。
群がる、といっても別に営業フロアが華やかになるわけではない。
行き帰り、主に帰りにいろんな女子に掻っ攫われる。
惟道も、それを嫌がるでもなく、かといって楽しんでいるようでもない。
その日一番に誘った者に、素直について行く、といった感じなのだ。
真砂のように声をかけるのすら躊躇われるほどの恐ろしい空気でもないし、清五郎のように軽くかわすわけでもないイケメンは、格好の標的となっているようだ。
「~~~ったく~~~っ! 何だってのよ、皆」
パックジュースを啜りながら、ゆいが機嫌悪そうに言う。
相変わらずお昼時になると、惟道は掻っ攫われ、今日もいない。
全女子社員から誘われているのではないか、と思うほど、毎日毎日違う人に誘われているようだ。
実際はいちいち覚えていないので、二回目、三回目の人もいるかもだが。
「一番初めに目を付けたのはあたしだってのに。ていうか惟道くんも、もうちょっとあたしに気を遣ってくれてもいいんじゃないの?」
「何で?」
「だってあたしが一番に手に入れたってのに。それに、仕事中だって常に傍にいるのはあたしなのよ?」
仕事中は深成の傍にもいるが。
確かに最近は基本的なことよりも専門的なことが増えてきて、ゆいの指導を仰ぐほうが多くなっているが。
「そりゃ一番近くにいるかもだけど、それはほんとに『いる』だけじゃない」
「惟道くんのモテ道を開いたのはあたしなのよっ?」
「……まぁ確かに、ゆいちゃんが初めに誘ったのがきっかけと言えなくもないけど」
「他の女に渡すために、モテ道を開いたわけじゃないのにっ」
「だったらもう、ゆいちゃんがちゃんと『付き合って』って言えばいいじゃない」
あきが言うと、ゆいは、拗ねたように口を尖らせた。
「いい大人が、何でそんなことわざわざ言わないといけないの。やることやったんだから、付き合ってるもんだと思ってた」
あ、やっぱり、と内心思ったが、とりあえず黙っておく。
確かにそれなりの歳になったら、付き合うスタートというのはわかりずらい。
学生とかのように、畏まって交際を申し込む、ということがないからか。
しかも大人だからやることやったら付き合ってる、とも言えるし、大人だからこそ付き合ってなくてもやることはやる、とも言えるのだ。
「う~ん、まぁ……惟道くんの場合は、そういうのって付き合う付き合ってないに関係ないような気もするしねぇ」
「そうだね。付き合ってるからって、彼女を大事にするってタイプでもなさそう」
深成もうんうんと頷く。
ここも真砂と大きく違う点だろう。
「ていうか、惟道くんて短期だから、そろそろ終わりなのよね。辞めちゃう前に、がっちり捕まえておかなくちゃ」
「え、もう?」
「初めから三か月って言ってたし」
なるほど、もっとも忙しい年度末だけの臨時バイトだったわけだ。
すでに二か月が過ぎている。
「何か……。結局全然何もわかんないままだな」
ここまで人となりがわからない人間がいただろうか。
持っているものは強烈なのに、人そのものはいまだ何もわからない。
もうちょっと打ち解けられたらいいのに、と思いつつ、午後からの仕事に集中していると、ぺろんとメールが入った。
清五郎からだ。
<少し人数に余裕のある今のうちに、資料室の整理をしようと思う。定時後で悪いが、集まれますか?>
宛先は、真砂・深成・あき・惟道。
ちろ、と上座を見ると、真砂はまだメールを開いていないようだ。
「課長。清五郎課長からメールが入ってるけど」
声をかけると、一瞬だけ顔を上げ、真砂はメールを開いた。
「あきちゃんは? 今日大丈夫?」
「うん」
深成の問いに答えながら、あきは少しきょろ、と周りを見た。
捨吉はいないし、千代も今日はいない。
使いやすい者を選んだのだろう。
一課の者にも声をかけるのだから、真砂も入れたのか。
二課のほうを見てみると、普通に惟道の横にゆいがいる。
何故ゆいには声をかけないのだろう、と思い、ゆいの予定表を見てみると、丁度定時の少し前から外出予定が入っていた。