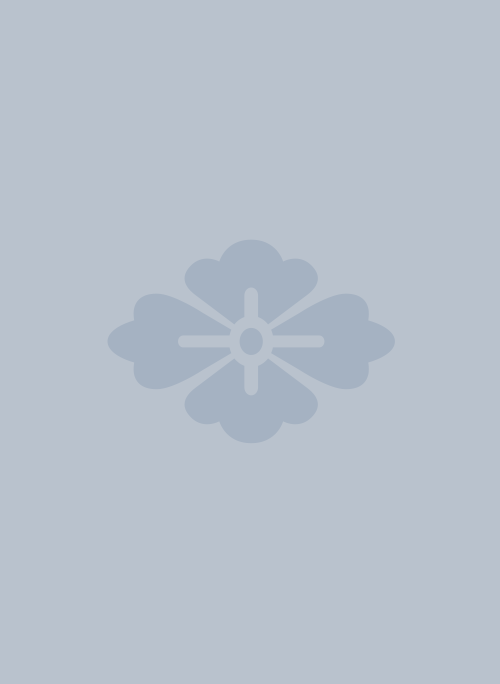「おお~!! 凄~い!!」
部屋に入るなり、深成が歓声を上げた。
二間続きの和室の奥に、露天風呂がある。
「贅沢だね~。露天風呂貸し切りなんて、そうないよ~」
うきうきと早くも浴衣を用意していた深成だったが、はた、と我に返る。
---あれれ? お部屋にお風呂で貸切風呂ってことは、お風呂一緒に入るってこと?---
確かに一人じゃ寂しい、とは言ったが、部屋風呂であれば問題ない。
---けど、家族風呂とかだったら、皆一緒に入るよね……---
真砂の思惑がわからず、深成は浴衣を持ったまま固まった。
真砂はちらりと腕時計に視線を落とし、次いで深成に目をやった。
「飯の前に、風呂入るか?」
「うえぇぇっ?」
びびくん! と深成が飛び上がる。
真砂が怪訝な顔をした。
「何だよ。そのつもりで浴衣用意したんじゃないのか?」
「う、そ、そうだけど。えっと、その……まだほら、時間も早いしさぁ」
赤くなってごにょごにょと言う。
ぶは、と真砂が吹き出した。
「はははっ。そんなに構えんでも、着いて早々そんなことはせんよ」
「え、でも。ほら、一緒にお風呂入ったら、やっぱり……」
結婚して子供もいるぐらいであれば、それこそ家族風呂として皆一緒に入っても何もないかもしれない。
だが真砂と深成は、まだまだ隙あらばらぶらぶしているようなバカップルである。
ちょっとくっついていただけで甘やかな空気が漂うのに、一緒に風呂など何もないわけがない。
「別に部屋風呂だからって、絶対一緒に入らんといかんわけじゃないぜ」
「あ、そ、そっか」
ほ、と息をつき、深成は身体の力を抜いた。
「ま、もうちょっと夜が更けてから、な」
にやにやと言う真砂に、い~っと顔を突き出し、深成は露天風呂に飛び込んだ。
「真砂~。わらわ、ちょっと売店見てくるね」
軽くお風呂に入った後、入れ替わりに入った真砂に言い、深成は一人、ふらふらとロビーの前の売店に向かった。
ちらちらと商品を見ていると、工事の音が聞こえて来た。
---あ、そういえば、何か工事してるとか言ってたな。そういや高山建設って?---
何か聞いたことある、と音のするほうを見ていると、一人の男性がこちらを見、驚いた顔をした。
そして駆け寄ってくる。
「深成ちゃん!」
「え? 誰?」
今しがた買ったお茶のペットボトルを握りしめ、深成は思いっきり不審そうな顔を向けた。
「私だよ。ほら、研修とかで何度か一緒になった……」
被っていたヘルメットを取ったのは海野 六郎だ。
かつてmira商社に研修に来、真砂の下で営業の勉強をしていた。
その後も一度、会社の親睦会などで会ったが。
「あ、ああ……。お久しぶりです」
やっと思い出したものの、それだけだ。
深成にとって六郎は、短期間真砂についていた人、というだけの認識だ。
真砂ありきの存在である。
「どうしたの? 旅行?」
「うん。六郎さんはお仕事だよね? あ、だから真砂、チェックインの時に確認したんだ」
ぽん、と手を叩く深成に、え、と六郎の顔が引き攣った。
「え、あの。深成ちゃん、旅行って、誰と……?」
「真砂」
さらっと答えた深成に、六郎は固まった。
が、すぐに気を取り直す。
---い、いや。今回もこの前みたいな、会社のイベントなのかも。二人とは限らんではないか---
そう思い、きょろきょろと周りを見回してみるが、他に知った顔があるわけでもない。
「あの。もしかして、今回はプライベートな旅行なの……?」
恐る恐る聞いてみる。
深成は思い切り不思議そうな顔で、こっくりと頷いた。
「ま、真砂課長と、二人で……?」
「そうだよ。わらわが温泉に行きたいって言ったから。でも二人で行っても大きいお風呂に一人は寂しいって言ったら、露天風呂付きのお部屋を取ってくれたんだ」
えへへ、と無邪気に言う深成に、六郎の顔はさらに強張った。
---へ、部屋に風呂だとっ? み、深成ちゃんはそれがどういうことか、わかっているのか! 奴め、深成ちゃんの幼さに付け込んで、着々と下心の刃を研ぎやがって……---
ぶるぶる、と拳を握りしめる六郎にも気付かず、深成は、は、と壁の時計に目をやると、あ、と声を上げた。
「そろそろ夕ご飯だ。真砂、もうお風呂出てるかな。じゃあね、六郎さん」
うさぎの巾着をぶんぶんと振って駆けて行く深成の格好に、六郎は、はっとした。
すでに浴衣だ。
なら、すでにお風呂に入った可能性が高いが、真砂は今入っているらしい。
ということは、別々に入った、ということになる。
---な、何だ。……そうだよな。あの幼い深成ちゃんが、まさかそんな……---
どこまでも、六郎の中の深成は幼い子供だ。
……初めて会ったときから、すでに深成も社会人だったはずなのだが。
何も知らない六郎は、とりあえず、ほっとしながら深成を見送った。
部屋に入るなり、深成が歓声を上げた。
二間続きの和室の奥に、露天風呂がある。
「贅沢だね~。露天風呂貸し切りなんて、そうないよ~」
うきうきと早くも浴衣を用意していた深成だったが、はた、と我に返る。
---あれれ? お部屋にお風呂で貸切風呂ってことは、お風呂一緒に入るってこと?---
確かに一人じゃ寂しい、とは言ったが、部屋風呂であれば問題ない。
---けど、家族風呂とかだったら、皆一緒に入るよね……---
真砂の思惑がわからず、深成は浴衣を持ったまま固まった。
真砂はちらりと腕時計に視線を落とし、次いで深成に目をやった。
「飯の前に、風呂入るか?」
「うえぇぇっ?」
びびくん! と深成が飛び上がる。
真砂が怪訝な顔をした。
「何だよ。そのつもりで浴衣用意したんじゃないのか?」
「う、そ、そうだけど。えっと、その……まだほら、時間も早いしさぁ」
赤くなってごにょごにょと言う。
ぶは、と真砂が吹き出した。
「はははっ。そんなに構えんでも、着いて早々そんなことはせんよ」
「え、でも。ほら、一緒にお風呂入ったら、やっぱり……」
結婚して子供もいるぐらいであれば、それこそ家族風呂として皆一緒に入っても何もないかもしれない。
だが真砂と深成は、まだまだ隙あらばらぶらぶしているようなバカップルである。
ちょっとくっついていただけで甘やかな空気が漂うのに、一緒に風呂など何もないわけがない。
「別に部屋風呂だからって、絶対一緒に入らんといかんわけじゃないぜ」
「あ、そ、そっか」
ほ、と息をつき、深成は身体の力を抜いた。
「ま、もうちょっと夜が更けてから、な」
にやにやと言う真砂に、い~っと顔を突き出し、深成は露天風呂に飛び込んだ。
「真砂~。わらわ、ちょっと売店見てくるね」
軽くお風呂に入った後、入れ替わりに入った真砂に言い、深成は一人、ふらふらとロビーの前の売店に向かった。
ちらちらと商品を見ていると、工事の音が聞こえて来た。
---あ、そういえば、何か工事してるとか言ってたな。そういや高山建設って?---
何か聞いたことある、と音のするほうを見ていると、一人の男性がこちらを見、驚いた顔をした。
そして駆け寄ってくる。
「深成ちゃん!」
「え? 誰?」
今しがた買ったお茶のペットボトルを握りしめ、深成は思いっきり不審そうな顔を向けた。
「私だよ。ほら、研修とかで何度か一緒になった……」
被っていたヘルメットを取ったのは海野 六郎だ。
かつてmira商社に研修に来、真砂の下で営業の勉強をしていた。
その後も一度、会社の親睦会などで会ったが。
「あ、ああ……。お久しぶりです」
やっと思い出したものの、それだけだ。
深成にとって六郎は、短期間真砂についていた人、というだけの認識だ。
真砂ありきの存在である。
「どうしたの? 旅行?」
「うん。六郎さんはお仕事だよね? あ、だから真砂、チェックインの時に確認したんだ」
ぽん、と手を叩く深成に、え、と六郎の顔が引き攣った。
「え、あの。深成ちゃん、旅行って、誰と……?」
「真砂」
さらっと答えた深成に、六郎は固まった。
が、すぐに気を取り直す。
---い、いや。今回もこの前みたいな、会社のイベントなのかも。二人とは限らんではないか---
そう思い、きょろきょろと周りを見回してみるが、他に知った顔があるわけでもない。
「あの。もしかして、今回はプライベートな旅行なの……?」
恐る恐る聞いてみる。
深成は思い切り不思議そうな顔で、こっくりと頷いた。
「ま、真砂課長と、二人で……?」
「そうだよ。わらわが温泉に行きたいって言ったから。でも二人で行っても大きいお風呂に一人は寂しいって言ったら、露天風呂付きのお部屋を取ってくれたんだ」
えへへ、と無邪気に言う深成に、六郎の顔はさらに強張った。
---へ、部屋に風呂だとっ? み、深成ちゃんはそれがどういうことか、わかっているのか! 奴め、深成ちゃんの幼さに付け込んで、着々と下心の刃を研ぎやがって……---
ぶるぶる、と拳を握りしめる六郎にも気付かず、深成は、は、と壁の時計に目をやると、あ、と声を上げた。
「そろそろ夕ご飯だ。真砂、もうお風呂出てるかな。じゃあね、六郎さん」
うさぎの巾着をぶんぶんと振って駆けて行く深成の格好に、六郎は、はっとした。
すでに浴衣だ。
なら、すでにお風呂に入った可能性が高いが、真砂は今入っているらしい。
ということは、別々に入った、ということになる。
---な、何だ。……そうだよな。あの幼い深成ちゃんが、まさかそんな……---
どこまでも、六郎の中の深成は幼い子供だ。
……初めて会ったときから、すでに深成も社会人だったはずなのだが。
何も知らない六郎は、とりあえず、ほっとしながら深成を見送った。