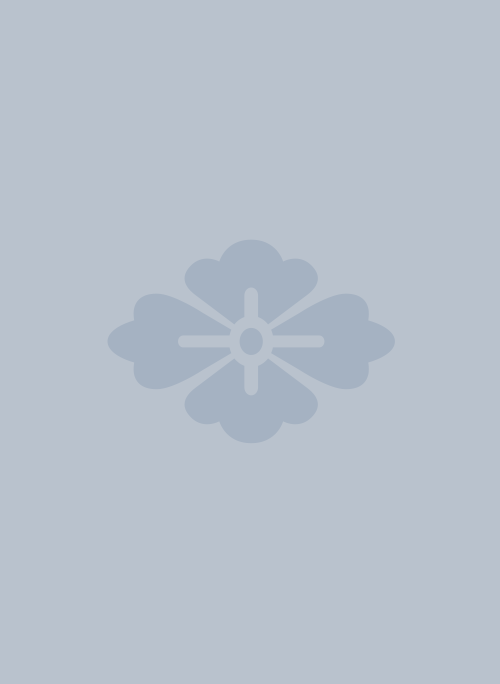「おはよん」
月曜日、深成は晴れやかにフロアに入った。
「おはよう深成ちゃん。何か朝からご機嫌だね」
すでに席についていた六郎が、深成に声をかける。
そして、ちらりと周りを見渡してから、少し声を潜めた。
「あの……。金曜日、ごめんね。何か、傷付けちゃったみたいで」
「ん? ……あ、そういえば。うん、それはもういいよ」
きょとんと小首を傾げる深成は、本当に金曜日の六郎とのことなど忘れていたようだ。
「でも私は、やっぱり心配なんだ。深成ちゃんが、悪い人に付きまとわれてるんじゃないかって」
「あのさぁ。何でそんなに、わらわを心配するの?」
ちょっと眉を寄せて、深成が言う。
う、と六郎が言葉に詰まった。
六郎が深成を心配するのは、深成のことを好いているからだ。
だがそんなこと、本人に言えるわけはない。
六郎が妙な汗を流しているうちに始業のチャイムが鳴り、同時に真砂について回らねばならない六郎は、目の回るような忙しさの渦に呑まれていった。
真砂の言った通り、それからの六郎は、前の席の深成と言葉を交わす暇もないほど忙しくなった。
真砂についてクライアントのところに出向き、帰って来てから打ち合わせ。
真砂が社内の会議のときは、言われた企画書を考えてまとめていく。
経過を報告しては差し戻しを食らい、また作り直し。
真砂の予定をチェックし、間々で業務報告を作っていく。
気が付けば定時はとうに過ぎ、深成の姿はない。
そんな日々が続くにつれて、深成に対する疑惑は隅に追いやられ、初期の気持ちが強くなる。
一番初めに深成を見たときの、『可愛い子だ』という気持ち。
深成への想いが強くなった六郎は、研修が終わる頃には、ある行動に出ようと決心を胸に秘めた。
「よし。企画書もOKだ」
期限の月末。
真砂は六郎の差し出した企画書に目を通して頷いた。
一緒に提出された報告書にハンコを押す。
「この一か月ちょっとで、営業の仕事はわかっただろう?」
「はい。お蔭様で、大分ノウハウも身に着いたと思います。企画案も応用すれば、自社での営業活動に役立ちそうですし。いい経験をさせて頂きました」
真砂にしごかれたお蔭で、何もわからない新人状態の六郎は、一か月ちょっとで立派な営業マンに生まれ変わった。
「明日、社長のところに出向いて、経過を報告する。それによってこの研修をいつまでにするか決めるからな」
「あ、あの。課長はどうお考えですか?」
少し思い詰めたように、六郎が言う。
真砂は少し考えて、顔を上げた。
「俺はもう大丈夫だと思うがな。元々取り組みも真面目だったし、吸収も早い。企画もちゃんと上げてきた。この上に教えることはない。後は社長が直に見て、どう判断するかだ」
---ということは、そろそろここともお別れか。ならば……---
ぐ、と拳を握りしめ、六郎は月半ばで決めていたことを、そろそろ実行に移すことにした。
結局六郎の研修は、この一週間で終了となった。
「いやぁ、さすが真砂課長やわぁ~。どや、もうどこの営業かて、どんと来いやろ?」
一週間前、社長室でミラ子社長は満足そうにそう言ったものだった。
ミラ子社長に挨拶をし、自社に研修終了の旨連絡をし、そんなこんなで最終日。
「深成ちゃん。ちょっといいかな」
そろそろ定時という頃、六郎が深成に声をかけた。
「ん、何? あ、六郎さん、今日でおしまいだね」
ぴょこ、と深成が顔を上げ、キーボードを打ちながら言う。
きょろ、と六郎は周りを見渡し、目に付いた資料室を指差す。
「ちょっと資料室まで、いい?」
「やだ」
躊躇なく断られる。
六郎の心が、若干折れそうになった。
---や、やっぱり前のことが尾を引いてるんだな。そりゃそうか……。でも……---
他に人気のないところは、と探すが、生憎フロアの中にはない。
仕方なく、六郎はエレベーターホールの隅に、深成を連れて行った。
「深成ちゃんにはお世話になったね。あの、何かいろいろあったけど、それについて、ちゃんと伝えておきたいことがあって……」
俯いたままの深成に、六郎は懸命に言った。
ぐ、と拳を握り、言うべきことのタイミングを計る。
月曜日、深成は晴れやかにフロアに入った。
「おはよう深成ちゃん。何か朝からご機嫌だね」
すでに席についていた六郎が、深成に声をかける。
そして、ちらりと周りを見渡してから、少し声を潜めた。
「あの……。金曜日、ごめんね。何か、傷付けちゃったみたいで」
「ん? ……あ、そういえば。うん、それはもういいよ」
きょとんと小首を傾げる深成は、本当に金曜日の六郎とのことなど忘れていたようだ。
「でも私は、やっぱり心配なんだ。深成ちゃんが、悪い人に付きまとわれてるんじゃないかって」
「あのさぁ。何でそんなに、わらわを心配するの?」
ちょっと眉を寄せて、深成が言う。
う、と六郎が言葉に詰まった。
六郎が深成を心配するのは、深成のことを好いているからだ。
だがそんなこと、本人に言えるわけはない。
六郎が妙な汗を流しているうちに始業のチャイムが鳴り、同時に真砂について回らねばならない六郎は、目の回るような忙しさの渦に呑まれていった。
真砂の言った通り、それからの六郎は、前の席の深成と言葉を交わす暇もないほど忙しくなった。
真砂についてクライアントのところに出向き、帰って来てから打ち合わせ。
真砂が社内の会議のときは、言われた企画書を考えてまとめていく。
経過を報告しては差し戻しを食らい、また作り直し。
真砂の予定をチェックし、間々で業務報告を作っていく。
気が付けば定時はとうに過ぎ、深成の姿はない。
そんな日々が続くにつれて、深成に対する疑惑は隅に追いやられ、初期の気持ちが強くなる。
一番初めに深成を見たときの、『可愛い子だ』という気持ち。
深成への想いが強くなった六郎は、研修が終わる頃には、ある行動に出ようと決心を胸に秘めた。
「よし。企画書もOKだ」
期限の月末。
真砂は六郎の差し出した企画書に目を通して頷いた。
一緒に提出された報告書にハンコを押す。
「この一か月ちょっとで、営業の仕事はわかっただろう?」
「はい。お蔭様で、大分ノウハウも身に着いたと思います。企画案も応用すれば、自社での営業活動に役立ちそうですし。いい経験をさせて頂きました」
真砂にしごかれたお蔭で、何もわからない新人状態の六郎は、一か月ちょっとで立派な営業マンに生まれ変わった。
「明日、社長のところに出向いて、経過を報告する。それによってこの研修をいつまでにするか決めるからな」
「あ、あの。課長はどうお考えですか?」
少し思い詰めたように、六郎が言う。
真砂は少し考えて、顔を上げた。
「俺はもう大丈夫だと思うがな。元々取り組みも真面目だったし、吸収も早い。企画もちゃんと上げてきた。この上に教えることはない。後は社長が直に見て、どう判断するかだ」
---ということは、そろそろここともお別れか。ならば……---
ぐ、と拳を握りしめ、六郎は月半ばで決めていたことを、そろそろ実行に移すことにした。
結局六郎の研修は、この一週間で終了となった。
「いやぁ、さすが真砂課長やわぁ~。どや、もうどこの営業かて、どんと来いやろ?」
一週間前、社長室でミラ子社長は満足そうにそう言ったものだった。
ミラ子社長に挨拶をし、自社に研修終了の旨連絡をし、そんなこんなで最終日。
「深成ちゃん。ちょっといいかな」
そろそろ定時という頃、六郎が深成に声をかけた。
「ん、何? あ、六郎さん、今日でおしまいだね」
ぴょこ、と深成が顔を上げ、キーボードを打ちながら言う。
きょろ、と六郎は周りを見渡し、目に付いた資料室を指差す。
「ちょっと資料室まで、いい?」
「やだ」
躊躇なく断られる。
六郎の心が、若干折れそうになった。
---や、やっぱり前のことが尾を引いてるんだな。そりゃそうか……。でも……---
他に人気のないところは、と探すが、生憎フロアの中にはない。
仕方なく、六郎はエレベーターホールの隅に、深成を連れて行った。
「深成ちゃんにはお世話になったね。あの、何かいろいろあったけど、それについて、ちゃんと伝えておきたいことがあって……」
俯いたままの深成に、六郎は懸命に言った。
ぐ、と拳を握り、言うべきことのタイミングを計る。