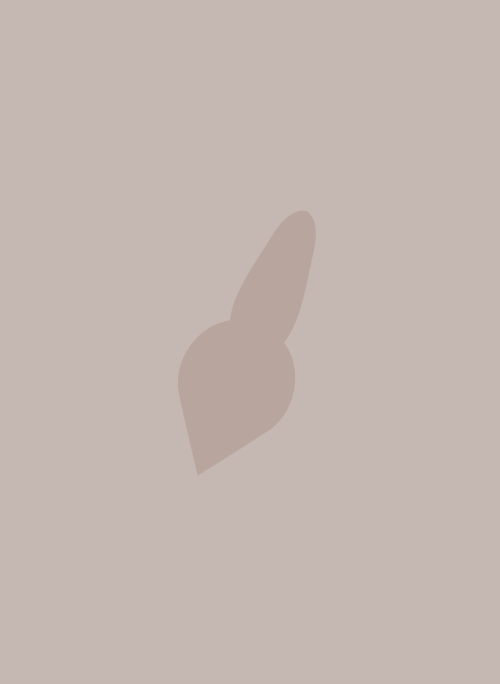「自己紹介が遅れたね。わたしはガジの会の中崎という。彼女は田村だ」
そう言って、男はおれに名刺を手渡した。
「ガジの会って、何すかそれ?」
名刺を見ながら、いぶかしげに聞くと、田村が答えた。
「嫌魔にとりつかれた被害者の会、といったところかしら。とりつかれた者同士で集まって、語り合い、苦労をわかちあうの。嫌魔にとりつかれた人間にとって、もっともつらいのは、孤独。そうでしょう?でも、とりつかれた者同士なら、なぜか嫌悪感を感じることはない。だから、とりつかれた者同士で集まって、嫌魔への対策を話しあったりしているの」
中崎がひきついで言った。
「ぼく達は、嫌魔にとりつかれたひと達を探しては、ガジの会への勧誘をしているんだ。どうだい、君もガジの会に入らないかい?悪い話じゃあないと思うけど」
おれは二人と名刺を見くらべてから、答えた。
「すいません。少しだけ考えさせてもらっていいすか」
中崎は笑みをくずさぬままうなずいた。
「いいとも、何かあったらいつでも、その名刺の住所をたずねてきてくれたまえ」
おれは二人と別れた。
ガジの会の話は、魅力的だなとは思った。しかしいい返事をしなかったのは、二人の挙動に不気味なものを感じたからだ。
あいつら、話している間、一度もまばたきをしなかったんだよ。
ささいなことといえば、ささいなことなんだけど、そのことが妙に気になったんだ。
別れ際に田村がこう言い残した。
「わたしにはわかるわ。あなたはきっとガジの会にくる。嫌魔にとりつかれた人間はけっしてふつうに生きることはできないのだから」
くやしいけど、そいつの言ったとおりになった。