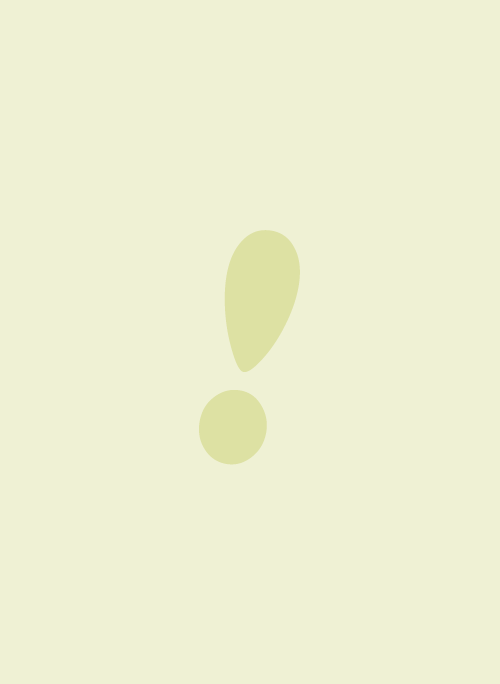ひどく静かに時間は過ぎていった。
まるで、痛みなんて感じていないかのようで、自分がひどく恨めしかった。
愛する人がこの世を去っても、日は昇る。
身体は空腹を訴える。
そういう自分を嫌いだと思った。
援軍は、いたって温厚に俺たち留学生を扱った。
3カ国間で取り決められたしばらくの休戦の間に、荷物をまとめるように指示し、俺たちはそれに従った。
加えて、彼らは、死んだ生徒の家族たちに手紙を書くよう、俺たちに言った。
死の通達は出来るが、最後の様子や遺した言葉を伝えることは出来ないから、と。
それぞれの墓標と、住所とを照らし合わせながら、俺たちは遺族に手紙を書いた。
まるで、痛みなんて感じていないかのようで、自分がひどく恨めしかった。
愛する人がこの世を去っても、日は昇る。
身体は空腹を訴える。
そういう自分を嫌いだと思った。
援軍は、いたって温厚に俺たち留学生を扱った。
3カ国間で取り決められたしばらくの休戦の間に、荷物をまとめるように指示し、俺たちはそれに従った。
加えて、彼らは、死んだ生徒の家族たちに手紙を書くよう、俺たちに言った。
死の通達は出来るが、最後の様子や遺した言葉を伝えることは出来ないから、と。
それぞれの墓標と、住所とを照らし合わせながら、俺たちは遺族に手紙を書いた。