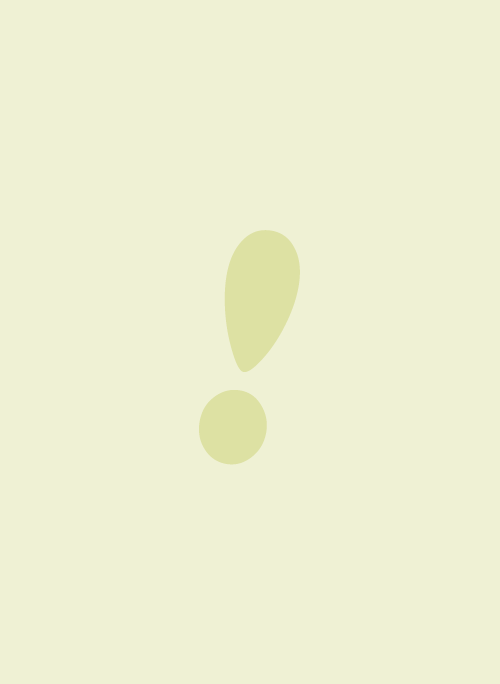静かに静かに、アレンは、私を抱いた。
私は、一つ吐息をつき、アレンを受け入れた。
甘い熱がわき上がる。
鼓動が重なる。
荒い息の色さえ、同じになって溶け合っていく。
その行為の中で、私は深い安らぎに包まれていた。
自分の全てがアレンのためにあるような気さえしていた。
身体の奥から貫いてくる甘やかで熱い痛みがひどく愛おしかった。
私の名前を耳元でささやくアレンの背中につめを立てる。
消えてしまわないように。
私がいなくなってしまわないように。
どうしてだろう?
泣きたいほどアレンが愛おしかった。
自分の全てが変わっていく夜の温度さえ、身体に刻みたいと思った。
「力、抜けるか」
「ん・・・っ、や、無理・・・みたい」
「全部、俺に預けて」
アレンの動きが速くなる。
痛みと愛情が溶けていく。
苦しくて、泣きたいくらい愛しい。
私は、一つ吐息をつき、アレンを受け入れた。
甘い熱がわき上がる。
鼓動が重なる。
荒い息の色さえ、同じになって溶け合っていく。
その行為の中で、私は深い安らぎに包まれていた。
自分の全てがアレンのためにあるような気さえしていた。
身体の奥から貫いてくる甘やかで熱い痛みがひどく愛おしかった。
私の名前を耳元でささやくアレンの背中につめを立てる。
消えてしまわないように。
私がいなくなってしまわないように。
どうしてだろう?
泣きたいほどアレンが愛おしかった。
自分の全てが変わっていく夜の温度さえ、身体に刻みたいと思った。
「力、抜けるか」
「ん・・・っ、や、無理・・・みたい」
「全部、俺に預けて」
アレンの動きが速くなる。
痛みと愛情が溶けていく。
苦しくて、泣きたいくらい愛しい。