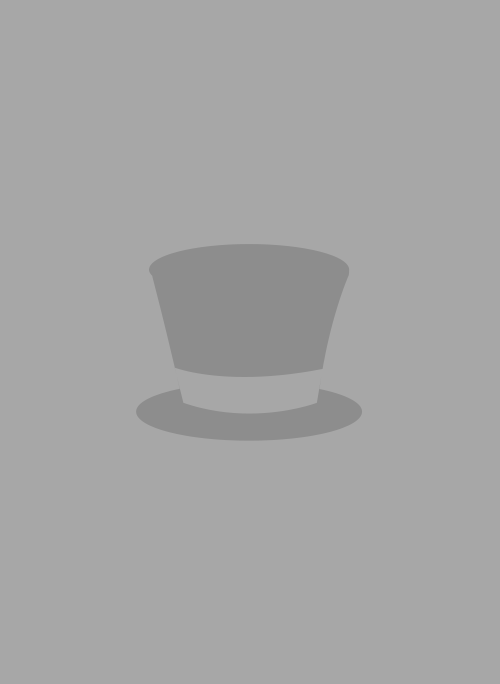「……ごめん」
「いいよ。俺だって血が怖くて騒いでたし…おあいこだろ」
な?と笑いかけると、凪原は安心したように微笑み、ゆっくり立ち上がった。
ゴォン!という爆音がするたびに縮こまってるが、それでも懸命に足を進めようとする姿はひどく愛嬌があった。
「俺だって…お前に迷惑かけてばかりだし。こんな風にお前に頼られるって、なんか新鮮で少し嬉しいんだ」
「………そっか、そっかぁ。でも、人には誰だって弱いところはあるもの。むしろ素直でいいと思う」
「………………そう、かな」
思い出したのは、赤。
弟の体から出た、忌まわしい赤。
雨に濡れたアスファルトの上に広がり、弟の白い服を赤く赤く染め上げていく。