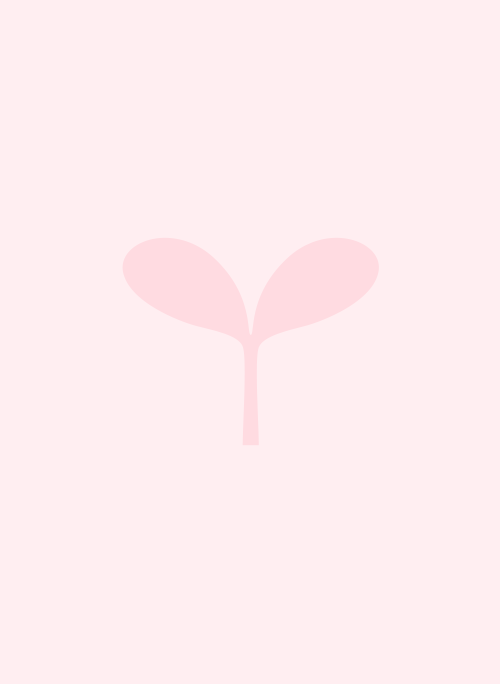「それで、何しに来たの?」
重々しい雰囲気に耐えきれず、ボクは不自然に話題を変えた。
ここへ来たとき、彼女はボクを探してやっとここに辿り着いたというような感じだった。
何か用があったに違いない。
「これを、湯川くんに渡しに」
彼女は思い出したように、制服のポケットから何やら白い封筒を取り出して、ボクの前に差し出した。
「手紙?」
手渡された封筒をよく見てみると、見覚えのある字体で「ヒロへ」と書かれていた。
ミツキの字だ。
すぐさま封を切って、中から一枚の便箋を取り出す。
――ヒロへ、追ってきちゃダメだからね
たった一行。
それだけが、記されていた。
「なに、これ…」
手紙を持つ手が小刻みに震える。
追ってきちゃダメなんて、そんなの、遺書にしては冗談が過ぎる。
「自殺する直前に、ミツキから預かったの」
「自殺の直前?」
「そう、自殺の直前。それを手渡されたとき、もしかしたら死のうとしてるのかもしれないって、なんとなくそう思った」
淡々とそう言ってのける彼女に、ボクは激しい違和感を覚えた。
ボクも人のことは言えないけれど。
でも、どう考えても、それは親友が言えた言葉じゃない。
「なら、どうして。
どうしてミツキを止めなかったの?」
「止められなかった。それはエゴだと思ったから。私はミツキに永遠の闇の中で生きることを強いれなかった」
すべてを悟っているかのような、奇妙なくらいに落ち着いた物言いだった。
「永遠の闇?なにそれ」
「そっか。ミツキ、湯川くんには話してなかったんだ…」
何か、ボクの知らないミツキの秘密を、彼女は知っているらしい。
「何?どういうこと?」
急かすように問い詰めれば、彼女は少し躊躇い気味に口を開いた。
「ミツキ、病気だったの。
いずれ全盲になってしまう病気」
「え…」
告げられた新たな真実に、ボクは一瞬、時間が止まってしまったかのような感覚に陥った。
「……ウソだ、そんなこと一言も…」
一言も言わなかった、ボクには。