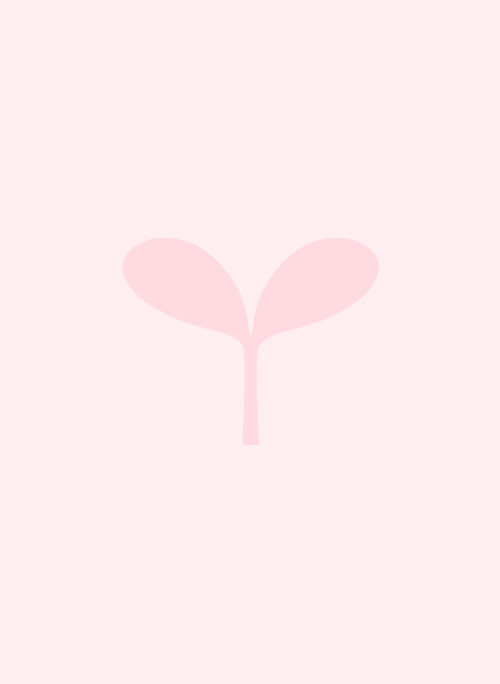無性に幼馴染の絵を見たくなった。
彼女の書き残した絵がいくつかあるかもしれないと期待して、放課後、美術室の中を探し回った。
でも、彼女の絵はどこにもなかった。
おそらく、全部彼女の両親に引き取られたあとなんだろう。
――もう一度、見たかったのにな。
落胆して、近くの席に崩れるように腰かけたそのときだった。
「いた、湯川くん」
ドアが開いて、見知った顔の女子が現れた。
幼馴染の、たった一人の親友だった、谷村香奈子。
「何、してるの?」
美術部でもないボクが1人、放課後美術室にいるのを奇妙に思ったらしい。
「ミツキの絵、探してた」
ボクの口から出た幼馴染の名前に、谷村さんはかすかに瞳を大きくする。
そして、答えた。
「ミツキの絵、もうないの、どこにも」
「どこにも…?」
意味深な彼女の言葉に、ボクは首を傾げた。
「“ミツキの絵だったもの”なら、ミツキの家にあるけど」
「どういう意味?」
「ミツキが死んだあと、美術室にあったミツキの絵は全部、黒い絵の具で塗りつぶされてたの。賞をとった油絵も、スケッチブックの中の絵も全部」
ボクの表情をチラチラと窺いながら、ゆっくりとそう告げる彼女。
ミツキの絵が塗りつぶされていたというその事実に、ボクは何か怒りに近いような感情を覚えた。
「……誰がそんなこと」
奥歯を噛むようにボクがそう呟くと、谷村さんは躊躇なくその名を口にした。
「ミツキ」
「え?」
聞き間違いだろうかと、ボクはじっと彼女の両眼を捕える。
彼女もまた、ボクを真っ直ぐと見据えていた。
「ミツキが自分でやったの、多分」
しっかりとした響きで、彼女は告げた。
けれど、その言葉の意味がボクには分からない。
ミツキが自分の絵を黒く塗りつぶすなんて、そんなこと絶対にあり得ないと思った。
「根拠はあるの?」
「………」
視線を外して黙り込む彼女に、ボクはすかさず言葉を重ねた。
「ミツキをいじめてた人たちの仕業かも」
「……いじめのこと、知ってたんだね、湯川くん」
責めるような言い方ではなかった。
ただ、なんだかとても傷ついたような表情を見せられて、ボクは少し苛立った。
ミツキを助けなかったことを、ボクは彼女が死んだ今でも後悔していない。
ボクは、優しい人にはなりたくなかったから。
だから、仕方なかったことなんだ。
なのに。
ミツキが死んで、
絵が見たくなって、それで。
ずっと、気持ち悪い。
「知ってたよ。知ってたけど、何もしなかった。軽蔑した?」
軽蔑したいなら、思う存分軽蔑すればいい。
人間なんてみんな、保身にまみれた偽善者ばかりで。
他人を貶めることで快楽を得る生き物なんだから。
いくら蔑まされようと、それはボクの本質で、人間の本能で、どうしようもないことだ。
「軽蔑なんてできないよ。私も湯川くんと同じだから」
懺悔にも似た谷村さんの言葉に、ボクは眉を顰めた。
ボクと同じということはつまり、彼女もミツキを見捨てた罪人で。
でも、彼女の場合はずっと、
その罪悪感に苛まれ続けてるんだろう、
ボクと違って。