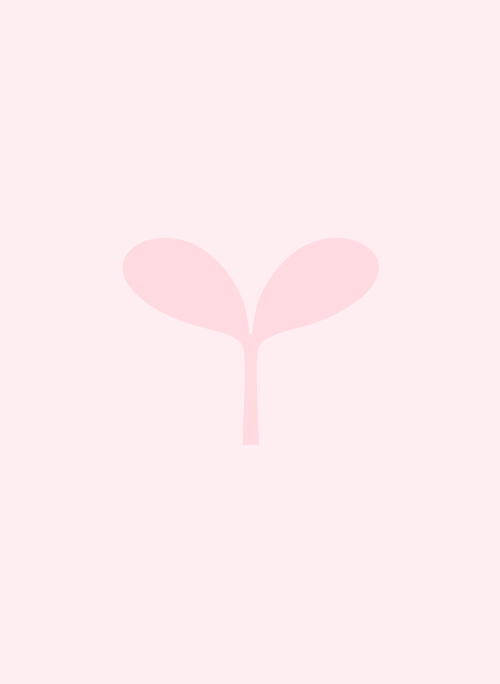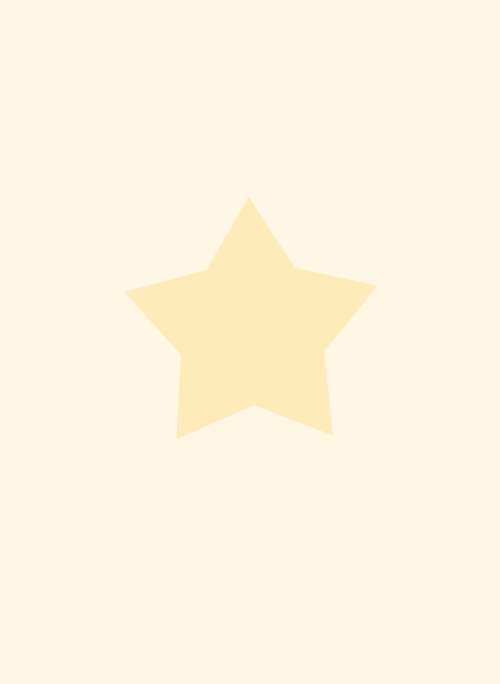それは、突然だった。彼女は僕を揺り起こした。
「お願い、答えて。アツキが崖から落ちたのよ」
「落ち着いて」
「あなたが手を差し伸べてくれていたら、もしかしたら……」
「サキちゃん。それは違う。僕は彼を見守っていたのだから」
「助かったかもしれなかったのに、どうにかなったかもしれないのに……。どうして助けてくれなかったの? なぜ、助けなかったの?」
「言ったろう? 僕は見守っていたんだ。広く大きな心で、彼を包み込んで……」
「何もしなかったのね? 何もしなかったんでしょ? 見守るっていうのは、ただ見届けるってことじゃないハズよ!」
「僕はそうやって、いつも彼から離れず、ずっと見守ってきた。彼もそれを望んでいた」
「ウソよ」
「彼が君に、ハッキリとそう言ったのかい?」
「……そうじゃないけど」
「じゃあ、どうなんだ?」
「あたし……」
「違うんだろう?」
「でも……救えたかもしれない彼を、救わなかった。あなたの言う見守るって、自分の身を守ることじゃない!」
「それは、君の‘答え’だ。僕のとは違う」
「えっ?」
「君は──あの場にいなかった」
「……」
「それが僕の‘答え’なんだ」
「──ねぇ、アツキとケンカして、あたしが来なかったことを責めてるの?」
「君が僕を責めているんだ。でも、僕は何とも思わないから、安心して」
「あなたのことばかり言うから……。だから、ケンカになったのよ」
「分かってる」
「分かってる? なら……」
「後悔してるんだろう? 今はとても、君は後悔している」
「うん」
「気持ちの整理が付いたら、君も、あの崖に行くがいい。アツキの為に、一緒に花を贈ろう」
「あなたと行くの?」
「僕がいなければ、君がどうなってしまうか分からないからね」
「……ありがとう。でも大丈夫。心配しないで。バカなマネはしないから。一人で行けるから」
「アツキはもう戻っては来ない。彼の心は死んでしまった。でも……」
「でも?」
「これからは僕が、君を見守る。君が望むように、彼よりもずっと広く、大きな心で……」
言い終わる前に、彼女は消えた。こうして僕は、また一人、葬った。
「お願い、答えて。アツキが崖から落ちたのよ」
「落ち着いて」
「あなたが手を差し伸べてくれていたら、もしかしたら……」
「サキちゃん。それは違う。僕は彼を見守っていたのだから」
「助かったかもしれなかったのに、どうにかなったかもしれないのに……。どうして助けてくれなかったの? なぜ、助けなかったの?」
「言ったろう? 僕は見守っていたんだ。広く大きな心で、彼を包み込んで……」
「何もしなかったのね? 何もしなかったんでしょ? 見守るっていうのは、ただ見届けるってことじゃないハズよ!」
「僕はそうやって、いつも彼から離れず、ずっと見守ってきた。彼もそれを望んでいた」
「ウソよ」
「彼が君に、ハッキリとそう言ったのかい?」
「……そうじゃないけど」
「じゃあ、どうなんだ?」
「あたし……」
「違うんだろう?」
「でも……救えたかもしれない彼を、救わなかった。あなたの言う見守るって、自分の身を守ることじゃない!」
「それは、君の‘答え’だ。僕のとは違う」
「えっ?」
「君は──あの場にいなかった」
「……」
「それが僕の‘答え’なんだ」
「──ねぇ、アツキとケンカして、あたしが来なかったことを責めてるの?」
「君が僕を責めているんだ。でも、僕は何とも思わないから、安心して」
「あなたのことばかり言うから……。だから、ケンカになったのよ」
「分かってる」
「分かってる? なら……」
「後悔してるんだろう? 今はとても、君は後悔している」
「うん」
「気持ちの整理が付いたら、君も、あの崖に行くがいい。アツキの為に、一緒に花を贈ろう」
「あなたと行くの?」
「僕がいなければ、君がどうなってしまうか分からないからね」
「……ありがとう。でも大丈夫。心配しないで。バカなマネはしないから。一人で行けるから」
「アツキはもう戻っては来ない。彼の心は死んでしまった。でも……」
「でも?」
「これからは僕が、君を見守る。君が望むように、彼よりもずっと広く、大きな心で……」
言い終わる前に、彼女は消えた。こうして僕は、また一人、葬った。