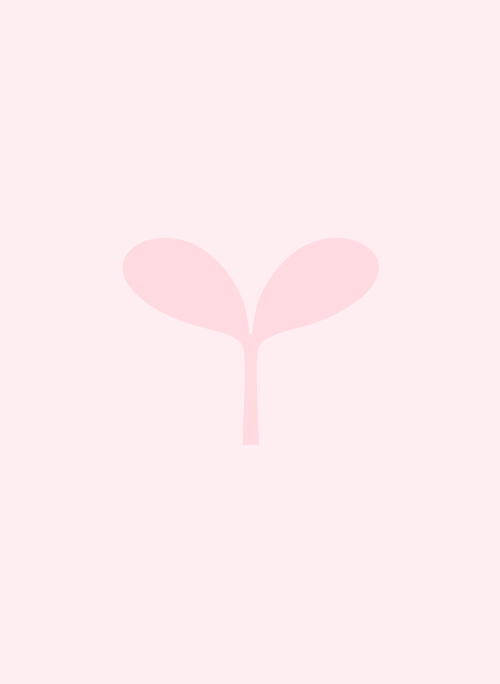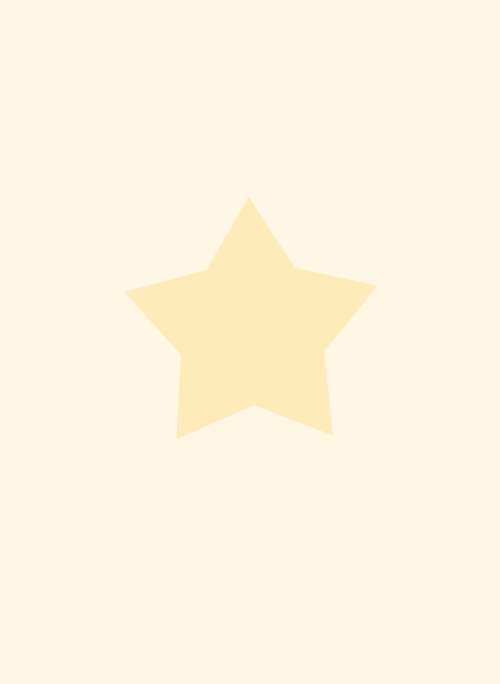「最近の若者は、イヤホンのしすぎで、耳で音の聞き分け出来なくなっているそうですよ」
電車が最寄り駅を過ぎてしまい、途方にくれていた時だった。
誰だか思い出せないのだが、つり革にぶら下がっていると、隣にいた小柄な初老の男から、声をかけられた。
なかなかお洒落で身なりがいい。傘を肘にかけ、イギリス紳士のようでもある。
咄嗟に取引先の人かもしれない、と思った。
「はい……」
私は会社が終わり、帰宅途中だった。迂闊にもため息を着いたようにも聞こえる返事をしてしまった。
「電車の中で、会話ができるのは、脳が判断して聞き分けが出来ているからなんですよ。今の人は、それができない」
「そうなんですか」
「イヤホンは全て、聞く情報でしょう? 脳は聞き分けをする必要がない訳です。そして、それに慣れてしまうと、脳が訓練されません。だから、イヤホンのない街が騒がしく聞こえる。全てを受け入れてしまいますからね。余分な音が多いのです」
「はあ」
「不快ですから、ついついイヤホンをつけて、聞き慣れた『ノイズ』でかき消そうとします。まさに悪循環ですよ」
「田舎なら、虫の声や川のせせらぎなどですかね」
「自然界の音……そういったものに耳を傾けて、脳は発達するのです」
窓から見えたネオンが糸を引く。ひとしきり話し終わったようなので、そろそろ誰なのか突き止めようと思った時、電車が減速しだした。
そしてすぐに金色に輝いた稲穂の見渡せる、知らない駅に止まる。
「人って不思議なものですよね。聞き分けの良い人、悪い人って言いますでしょう?」
フフフ、と口ずさんで、男は電車を降りて行く。
背中を見送る私に、サヨウナラと挨拶をするかのように傘で合図をした。反対側のホームの端まで歩くと、男は立ち止まり、振り向く。
確かに見覚えのある男だった。ニッコリと微笑んでいる。
しかし……思い出せない。記憶のどこかにしまい込んでしまったのだろうか?
傘の動きを追っていると、手招きしているようにも見える。
私は目を瞑った。──再び顔を挙げた時、忽然と私の前から消えていた。
そして……、突然グニャリと空間が歪む。私は雑巾のように捻られた車両に挟まれ、生き絶えたのである。
電車が最寄り駅を過ぎてしまい、途方にくれていた時だった。
誰だか思い出せないのだが、つり革にぶら下がっていると、隣にいた小柄な初老の男から、声をかけられた。
なかなかお洒落で身なりがいい。傘を肘にかけ、イギリス紳士のようでもある。
咄嗟に取引先の人かもしれない、と思った。
「はい……」
私は会社が終わり、帰宅途中だった。迂闊にもため息を着いたようにも聞こえる返事をしてしまった。
「電車の中で、会話ができるのは、脳が判断して聞き分けが出来ているからなんですよ。今の人は、それができない」
「そうなんですか」
「イヤホンは全て、聞く情報でしょう? 脳は聞き分けをする必要がない訳です。そして、それに慣れてしまうと、脳が訓練されません。だから、イヤホンのない街が騒がしく聞こえる。全てを受け入れてしまいますからね。余分な音が多いのです」
「はあ」
「不快ですから、ついついイヤホンをつけて、聞き慣れた『ノイズ』でかき消そうとします。まさに悪循環ですよ」
「田舎なら、虫の声や川のせせらぎなどですかね」
「自然界の音……そういったものに耳を傾けて、脳は発達するのです」
窓から見えたネオンが糸を引く。ひとしきり話し終わったようなので、そろそろ誰なのか突き止めようと思った時、電車が減速しだした。
そしてすぐに金色に輝いた稲穂の見渡せる、知らない駅に止まる。
「人って不思議なものですよね。聞き分けの良い人、悪い人って言いますでしょう?」
フフフ、と口ずさんで、男は電車を降りて行く。
背中を見送る私に、サヨウナラと挨拶をするかのように傘で合図をした。反対側のホームの端まで歩くと、男は立ち止まり、振り向く。
確かに見覚えのある男だった。ニッコリと微笑んでいる。
しかし……思い出せない。記憶のどこかにしまい込んでしまったのだろうか?
傘の動きを追っていると、手招きしているようにも見える。
私は目を瞑った。──再び顔を挙げた時、忽然と私の前から消えていた。
そして……、突然グニャリと空間が歪む。私は雑巾のように捻られた車両に挟まれ、生き絶えたのである。