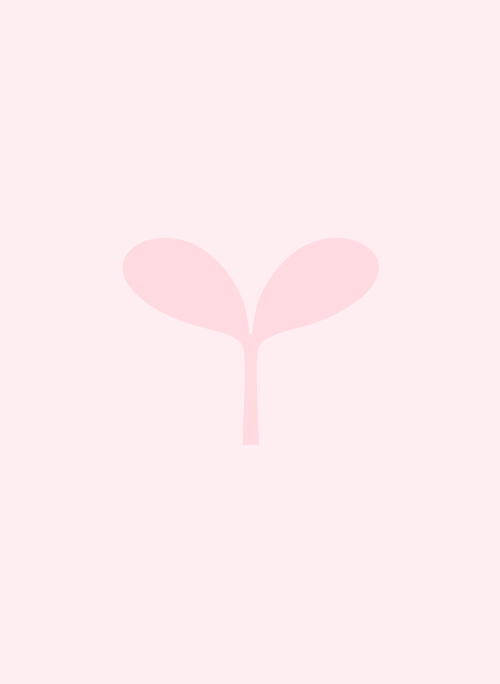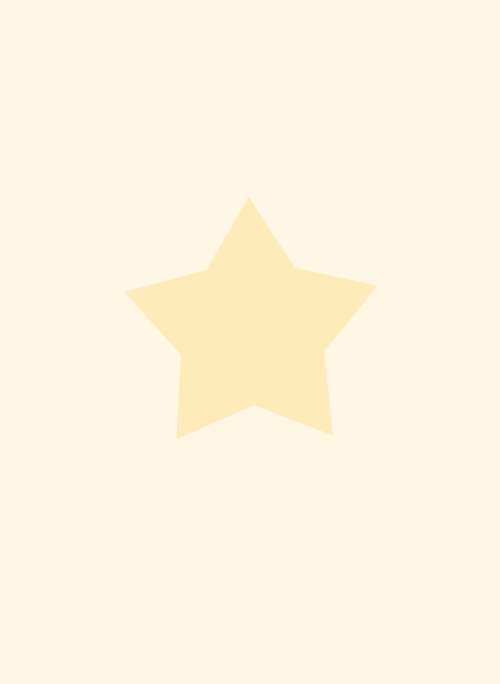校舎の屋上で空を見ながら、学生服を着た三人の高校生が話をしている。
一人は両腕を頭の後ろに回して寝っ転がり、一人は猫背にあぐら、唯一の女子は下着が見えないようにガードしつつ、三角座りだ。湿ったような色が固着したコンクリートとの間には、柔らかいハンカチを敷いている。
「ねぇ、このどこまでも青い空を眺めていると、日本は平和だなって思うの」
カタカナで言えばマシになるが、それでもいわゆるおかっぱ頭の喜久子が、話を切り出した。
「平和? そんなことないよ。期末テストが迫ってるし、勉強しなきゃ」
琉太が猫背のまま反応する。
「やれやれって感じ。溜め息が出るわ」
「どういう意味だよ?」
「テストだどうの言っている間にも、世界の何処かで戦争をやってるし、小さな子供たちが犠牲になっている。アンタには彼等の悲鳴が聞こえないの?」
琉太が不服そうにあぐらを外し、友幸に目をやる。
「そうかもしれないけどさ……。友幸、お前はどう思うよ。僕らは僕らの世界で生きているだけで、非難されるのか?」
「非難じゃないわ」
喜久子が割って入る。
「ただ、呑気に空を眺めていられるのも、この国が守られているってこと。大国の軍事力を背景にした幻想……」
「核兵器の話? もしかして喜久子は、日本も核を持つべきだという意見なの?」
「核武装、すべきよ」
──友幸は空を眺めていた。透き通った核弾頭が瞳の表面で交差する。
「キクちゃん。それは違うよ」
友幸がゆっくりと体を起こす。
「どう違うのよ?」
「短絡的だよ」
「じゃあ、どうやって国を守るの? 皆で仲良くお手々繋いで、本気で解決すると思ってるの?」
「力のバランスだけで物事を捉えたら、見えるものも見えなくなる」
「抽象的な言い回しね。具体的に、何も言えないんじゃない」
突然、チャイムの音が鳴り響く。三人が同じように息を吸う空間だ。
「時間切れ……ね」
琉太も友幸も黙っていた。青かった空は、いつの間にか黒い雲に覆われ、ぽつりぽつりと雨粒が落ちる。
漸く友幸が立ち上がる。引き留めるように喜久子の左肩に手を置いた。
「傘が要るわ」
喜久子はそう呟き、友幸の手を祓った。
一人は両腕を頭の後ろに回して寝っ転がり、一人は猫背にあぐら、唯一の女子は下着が見えないようにガードしつつ、三角座りだ。湿ったような色が固着したコンクリートとの間には、柔らかいハンカチを敷いている。
「ねぇ、このどこまでも青い空を眺めていると、日本は平和だなって思うの」
カタカナで言えばマシになるが、それでもいわゆるおかっぱ頭の喜久子が、話を切り出した。
「平和? そんなことないよ。期末テストが迫ってるし、勉強しなきゃ」
琉太が猫背のまま反応する。
「やれやれって感じ。溜め息が出るわ」
「どういう意味だよ?」
「テストだどうの言っている間にも、世界の何処かで戦争をやってるし、小さな子供たちが犠牲になっている。アンタには彼等の悲鳴が聞こえないの?」
琉太が不服そうにあぐらを外し、友幸に目をやる。
「そうかもしれないけどさ……。友幸、お前はどう思うよ。僕らは僕らの世界で生きているだけで、非難されるのか?」
「非難じゃないわ」
喜久子が割って入る。
「ただ、呑気に空を眺めていられるのも、この国が守られているってこと。大国の軍事力を背景にした幻想……」
「核兵器の話? もしかして喜久子は、日本も核を持つべきだという意見なの?」
「核武装、すべきよ」
──友幸は空を眺めていた。透き通った核弾頭が瞳の表面で交差する。
「キクちゃん。それは違うよ」
友幸がゆっくりと体を起こす。
「どう違うのよ?」
「短絡的だよ」
「じゃあ、どうやって国を守るの? 皆で仲良くお手々繋いで、本気で解決すると思ってるの?」
「力のバランスだけで物事を捉えたら、見えるものも見えなくなる」
「抽象的な言い回しね。具体的に、何も言えないんじゃない」
突然、チャイムの音が鳴り響く。三人が同じように息を吸う空間だ。
「時間切れ……ね」
琉太も友幸も黙っていた。青かった空は、いつの間にか黒い雲に覆われ、ぽつりぽつりと雨粒が落ちる。
漸く友幸が立ち上がる。引き留めるように喜久子の左肩に手を置いた。
「傘が要るわ」
喜久子はそう呟き、友幸の手を祓った。