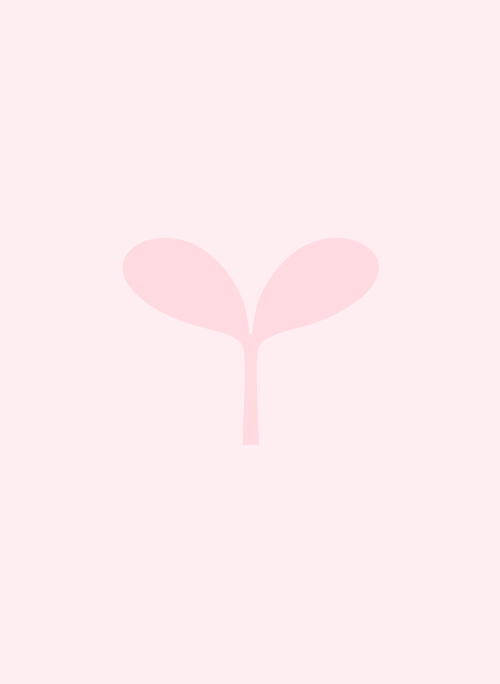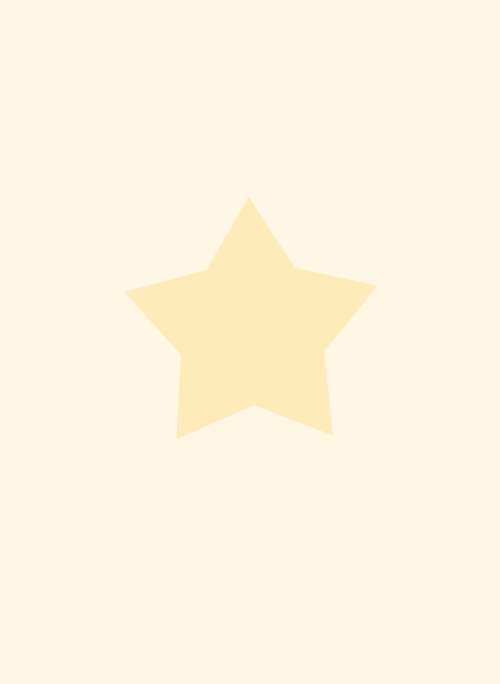妻はまだ、投票所から出てこない。先に済ませた私は小さな娘を連れ、小学校の運動場に出た。
「ねえ、お父さん。あそぼ」
くりくりまなこが話し掛ける。柔らかく手を繋いでいた私は、しずかに足を止める。
「何して遊ぼうか?」
「えーとね、えーと……」
あたりを見回しても、なかなか答えが出ない。娘は目を点にし、考えている。
「お父さんは何したい?」
油断していた訳ではないが、突然バトンが回ってきた。
「そうだな」
緑色で、移動式のバスケットに目が止まる。
「あそこまで、競走しよっか? 駆けっこ」
「うん、いいよ。どっちが速いか勝負ね」
娘はすぐに走ろうと身構える。ほっぺの上の真剣な眼差しが、堪らない。
「じゃあ行くよ。よーい、どん!」
娘が勢いよく飛び出し、私がその後に続く。
抜きそうで抜かない。歩幅を小さく、足音を立て、チラチラと姿を見せては後退する。我ながら見事な演出だ。
「やったー! いっちばーん!」
僅かの差だった。塗装の剥げた支柱に、娘がタッチした。
「速かったねー」
娘は肩で息をしている。
「今度はアッチの鉄棒まで走ろっか?」
実は私もかなり息が上がっていたが、強がったのだ。
「ちょっと、お休みしよーよ」
娘はその場にしゃがみ、すぐに地面をいじり出した。
「手が汚れるから、やめなさい」
妻がよく言っていたセリフが、つい口から滑り落ちた。
「こうやっていると、何か見付かるかもしれないよ」
小さな背中がそんなことを言う。
「そうなんだ」
「スズメの涙とか、拾うの」
「スズメの涙?」
「うん。ホラ、こんなやつ……」
キラキラと光る小さな砂粒が、手の平の真ん中で転がった。
「何やってるの? そんなことしたら、手が汚れるじゃない」
日傘をさした妻が私たちを見付けて、やって来る。
「いいさ。スズメの涙を拾っているみたいだから」
「何それ?」
「多分、もう僕たちには気付かないものだよ」
差し出した手の中で、先ほど貰った砂粒がキラリと光る。
「ふうん」
妻はそう言うと、娘に視線を移し、クルクルと日傘を回した。
「ねえ、お父さん。あそぼ」
くりくりまなこが話し掛ける。柔らかく手を繋いでいた私は、しずかに足を止める。
「何して遊ぼうか?」
「えーとね、えーと……」
あたりを見回しても、なかなか答えが出ない。娘は目を点にし、考えている。
「お父さんは何したい?」
油断していた訳ではないが、突然バトンが回ってきた。
「そうだな」
緑色で、移動式のバスケットに目が止まる。
「あそこまで、競走しよっか? 駆けっこ」
「うん、いいよ。どっちが速いか勝負ね」
娘はすぐに走ろうと身構える。ほっぺの上の真剣な眼差しが、堪らない。
「じゃあ行くよ。よーい、どん!」
娘が勢いよく飛び出し、私がその後に続く。
抜きそうで抜かない。歩幅を小さく、足音を立て、チラチラと姿を見せては後退する。我ながら見事な演出だ。
「やったー! いっちばーん!」
僅かの差だった。塗装の剥げた支柱に、娘がタッチした。
「速かったねー」
娘は肩で息をしている。
「今度はアッチの鉄棒まで走ろっか?」
実は私もかなり息が上がっていたが、強がったのだ。
「ちょっと、お休みしよーよ」
娘はその場にしゃがみ、すぐに地面をいじり出した。
「手が汚れるから、やめなさい」
妻がよく言っていたセリフが、つい口から滑り落ちた。
「こうやっていると、何か見付かるかもしれないよ」
小さな背中がそんなことを言う。
「そうなんだ」
「スズメの涙とか、拾うの」
「スズメの涙?」
「うん。ホラ、こんなやつ……」
キラキラと光る小さな砂粒が、手の平の真ん中で転がった。
「何やってるの? そんなことしたら、手が汚れるじゃない」
日傘をさした妻が私たちを見付けて、やって来る。
「いいさ。スズメの涙を拾っているみたいだから」
「何それ?」
「多分、もう僕たちには気付かないものだよ」
差し出した手の中で、先ほど貰った砂粒がキラリと光る。
「ふうん」
妻はそう言うと、娘に視線を移し、クルクルと日傘を回した。