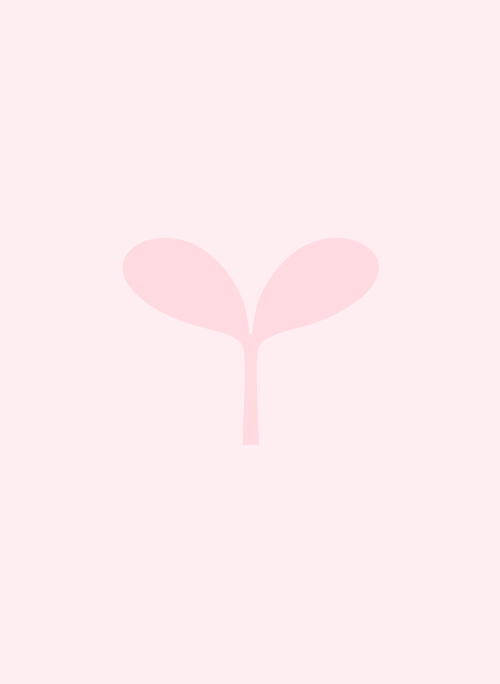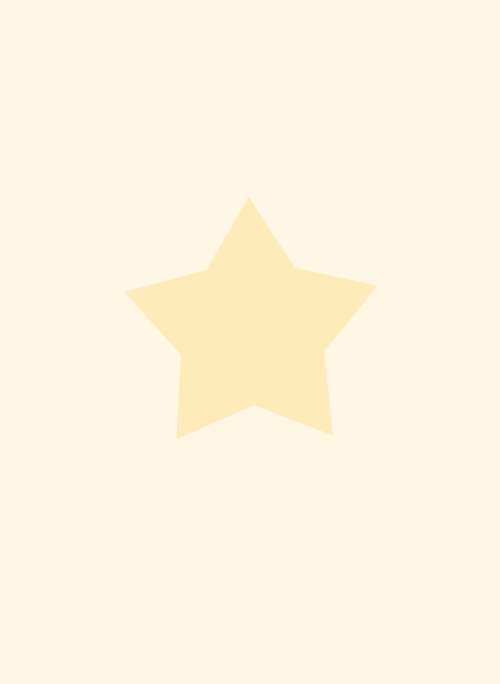西海ルイ子が都会での仕事を辞め故郷に帰った時、既に五十を過ぎていた。
死んだ両親が唯一残してくれた海岸沿いの小さな家も潮風に晒され、老朽化が著しい。
帰ってきてから夕陽を横に、久し振りに海岸を歩く。しかし、ルイ子の知っている美しい景色は、そこにはなかった。空き缶にペットボトル、スーパーのレジ袋……。住民が不法投棄したであろう生活ゴミの山が、進行を妨げた。
──商店街で居酒屋を営む幼馴染みの南虎吉(とらきち)と、営業時間が過ぎてから一杯飲んだ。
幼い頃、虎吉とルイ子の家は隣同士で、一才下の虎吉はルイ子の僕のようなものだった。中学生の卒業を目前にルイ子の両親が浜で水死し、町を出るまで、その関係は続いた。
「なあ、ルイ姉。今更何でこんなヨレヨレの田舎に戻って来たんよ」
筋肉隆々の二の腕をテーブルに突き出し、ルイ子に日本酒を注ぐ。既に病気で妻を亡くし、今は独り身だった。
「ねえ、虎ちゃん」
虎吉が味気ない酒を舐める。酔えるのは、妻を思いながら飲む酒だけだった。
「何で海岸があーなちゃったの?」
気まずそうに顔を背け、虎吉はまだ残っている自分の酒を飲む。
「……なんかさ。外から来た奴らが捨てやがるんだ。始めは皆で監視したり、掃除したり……」
ルイ子は虎吉に注いでやる。すんません、と虎吉が会釈する。
「手に負えなくなってから、いつの間にか、当の住民まで捨て出して……」
「それで、アンタも棄てたの? 虎吉」
ルイ子が一升瓶の底をガツンと置く。暫くして、コクリと頷いた虎吉の頭を、ルイ子は力一杯叩いた。
「ごめんよ、ルイ姉……」
コップが弾け飛び、虎吉が両手で頭を抱え、震えている。その様子を見て、ルイ子はゆっくりと手を下げた。
「バカね。もう真似しちゃだめ。わかった?」
「本当に、ごめんよ」
それから三日後の事だった。目的を失っていたルイ子の心が決まる。
「虎ちゃん、次の選挙に立候補するわ」
「……ん、ええっ!」
「市長選挙に立候補して、アタシがこの町をきれいにするの。無投票改選も、今回でおしまいよ」
虎吉の瞳が丸くなる。完全に取り残された目だ。
──その晩、結局二人で飲み明かした。ヤケに、旨い酒だった。
死んだ両親が唯一残してくれた海岸沿いの小さな家も潮風に晒され、老朽化が著しい。
帰ってきてから夕陽を横に、久し振りに海岸を歩く。しかし、ルイ子の知っている美しい景色は、そこにはなかった。空き缶にペットボトル、スーパーのレジ袋……。住民が不法投棄したであろう生活ゴミの山が、進行を妨げた。
──商店街で居酒屋を営む幼馴染みの南虎吉(とらきち)と、営業時間が過ぎてから一杯飲んだ。
幼い頃、虎吉とルイ子の家は隣同士で、一才下の虎吉はルイ子の僕のようなものだった。中学生の卒業を目前にルイ子の両親が浜で水死し、町を出るまで、その関係は続いた。
「なあ、ルイ姉。今更何でこんなヨレヨレの田舎に戻って来たんよ」
筋肉隆々の二の腕をテーブルに突き出し、ルイ子に日本酒を注ぐ。既に病気で妻を亡くし、今は独り身だった。
「ねえ、虎ちゃん」
虎吉が味気ない酒を舐める。酔えるのは、妻を思いながら飲む酒だけだった。
「何で海岸があーなちゃったの?」
気まずそうに顔を背け、虎吉はまだ残っている自分の酒を飲む。
「……なんかさ。外から来た奴らが捨てやがるんだ。始めは皆で監視したり、掃除したり……」
ルイ子は虎吉に注いでやる。すんません、と虎吉が会釈する。
「手に負えなくなってから、いつの間にか、当の住民まで捨て出して……」
「それで、アンタも棄てたの? 虎吉」
ルイ子が一升瓶の底をガツンと置く。暫くして、コクリと頷いた虎吉の頭を、ルイ子は力一杯叩いた。
「ごめんよ、ルイ姉……」
コップが弾け飛び、虎吉が両手で頭を抱え、震えている。その様子を見て、ルイ子はゆっくりと手を下げた。
「バカね。もう真似しちゃだめ。わかった?」
「本当に、ごめんよ」
それから三日後の事だった。目的を失っていたルイ子の心が決まる。
「虎ちゃん、次の選挙に立候補するわ」
「……ん、ええっ!」
「市長選挙に立候補して、アタシがこの町をきれいにするの。無投票改選も、今回でおしまいよ」
虎吉の瞳が丸くなる。完全に取り残された目だ。
──その晩、結局二人で飲み明かした。ヤケに、旨い酒だった。