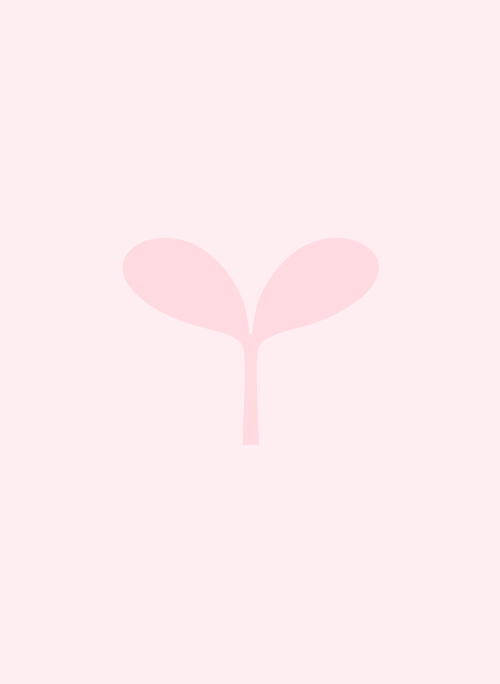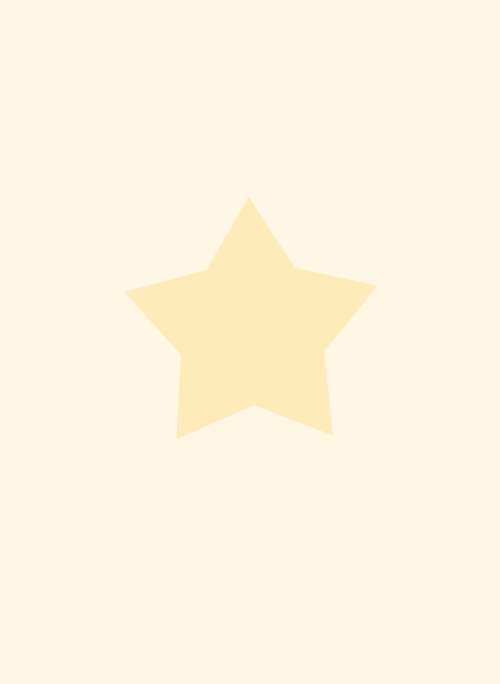仕事を無理矢理に終わらせ、定時に退社。慌ただしく電車に飛び乗る。
なぜそんなに急いでいるのか?
それは、昼休みの終わり際に気付いた一通のメールが原因だった。
差出人は妻だった。機嫌よく遊んでいた幼い娘が、泣き出したという。
その程度でメールをするなと最初は思ったのだが、号泣しているというのだ。
状況が飲み込めず、無性に心配になった私は、急いで自宅に戻ってきた。玄関の扉を開けると、眉の垂れ下がった妻が待っていた。助けを求めているのがひと目で分かった。
「おかえりなさい」
「ただいま。いったいどうしたんだい?」
「それがね……」
おとうさん、と泣きながら奥の部屋から娘が抱きついてきた。
「おい、どうしたんだ?」
まだ靴も脱いでいない私が娘と目線を合わせても、何も言わない。
「私たちのビデオを見ていたのよ」
妻が見かねて、教えてくれた。
「ビデオ?」
「フィジーで撮った、私たちのほら……結婚式のビデオ! 最初は嬉しそうに観ていたのよ」
「フーン。それで?」
「それが突然、お父さんがどっかに行っちゃう──って、大泣きよ」
娘が目に涙を浮かべて話そうとするが、思い出してしまったのか、また泣き出してしまう。
「どうして泣くの?」
私のスラックスで涙を拭う娘。
「ねぇ、子供って親を選ぶって、聞いたことない?」
「何それ? 知らないよ。そうなの?」
「本当かどうかは分からないけど、高いお空から見下ろしていて、私たちが面白そうだったんだって。それでお父さんに会いに来たって」
「泣きながら、そんなこと言ってたの?」
面白い話である。もしそうなら……。顔を埋めている娘の頭を撫でながら、ふと、気付いたことがあった。
「因みに、僕の相手が君だって、気付いているの?」
妻の顔が引き吊った。もはや、口元が台形だ。
「お願い。今はまだ、言わないで」
スリッパの音を立てて慌ただしくキッチンに戻って行く妻。娘が自分で気付くまで、そう遠くはないだろう。
私は踵を潰さないように靴を脱ぎ、娘を抱き上げた。
「重!?」
言うまでもないが、娘は必死にしがみついている。
なぜそんなに急いでいるのか?
それは、昼休みの終わり際に気付いた一通のメールが原因だった。
差出人は妻だった。機嫌よく遊んでいた幼い娘が、泣き出したという。
その程度でメールをするなと最初は思ったのだが、号泣しているというのだ。
状況が飲み込めず、無性に心配になった私は、急いで自宅に戻ってきた。玄関の扉を開けると、眉の垂れ下がった妻が待っていた。助けを求めているのがひと目で分かった。
「おかえりなさい」
「ただいま。いったいどうしたんだい?」
「それがね……」
おとうさん、と泣きながら奥の部屋から娘が抱きついてきた。
「おい、どうしたんだ?」
まだ靴も脱いでいない私が娘と目線を合わせても、何も言わない。
「私たちのビデオを見ていたのよ」
妻が見かねて、教えてくれた。
「ビデオ?」
「フィジーで撮った、私たちのほら……結婚式のビデオ! 最初は嬉しそうに観ていたのよ」
「フーン。それで?」
「それが突然、お父さんがどっかに行っちゃう──って、大泣きよ」
娘が目に涙を浮かべて話そうとするが、思い出してしまったのか、また泣き出してしまう。
「どうして泣くの?」
私のスラックスで涙を拭う娘。
「ねぇ、子供って親を選ぶって、聞いたことない?」
「何それ? 知らないよ。そうなの?」
「本当かどうかは分からないけど、高いお空から見下ろしていて、私たちが面白そうだったんだって。それでお父さんに会いに来たって」
「泣きながら、そんなこと言ってたの?」
面白い話である。もしそうなら……。顔を埋めている娘の頭を撫でながら、ふと、気付いたことがあった。
「因みに、僕の相手が君だって、気付いているの?」
妻の顔が引き吊った。もはや、口元が台形だ。
「お願い。今はまだ、言わないで」
スリッパの音を立てて慌ただしくキッチンに戻って行く妻。娘が自分で気付くまで、そう遠くはないだろう。
私は踵を潰さないように靴を脱ぎ、娘を抱き上げた。
「重!?」
言うまでもないが、娘は必死にしがみついている。