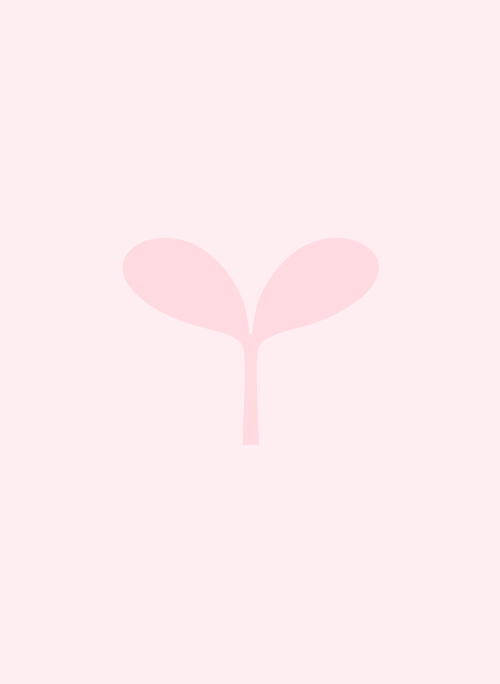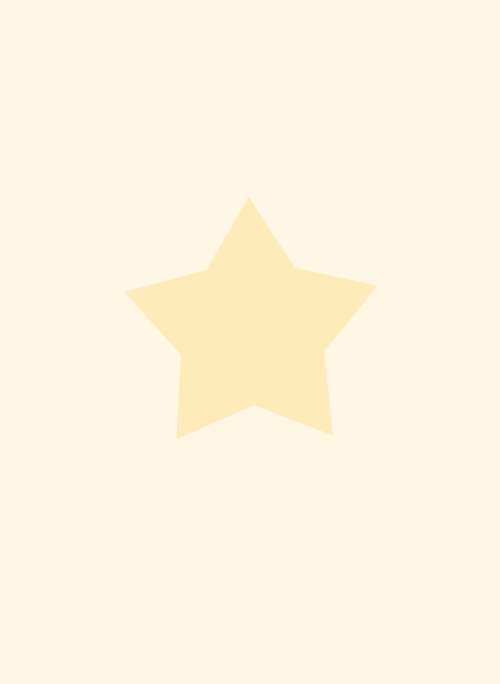ぽつ、ぽつ、ぽつ。
やっぱり降り出した。最近の天気予報はかなり当たる。
持っていた小豆色の傘を広げ、体がハミ出さないように気を付ける。
パラ、パラ、パラ。
雨音が変わる。
何だか楽しい。
由利は夫の秀夫を、駅まで向かいに行く途中である。
クルクル傘を回して、スキップ踏んで。
ルン、ルン、ルン。
鼻唄も口ずさむ。
ちゃぷ、ちゃぷ、ちゃぷ。
水溜まりも、お気に入りの向日葵のサンダルで、へっちゃら。
らん、らん、らん。
体も踊る、心も躍る。
あの人が待っている。
いつもの駅で。
いち、にの、さん。
大きな水溜まりも、ひとっ飛び。
ずんずん、ずんずん、どこまでも。
ずんずん、ずんずん、歩いて行く。
あの人のもとへ。
あの人の笑顔に。
この紺色の傘を、貴方に届けるため。
この雨の中を、二人で帰るために。
フン、フン、フン。
いっちに、いっちに。
行進だ。
みぎ、ひだり。
みぎ、ひだり。
見えてきた。
あの人のいる駅が、見えてきた。
みぎ、ひだり。
みぎ、ひだり。
らん、らん、らん。
全体、止まれ。
いっち、に。
到着。
「早かったね」
秀夫が優しく微笑む。
「だって、雨だもん。じっとしてられないよ」
由利は持って来た傘を手渡す。
「ありがとう」
バッサア。
秀夫は勢いよく傘を広げた。
大きな、大きな、紺色の傘だった。
「この傘も古くなったな」
秀夫の傘は、ツギハギだらけだった。
色々な当て布が模様になり、芸術的な雰囲気さえ、かもし出している。
「だってもう私たち、長いもん」
由利は顔をくしゃくしゃにして、しみじみと言った。
「この傘一本で、一緒に帰ろうか?」
秀夫は思い付いたように、白々しく言った。
「いいわよ」
くすりと白髪の由利が笑うと、同じく白髪の秀夫も、にこやかに笑った。
ちゃぷ、ちゃぷ、ちゃぷ。
二人いっしょに傘の中。
るん、るん、るん。
雨音聞いて、帰る道。
完
やっぱり降り出した。最近の天気予報はかなり当たる。
持っていた小豆色の傘を広げ、体がハミ出さないように気を付ける。
パラ、パラ、パラ。
雨音が変わる。
何だか楽しい。
由利は夫の秀夫を、駅まで向かいに行く途中である。
クルクル傘を回して、スキップ踏んで。
ルン、ルン、ルン。
鼻唄も口ずさむ。
ちゃぷ、ちゃぷ、ちゃぷ。
水溜まりも、お気に入りの向日葵のサンダルで、へっちゃら。
らん、らん、らん。
体も踊る、心も躍る。
あの人が待っている。
いつもの駅で。
いち、にの、さん。
大きな水溜まりも、ひとっ飛び。
ずんずん、ずんずん、どこまでも。
ずんずん、ずんずん、歩いて行く。
あの人のもとへ。
あの人の笑顔に。
この紺色の傘を、貴方に届けるため。
この雨の中を、二人で帰るために。
フン、フン、フン。
いっちに、いっちに。
行進だ。
みぎ、ひだり。
みぎ、ひだり。
見えてきた。
あの人のいる駅が、見えてきた。
みぎ、ひだり。
みぎ、ひだり。
らん、らん、らん。
全体、止まれ。
いっち、に。
到着。
「早かったね」
秀夫が優しく微笑む。
「だって、雨だもん。じっとしてられないよ」
由利は持って来た傘を手渡す。
「ありがとう」
バッサア。
秀夫は勢いよく傘を広げた。
大きな、大きな、紺色の傘だった。
「この傘も古くなったな」
秀夫の傘は、ツギハギだらけだった。
色々な当て布が模様になり、芸術的な雰囲気さえ、かもし出している。
「だってもう私たち、長いもん」
由利は顔をくしゃくしゃにして、しみじみと言った。
「この傘一本で、一緒に帰ろうか?」
秀夫は思い付いたように、白々しく言った。
「いいわよ」
くすりと白髪の由利が笑うと、同じく白髪の秀夫も、にこやかに笑った。
ちゃぷ、ちゃぷ、ちゃぷ。
二人いっしょに傘の中。
るん、るん、るん。
雨音聞いて、帰る道。
完