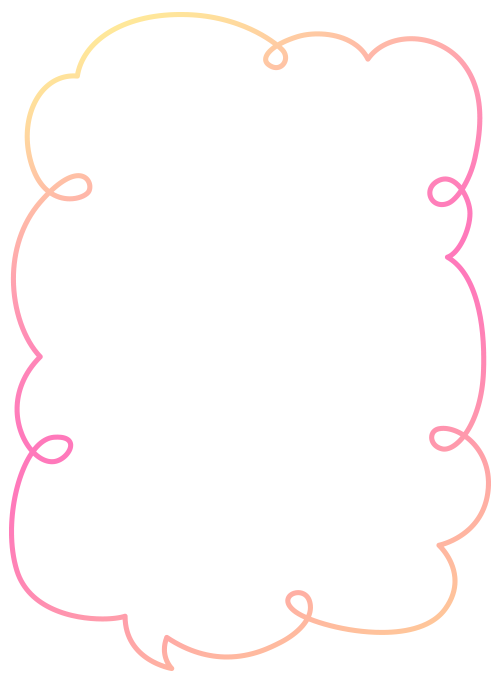ずっとずっと避け続けていたのに、こんなタイミングで会ってしまうなんて。
三浦君の顔を見た途端、今までの恐怖がフラッシュバックする。
爪の入った赤い封筒を送りつけてきたり、無言電話をかけてきたり、ショートメールやラインを送ってきたり。
そのストーカー行為のすべてを、あたしの目の前にいる彼がしていたとしたら……。
ううん、違う。彼がやっていたんだ。
そうだ。彼以外には考えられない。
「……――けて……。誰か……たすけて……」
叫ぶこともできないくらい驚き、恐怖を感じていた。
小声でそう口にするのが精いっぱいだ。
誰か。お願い……。
あたしを助けて……――!!!!
「お願い、助けて……!」
その言葉を聞くなり、三浦君は周りに視線を走らせた後、人差し指を口に当てた。
「しっ。静かにしろ。いいか、黙ってついてこい。叫んだらどうなるか分かってるな?」
「……はっ……はいっ……」
心臓がドクンと鳴る。
頭の中には警報を知らせるサイレンが鳴り響き、圧倒的な恐怖に目頭が熱くなる。
もうダメかもしれない。
もう彼からは逃れられない。
彼はずっとついてくる。あたしを追いかけてくる。
ガクガクと足を震わせるあたしの腕を掴んだまま、三浦君はあたしの体を普段使われていない教材室に押し込んだ。