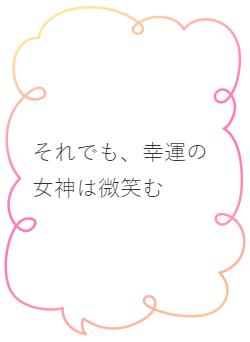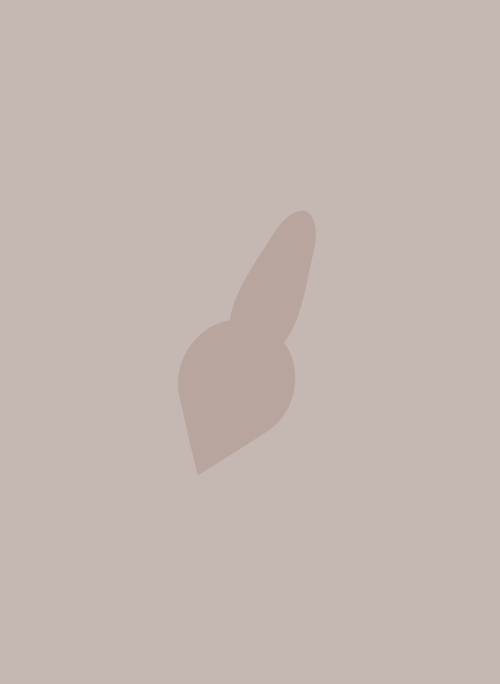しかし、流れ込んできた声は、栞さんのものではなかった。
《石原さん?私、佐藤だけど。》
「は?佐藤?え、なんでっ・・・」
なんでいきなり佐藤から電話?
なんで私の携帯番号知って・・・って、前もなんか電話してきてたな、コイツ。
なんで知ってんだ?
私のプライバシーは一体どうなっているんだ・・・。
そう不安になった私を見透かすように、佐藤はさらりと言った。
《前、言ってなかったけど、石原さんの番号はね。
私が勝手にロッカーの中に入ってた携帯を取り出して、知ったものよ。
石原さんのプライバシーはきっちり守られているから、安心して。》
あぁ・・・体育倉庫に閉じ込められた時のことかな。
つか、それ、守られてるって言えんのか?
「・・・・・・佐藤ってこえー・・・」
《そうよ、怖いのよ、私って。
石原さん、とっくに解ってるはずじゃない。
私が怖いこと。》
思わず漏れた呟きに対する、クールな答え。
私は首を傾げた。
「普通、自分が怖いって認めるか?」
《さあ?解らないわね。人それぞれじゃないの?》
「そ、っか・・・そうだよな。」
佐藤の言葉に、頷いた。
十人十色って、いうもんな。
《私は、認めるわ。自分が怖いって。
私自身が誰よりよく知ってるから。》
佐藤の声は、何かを噛み締めているようだった。
《・・・石原さん。あのね、私・・・ううん、私達。
あなたに、言いたいことがあるの。》
「言いたいこと?」
私はオウム返しに聞いた。
あまりに真剣な口調の佐藤に、気圧されそうだ。
《石原さん?私、佐藤だけど。》
「は?佐藤?え、なんでっ・・・」
なんでいきなり佐藤から電話?
なんで私の携帯番号知って・・・って、前もなんか電話してきてたな、コイツ。
なんで知ってんだ?
私のプライバシーは一体どうなっているんだ・・・。
そう不安になった私を見透かすように、佐藤はさらりと言った。
《前、言ってなかったけど、石原さんの番号はね。
私が勝手にロッカーの中に入ってた携帯を取り出して、知ったものよ。
石原さんのプライバシーはきっちり守られているから、安心して。》
あぁ・・・体育倉庫に閉じ込められた時のことかな。
つか、それ、守られてるって言えんのか?
「・・・・・・佐藤ってこえー・・・」
《そうよ、怖いのよ、私って。
石原さん、とっくに解ってるはずじゃない。
私が怖いこと。》
思わず漏れた呟きに対する、クールな答え。
私は首を傾げた。
「普通、自分が怖いって認めるか?」
《さあ?解らないわね。人それぞれじゃないの?》
「そ、っか・・・そうだよな。」
佐藤の言葉に、頷いた。
十人十色って、いうもんな。
《私は、認めるわ。自分が怖いって。
私自身が誰よりよく知ってるから。》
佐藤の声は、何かを噛み締めているようだった。
《・・・石原さん。あのね、私・・・ううん、私達。
あなたに、言いたいことがあるの。》
「言いたいこと?」
私はオウム返しに聞いた。
あまりに真剣な口調の佐藤に、気圧されそうだ。