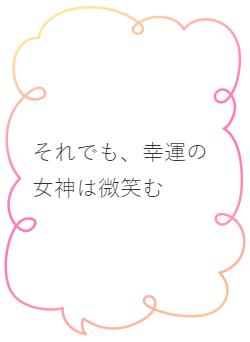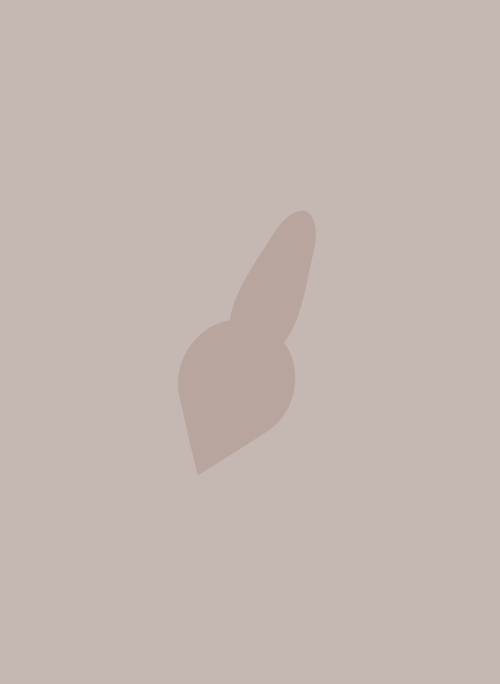石原は、俺の問いにキッパリと答えた。
「何もされてねぇよ。
私は、何かされるほど弱くないんでな。」
俺は、眉間にしわを寄せる。
「本当かよ?」
「本当だ。」
石原は迷いなくそう答える。
なら。
それなら、なぜ――
「じゃあ、なんで俺の顔見ないんだ?」
その問いを放った途端。
石原の体がビクッと反応した。
さっきまで、何もされてないとキッパリと答えていた石原が、黙った。
数秒の沈黙の後、石原は小さなかすれた声で、呟くように言った。
「・・・・・・ごめん。」
幼い子供のような言い方だった。
わりぃ、ではなく、ごめん。
「ごめん、私自身の問題。
今は――森井の顔、見れない。」
予想外のことに、思考がついていかない俺の横で。
石原はガタンと席を立った。
「本当に、ごめんっ・・・・・・。」
真っ直ぐに俺に向けられた瞳には。
涙が、今にも溢れ出そうなほどに、溜められていた。
石原はどこかへと、走り去って行った。
俺は、その場にへたりこんだ。
―――なんで、泣きそうな顔、してんだよ・・・・・・。
俺の顔を見る見ないよりなにより。
泣くな――・・・・・・。
そう、願った。
―千春side end―
「何もされてねぇよ。
私は、何かされるほど弱くないんでな。」
俺は、眉間にしわを寄せる。
「本当かよ?」
「本当だ。」
石原は迷いなくそう答える。
なら。
それなら、なぜ――
「じゃあ、なんで俺の顔見ないんだ?」
その問いを放った途端。
石原の体がビクッと反応した。
さっきまで、何もされてないとキッパリと答えていた石原が、黙った。
数秒の沈黙の後、石原は小さなかすれた声で、呟くように言った。
「・・・・・・ごめん。」
幼い子供のような言い方だった。
わりぃ、ではなく、ごめん。
「ごめん、私自身の問題。
今は――森井の顔、見れない。」
予想外のことに、思考がついていかない俺の横で。
石原はガタンと席を立った。
「本当に、ごめんっ・・・・・・。」
真っ直ぐに俺に向けられた瞳には。
涙が、今にも溢れ出そうなほどに、溜められていた。
石原はどこかへと、走り去って行った。
俺は、その場にへたりこんだ。
―――なんで、泣きそうな顔、してんだよ・・・・・・。
俺の顔を見る見ないよりなにより。
泣くな――・・・・・・。
そう、願った。
―千春side end―