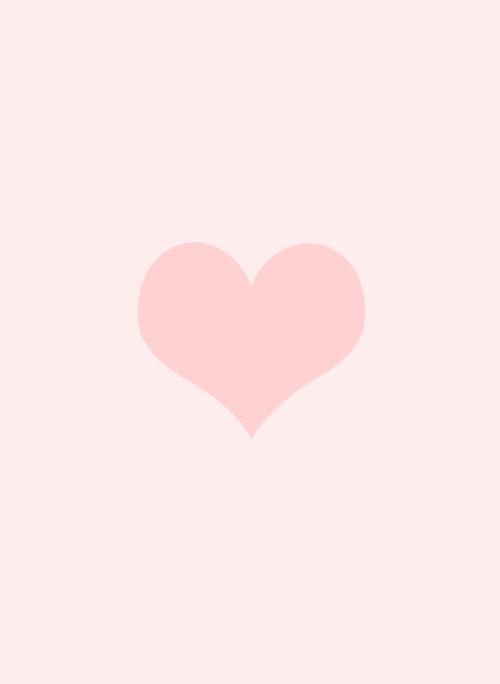嬉しそうに目を細めながら彼らに近付き始めた英明の足元に、コロコロと小さく音をたてながら、黄色いボールが転がって来た。
――あ。
しゃがんでボールを拾い上げると、それを追って三人の小さな女の子たちが駆けて来た。
「ボール~!」
一番大きな子の左手には、どことなくおぼつかない足取りの小さな女の子の手がしっかり握られ、そんな二人の前にはもう一人、女の子が走っている。
「君たちの?」
一番最初に到着した子に英明が優しく声をかけると、女の子はコクリとうなずいた。
「はい」
ボールを手渡していると、後ろからついて来ていた二人も到着する。
「お名前は?」
しゃがんで目線を彼女たちに合わせて英明が尋ねると、ボールを受け取った小さな女の子が、恥ずかしそうに笑い、小さく答えてきた。
「しんどうみづきちゃん」
「何歳?」
「四さい」
「わたしはしんどうゆづきだよ!」
"みづき"と名乗った女の子の後ろで、一番大きな女の子が元気よく答える。
「お! 元気だねぇ、何歳?」
「六さい!」
「わたしはお名前言えるかな?」
"ゆづき"と名乗った女の子としっかり手を繋いでいる女の子に英明が尋ねると、女の子は少し不安そうな顔で姉の手をしっかり握り、しかし、小さいがはっきりと、こう答えた。
「ちんどうかづゅきちゃんでしゅ」
「いくつ?」
「二ちゃい」
「二歳かぁ。ちゃんと言えて賢いなぁ」
三人の頭を順番に撫でながら英明は嬉しそうに目を細め、三人の顔を順番に見た。
「優月~! 美月~! 華月~!」
三人が戻らない事を心配した母親が、三人を探して辺りをキョロキョロしながら娘たちの名前を呼んでいる。と、側にいた父親が彼女の肩に軽く振れ、英明の方を指差した。
「……!」
ボディパーマのかかった茶色の髪を風に揺らし、ロシア人である亡き母より受け継いだ色素の薄い瞳で、彼女がしっかりと英明の姿を捕らえる。その隣には、かつてその瞳に暗い闇を宿して苦悩し、闇の中を彷徨っていた快が、しっかりとした明るい瞳で、微かに口元を緩めていた。