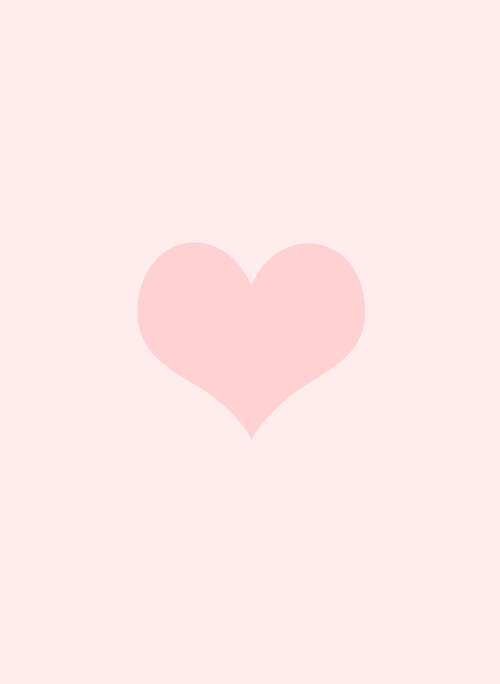――来年の夏には赤ちゃんが産まれる。今から一年も経たないうちに、あたしたちは"親"に……いや、実際にはもう"親"か。
瀬奈は閉じていた携帯電話をおもむろに開くと、ある場所へと電話をかけた。
「市立N総合病院精神科です」
数回の呼び出し音の後、受話器が上がり、女性の声が聞こえてくる。
「すみません、わたし、城ヶ崎と言います。石崎先生、いらっしゃいますか? そちらに通院している神堂快の事でお話が――」
要件を伝えて電話を切る。
――もう一つの不安は、石崎先生に直接訊いて確かめよう。
午後の業務の開始時間が迫ってくる。瀬奈は気分を切り換えるように軽く頭を振ると、ロッカールームを出た。
「ありがとうございました」
夕方、仕事帰りに総合病院を訪れた瀬奈は、石崎と話した後、丁寧に頭を下げ、病院を後にした。
――よかった。やっぱり昔の人の"無責任"な迷信だったんだ。
不安が一つ解消されたせいか、ここ数日ずっと暗かった瀬奈の表情は、久し振りに明るかった。
――後はあたし自身の問題か……。
インディゴブルーのジャケットの襟を直し、家へと歩き出す。と、突然、腹部に鈍く重い痛みを感じ、瀬奈は思わず立ち止まった。
何だろう……?
腹部が少し張っている感じがする。妊娠初期には軽い痛みを感じる事があると、産婦人科の医師に言われているが、今、感じている痛みはいつも感じているものより強い鈍痛だ。
――まさか……!
思わず腹部に手を当てた瀬奈の頭に"流産"の二文字が浮かんだ。
――嘘……!
デニムのポケットから携帯電話を取り出し、急いで産婦人科医院の番号をプッシュする。電話に出た受付の女性に慌てた口調で腹部の痛みを訴えた。
「出血してますか? 今すぐ来れますか?」
訴えを聞いた受付の女性が落ち着いた口調でゆっくり瀬奈に質問する。
「出血は確かめてないので判りませんが、すぐ行きます」
瀬奈は自分でも呼吸を整えながらそう答えると電話を切り、病院へと向かいながら、今度は快に電話した。
「もしもし快、今から病院来れる?」
「え……」
突然の瀬奈の言葉に、快から曇った返事が返ってくる。
「どうかしたのか……?」
「実はちょっとお腹が痛くて……。今、病院に連絡して向かってるとこ。もし無理なら一人でも大丈夫だから」