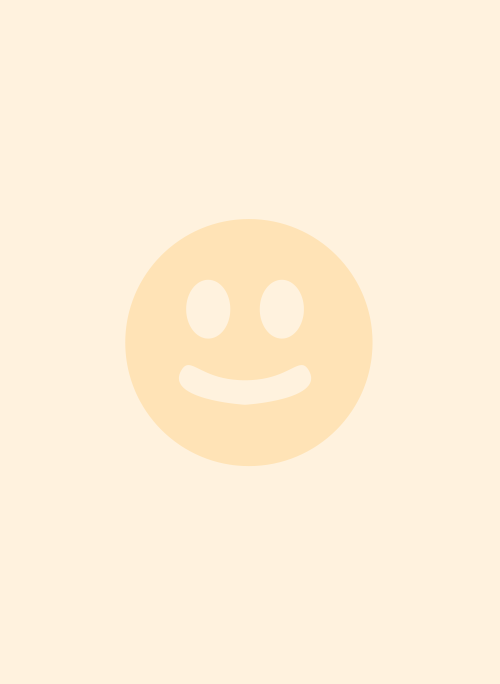向かい合って、ピノキオはもう一つの手も千沙と重ねるように持ち上げた。
「・・・温かいね。これが、体温なんだね、生きてる証拠」
ピノキオの言葉に彼女は頷く。そんなこと普段は考えないけれど、それは真実だった。私達は、生きている。だから血が通い、この手は温かい。
ふんわりと柔らかく瞳を細めて、サラサラした茶色の髪の下からピノキオが千沙を見詰めた。
「ちょこっとルールを破ろう。今そう決めたよ、僕」
「え?」
ピノキオは何を言っているんだろう。ルール?それはこの部屋のルールだろうか。ニコニコと笑ったままで、機嫌よさそうに彼は言った。
「最後のドアの向こうの世界はね、僕たちはただの通りすがりなんだ」
「え」
「通りすがり・・・・。いつも、普段の生活をしていて出会う人っているでしょう?散歩でよく見る人とか・・・よくいく店の店員だとか」
千沙は考えてから頷いた。顔見知り、程度というのだろうか。そういった関係の人は確かに沢山いる。言葉を交わしたことはないし、どこの誰かも知らない。だけど毎日すれ違うから、何か知っている人であるかのような気がするって人達。
最後のドアをちらりと見て、ピノキオは言った。
「通りすがり、なんだって。それは知ってる。今までにそれがなかったから、あそこがそうなんだ。この6つの世界はね、千沙と僕の平行世界だよ」