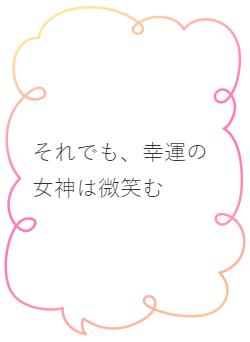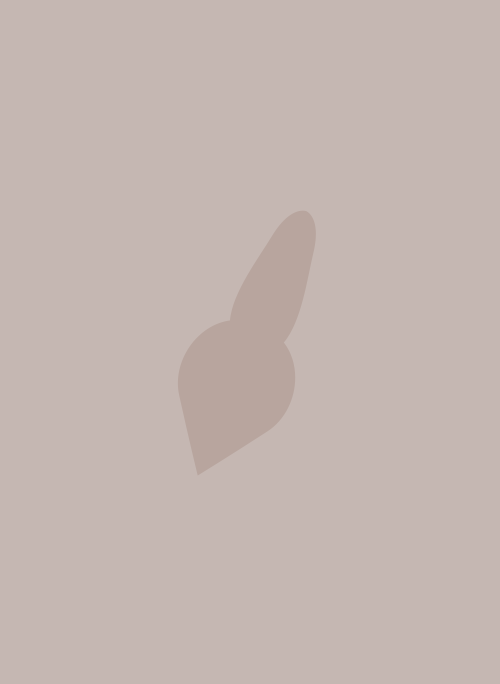嫌な予感・・・というより、嫌な推測が頭を過ぎる。
おそるおそる寝息の聞こえた方を見れば――
「あぁ・・・・・・やっぱり。」
げんなりと呟く。
案の定、お母さんが机に突っ伏して、安らかな寝息をたてていた。
「あれ?お母さん寝ちゃった?」
「はい、どうやらそうらしいです。
・・・お母さーん!
うわぁ、全然起きない。」
ゆさゆさと揺さぶるも、熟睡しているらしく、
まったくもって起きる気配がない。
「すみません、み・・・じゃない、千秋先輩。」
「いいよ、別に。
それより、羽依。」
「はい?」
「これからは、"先輩"も敬語も無しにできるといいね?」
「・・・・・・・/////」
「羽依、可愛いね?
良かった、可愛い羽依が俺のモノで。」
ニッコリと笑ったみ・・・じゃない、千秋先輩は、
少し名残惜しそうに、私の家から出た。
玄関まで送った私に――明日の朝、迎えに来るね、と甘く囁き、
不意打ちの、触れるだけの甘いキスをして。
真っ赤になったであろう私に、優しく笑いかけて。
―――帰っていった。
おそるおそる寝息の聞こえた方を見れば――
「あぁ・・・・・・やっぱり。」
げんなりと呟く。
案の定、お母さんが机に突っ伏して、安らかな寝息をたてていた。
「あれ?お母さん寝ちゃった?」
「はい、どうやらそうらしいです。
・・・お母さーん!
うわぁ、全然起きない。」
ゆさゆさと揺さぶるも、熟睡しているらしく、
まったくもって起きる気配がない。
「すみません、み・・・じゃない、千秋先輩。」
「いいよ、別に。
それより、羽依。」
「はい?」
「これからは、"先輩"も敬語も無しにできるといいね?」
「・・・・・・・/////」
「羽依、可愛いね?
良かった、可愛い羽依が俺のモノで。」
ニッコリと笑ったみ・・・じゃない、千秋先輩は、
少し名残惜しそうに、私の家から出た。
玄関まで送った私に――明日の朝、迎えに来るね、と甘く囁き、
不意打ちの、触れるだけの甘いキスをして。
真っ赤になったであろう私に、優しく笑いかけて。
―――帰っていった。