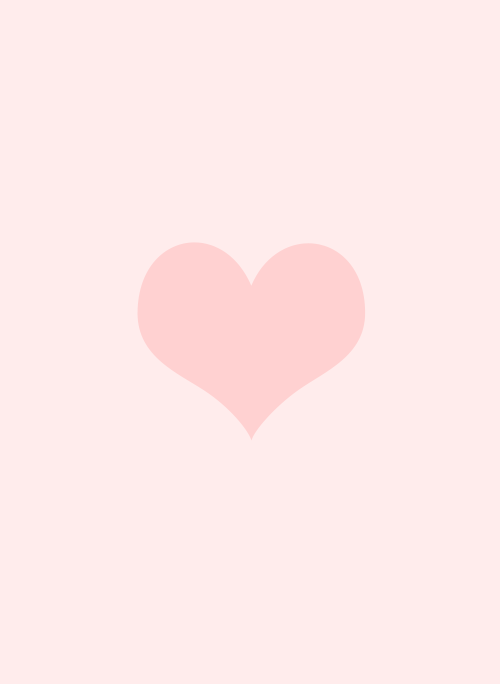(やっぱり、迎えを頼むべきだった)
声の大きさからすると、主はもうすぐ傍にいると考えていい。
後悔してもどうしようもない状況になってしまった。
「やっぱり、宮ノ沢くんじゃない。久しぶり」
声の主を見つけて、沈んでいた気持ちが更に沈んでいき、その音が頭で鳴り響いているかのうようだった。
「ちょっと、もしかして忘れたの?
上越、上越まくり(うわごしまくり)」
忘れるはずがない。
高校三年生の夏、僕は彼女に振られたのだ。
地元に帰ってきて一番会いたくない人物に、まさか一番に会ってしまうとは僕も相当ついていない。
「忘れるはずがないじゃん」
ため息をつきながら呟いた。
「どうして?」
まるであのことが無かったかのように、無邪気な笑顔でこちらを見ている。
彼女にとっては、ただの高校時代のクラスメートに会ったにすぎないのだろう。
「その変わった名前」
適当に違った理由を見つけ、その場から立ち去ろうとする。
足早で歩いたつもりだったが、それでも彼女は僕の後ろにぴったりとくっついて歩いてくる。
「やっぱり、名前か。
お父さんが競艇好きでその決まり手を娘の名前にするって、どう考えても可笑しいよね」
それ以上の言葉は僕の耳の中までは入ってきたものの脳まで届くことはなく、何も理解できず、何も覚えていなかった。
ただ、実家に着いて気付いたら携帯電話のアドレス帳には『上越まくり』一件が増えていた。
声の大きさからすると、主はもうすぐ傍にいると考えていい。
後悔してもどうしようもない状況になってしまった。
「やっぱり、宮ノ沢くんじゃない。久しぶり」
声の主を見つけて、沈んでいた気持ちが更に沈んでいき、その音が頭で鳴り響いているかのうようだった。
「ちょっと、もしかして忘れたの?
上越、上越まくり(うわごしまくり)」
忘れるはずがない。
高校三年生の夏、僕は彼女に振られたのだ。
地元に帰ってきて一番会いたくない人物に、まさか一番に会ってしまうとは僕も相当ついていない。
「忘れるはずがないじゃん」
ため息をつきながら呟いた。
「どうして?」
まるであのことが無かったかのように、無邪気な笑顔でこちらを見ている。
彼女にとっては、ただの高校時代のクラスメートに会ったにすぎないのだろう。
「その変わった名前」
適当に違った理由を見つけ、その場から立ち去ろうとする。
足早で歩いたつもりだったが、それでも彼女は僕の後ろにぴったりとくっついて歩いてくる。
「やっぱり、名前か。
お父さんが競艇好きでその決まり手を娘の名前にするって、どう考えても可笑しいよね」
それ以上の言葉は僕の耳の中までは入ってきたものの脳まで届くことはなく、何も理解できず、何も覚えていなかった。
ただ、実家に着いて気付いたら携帯電話のアドレス帳には『上越まくり』一件が増えていた。