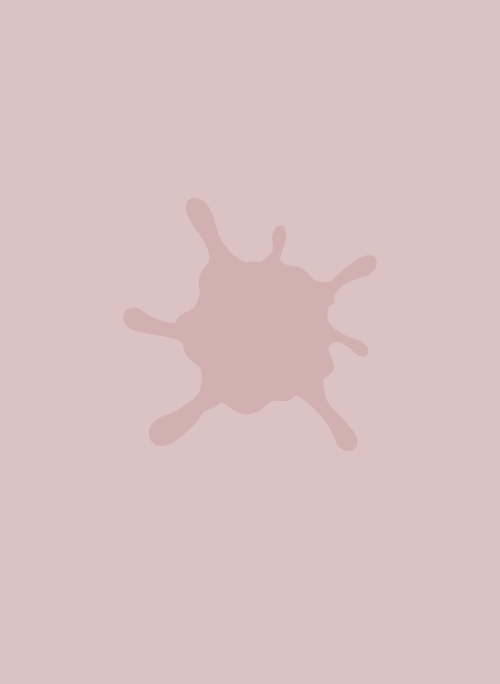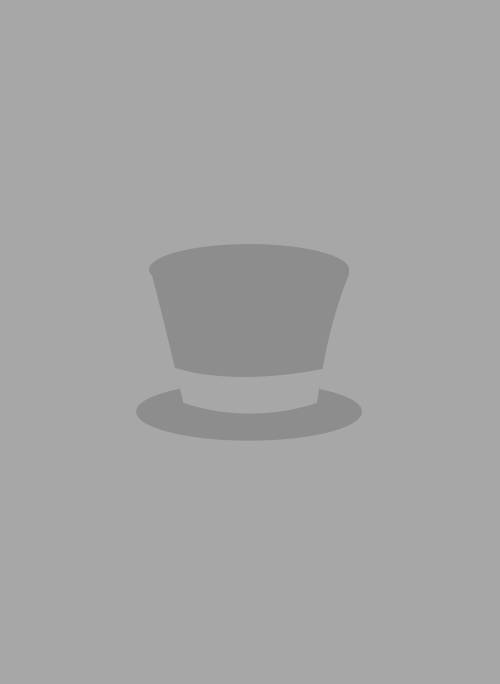すっきりと気負うことなく見返してくるこの瞳を、自分はずっと待ちわびていたのだ。
「誰ぞ、私に剣を」
体を起こしてそう言うと、教官が戸惑いつつも、ずしりと重みのある木剣を渡してきた。
「全力でかかれよ」
青礼が傍らに置いていた木剣を取って立ち上がった。
教官が少年たちを輪を作るように下がらせ、即席の試合場が出来る。
崔延は裾の長い上衣を脱ぎ、胴衣と袴の帯を一度締め直した。
半身を引き、踵を浮かせて体重を動かしやすい姿勢を取る。
青礼の方へ出ている側を庇えるよう剣先をやや寄らせ、だがいつでも翻せるように手首に力をこめる。
さすがに相手には隙がない。
じりじりと互いの隙を狙って打ち込もうとするために、右回りに回転が出来た。
相手の左身が奥へと消えた。
木剣から左手を離したのだ、と気づいたのは、大きく飛び退ってからだ。
右手の中で剣を滑らせ突き出すことで射るような速さを得た剣は、崔延の一撃に阻まれ下へと向けられる。
戻ってこようとする相手の左身に一瞬の空隙を見つけ、崔延も右手を離し左手だけで打ち込む。
さらに相手が剣先を返して胴に当ててくるより速く、剣の柄で顎を打とうと手首をひねった。
だが相手は顎を上げ、剣先を手元に引き戻してきた。
その素早い動きに、崔延は咄嗟に木剣を引いて喉を庇う。
容赦のない突きに肘が痺れたが、木剣をもろに突いてしまった衝撃は向こうにもきたはずだ。
くっと眉を寄せた相手の懐から退き、崔延は再び体をぶつけるつもりで打ちかかった。
ボクッ、とこもった音がした。
自分の白い木剣を受け止めた青礼の焦げ色の木剣が、ゆっくりと有り得ない所から曲がり落ちていく。
(折れた……!?)
「参りました」
気がつくと、足下で青礼が膝をついていた。
「さすがは殿下。お強くていらっしゃる――」
ほっとしたように喋り始めた教官の片手には、先ほどまで青礼が同輩に向けていた、白木の木剣が握られていた。