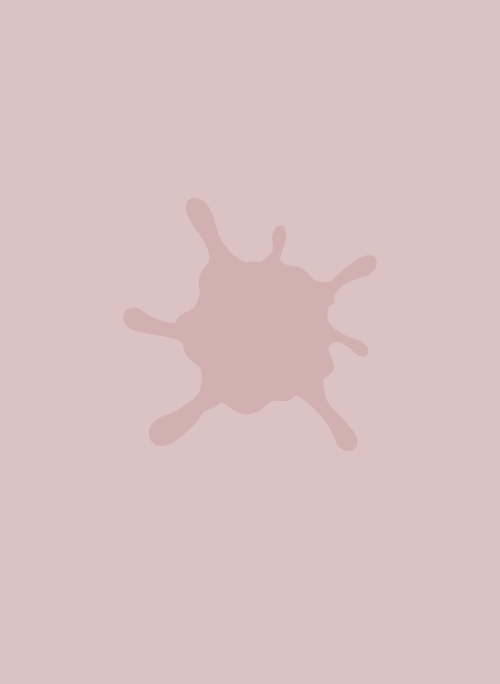アイスピックで氷を割ると、半分をアイスペールに入れ、残りを冷凍庫に入れた。
「やっぱロックだよね」
直樹がウイスキーを注ぐ。
「まぁこれが一番氷の美味さが分かるよな」
井上はグラスの中の氷を指で弾いた。
「あら聖人帰ってたの?」
母の綾乃がリビングに入って来た。
「ああ、たった今ね」
「そう。ご飯は?」
「ああ、食べてきた」
「あら、じゃあ井上くんこれ食べる?」
綾乃は聖人の為に作って置いてあった夕食のおかずを、井上に勧める。
「マジっすか。じゃあ遠慮なく頂きます」
井上はすでに夕食を済ませているだろうに、笑顔で手を上げた。
「じゃあちょっとお母さんも一緒に飲みましょうよ。せっかく聖人が南極の氷を貰ってきたんだから」
「南極の氷?」
「彼女の叔父さんが南極観測隊員らしいんですよ」
「ちょっと聖人! アナタ彼女がいたの?」
「あ、いや、まぁ……」
「何で言わないのよ。そんな大事なことを!」
母に問い詰められて、聖人は言葉に詰まる。
梓と付き合い始めて半年。決して隠していたわけではないのだが、何となく言いそびれていたのだ。
「まぁまぁ母さん。良いじゃないか、別にそのせいで成績が下がったわけでもないんだろうし」
直樹が助け舟を出す。
「そんなことを言ってるんじゃないわよ。私はもうずっと前から娘が欲しかったんだから、いるならいるでもっと家に連れて来なさいってことが言いたいのよ」
「え?」
三人は同時に唖然とした。
「いや、母さん。別に嫁ってわけじゃなく、まだただの彼女なんだし、だいたい高校生の頃の恋愛で、そのまま結婚まで至るかってのも、分からないだろ」
直樹が呆れ顔で言う。
「いや、兄ちゃん。それはないよ。梓はすげぇ家庭的なヤツでさぁ、確かにまだ高校生だけど、ずっと一緒にいたいって思ってるし」
「へぇ、梓ちゃんって言うのね。じゃあ明日連れて来なさい」
母は目を輝かせると、兄弟を無視してそう言った。
「やっぱロックだよね」
直樹がウイスキーを注ぐ。
「まぁこれが一番氷の美味さが分かるよな」
井上はグラスの中の氷を指で弾いた。
「あら聖人帰ってたの?」
母の綾乃がリビングに入って来た。
「ああ、たった今ね」
「そう。ご飯は?」
「ああ、食べてきた」
「あら、じゃあ井上くんこれ食べる?」
綾乃は聖人の為に作って置いてあった夕食のおかずを、井上に勧める。
「マジっすか。じゃあ遠慮なく頂きます」
井上はすでに夕食を済ませているだろうに、笑顔で手を上げた。
「じゃあちょっとお母さんも一緒に飲みましょうよ。せっかく聖人が南極の氷を貰ってきたんだから」
「南極の氷?」
「彼女の叔父さんが南極観測隊員らしいんですよ」
「ちょっと聖人! アナタ彼女がいたの?」
「あ、いや、まぁ……」
「何で言わないのよ。そんな大事なことを!」
母に問い詰められて、聖人は言葉に詰まる。
梓と付き合い始めて半年。決して隠していたわけではないのだが、何となく言いそびれていたのだ。
「まぁまぁ母さん。良いじゃないか、別にそのせいで成績が下がったわけでもないんだろうし」
直樹が助け舟を出す。
「そんなことを言ってるんじゃないわよ。私はもうずっと前から娘が欲しかったんだから、いるならいるでもっと家に連れて来なさいってことが言いたいのよ」
「え?」
三人は同時に唖然とした。
「いや、母さん。別に嫁ってわけじゃなく、まだただの彼女なんだし、だいたい高校生の頃の恋愛で、そのまま結婚まで至るかってのも、分からないだろ」
直樹が呆れ顔で言う。
「いや、兄ちゃん。それはないよ。梓はすげぇ家庭的なヤツでさぁ、確かにまだ高校生だけど、ずっと一緒にいたいって思ってるし」
「へぇ、梓ちゃんって言うのね。じゃあ明日連れて来なさい」
母は目を輝かせると、兄弟を無視してそう言った。