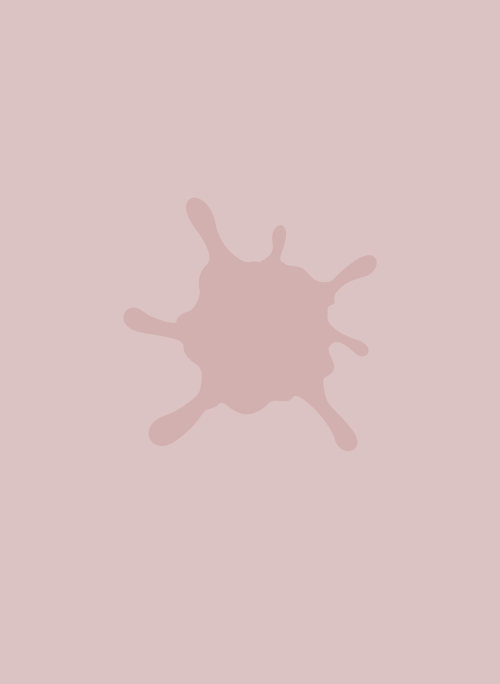「まさか血液を盗んで撃たれるとは思わなかったな。ところでいまさらおれのプロフィールは関係ないだろ?」
いま話すことか?と訝る目で振り向く。
「なぜ血を求める?」
質問に質問で返してきた執行官の額には横皺が刻まれていた。
「うまいからさ」
おれは端的に答えた。
「嘘を言うな」
「本当さ。鉄が錆びたようなあのニオイと喉越しがたまらない。それに小さい頃から赤い色が好きで、服も赤い色を好んで選んだ」
現実の世界で何度同じ答えを言っても、理解してもらったことはない。
「わからん」
執行官はヤレヤレと頭を振る。