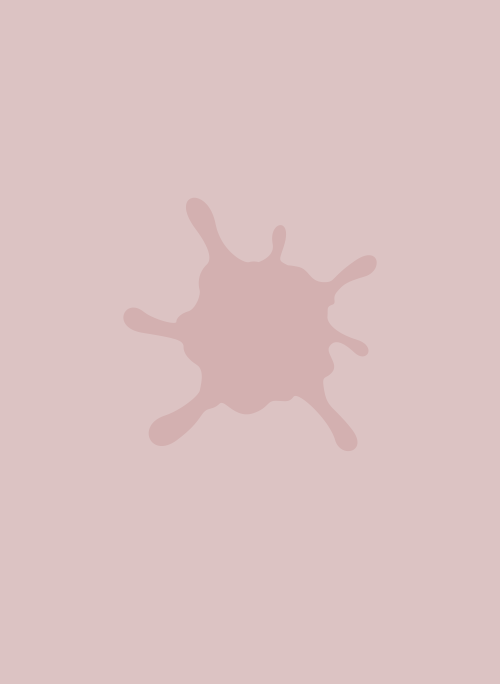「忘れません。あなたがこの世界に存在している限り、僕はあなたを忘れませんよ」
「じゃあ、私が死ねば忘れてくれる?」
「その発想はありませんでした」
うつ向いたまま尋ねてくる彼女の言葉に思わず感心。だけどそんな場合じゃないことは、百も承知だ。
「そうですね、多分、忘れないと思います。この家にあなたが来た時点で、あなたは印象深い人の位置付けですから」
「……なんか、複雑」
「そうですか? ああでも、やっぱり。同じですから、僕たちは」
「え?」
「ほら、僕とあなたで『野良猫』でしょう?おんなじ、猫繋がりです」
「……でも、野良犬とかあるじゃん」
「ええ、ですが、それでも誰がなんと言おうと僕は断言します。
『僕と野良さんは猫同盟です』と」
「なにそれ」
あ、今笑った。
それが何故か嬉しく感じる。