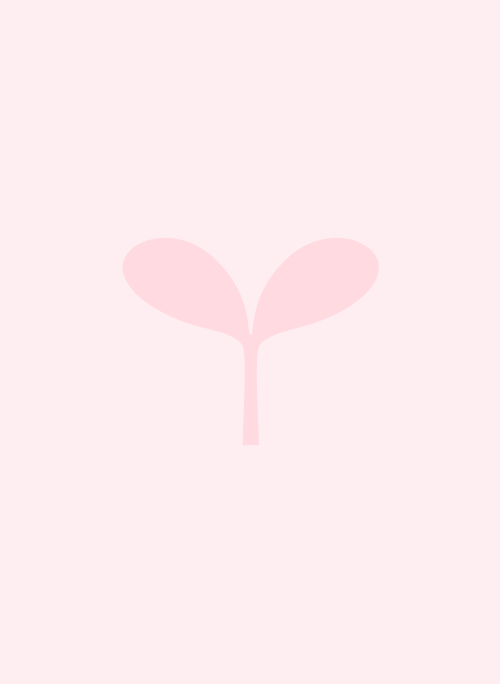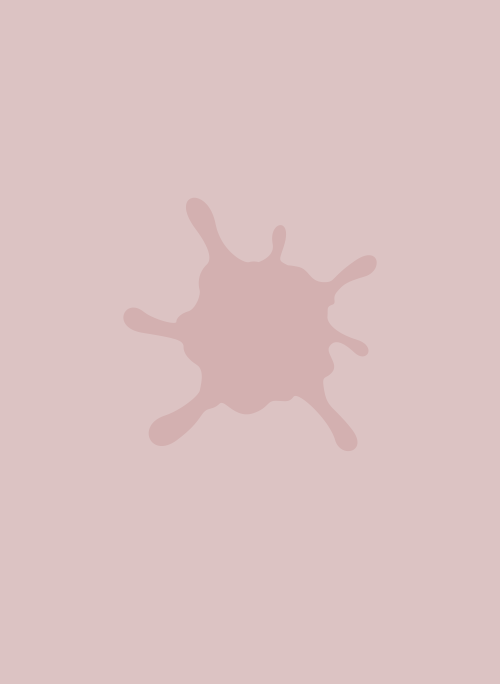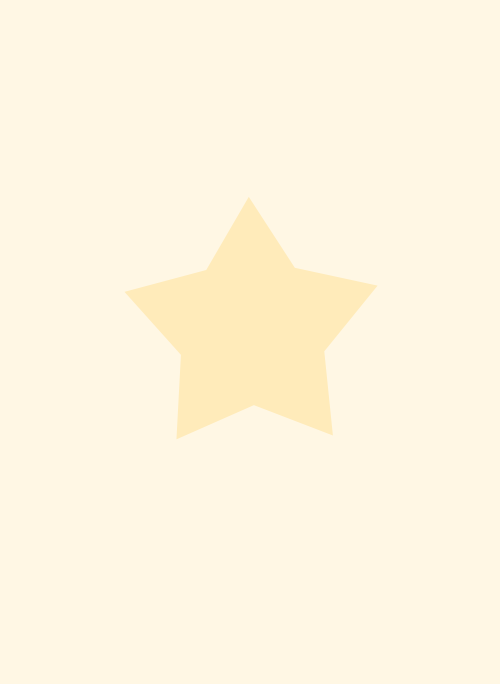──事件から一年半後。
ベッドの上で縛られ、炎に包まれた肉体が、本能を晒け出し、のたうちまわる。ギシギシと激しく軋み、橙色に燃え上がった炎は、部屋の天井をも焙った。
焦げた臭いが立ち込め、逃げ場を失った水分がぶくぶくと泡となる。溶け出した体液が熊手のように分岐した筋を作り、垂れ滴る。
「ううっ、うーう、うう……」
口に詰められたタオルが、肉体から叫び声を奪う。
これほどの火事だというのに、スプリンクラーはおろか、火災報知器すら反応しない。月明かりを頼りに忍び込んだ黒い影が、予め、それらが反応しないように、手を加えたのだ。
炎が上がったのは、人目がなく、森の奥に建てられた山荘を改造した、ある研究施設であった。
──それは、今からほんの数分前の出来事だった。
数年前から機会を伺っていた影は、ついにその傍らに立った。歯を食いしばると、ガタガタと全身が震える。
目の前のそれは、睡眠薬を服用し、眠っていた。
失った筈の手足が再生している。
影は必死にその体の震えを抑えると、鎖をベッドに巻き付けて縛る。
次にリュックサックから細い容器に入れたガソリンを取り出し、ぴゅうぴゅうとその上にまんべんなく掛ける。空になった容器を床に捨て、ポケットをまさぐった。
ベッドに縛り付けられたそれは、顔にガソリンが掛けられ、気管に入ったのか咳をして目を醒ました。
すかさず影は、驚いてバタバタと暴れるそれを抑え込み、タオルを口に押し込む。一度離れてライターの炎を見せると、逃げられないと悟ったのか、観念し、ゴクリと唾を飲み込んだ。
ベッドの上で縛られ、炎に包まれた肉体が、本能を晒け出し、のたうちまわる。ギシギシと激しく軋み、橙色に燃え上がった炎は、部屋の天井をも焙った。
焦げた臭いが立ち込め、逃げ場を失った水分がぶくぶくと泡となる。溶け出した体液が熊手のように分岐した筋を作り、垂れ滴る。
「ううっ、うーう、うう……」
口に詰められたタオルが、肉体から叫び声を奪う。
これほどの火事だというのに、スプリンクラーはおろか、火災報知器すら反応しない。月明かりを頼りに忍び込んだ黒い影が、予め、それらが反応しないように、手を加えたのだ。
炎が上がったのは、人目がなく、森の奥に建てられた山荘を改造した、ある研究施設であった。
──それは、今からほんの数分前の出来事だった。
数年前から機会を伺っていた影は、ついにその傍らに立った。歯を食いしばると、ガタガタと全身が震える。
目の前のそれは、睡眠薬を服用し、眠っていた。
失った筈の手足が再生している。
影は必死にその体の震えを抑えると、鎖をベッドに巻き付けて縛る。
次にリュックサックから細い容器に入れたガソリンを取り出し、ぴゅうぴゅうとその上にまんべんなく掛ける。空になった容器を床に捨て、ポケットをまさぐった。
ベッドに縛り付けられたそれは、顔にガソリンが掛けられ、気管に入ったのか咳をして目を醒ました。
すかさず影は、驚いてバタバタと暴れるそれを抑え込み、タオルを口に押し込む。一度離れてライターの炎を見せると、逃げられないと悟ったのか、観念し、ゴクリと唾を飲み込んだ。