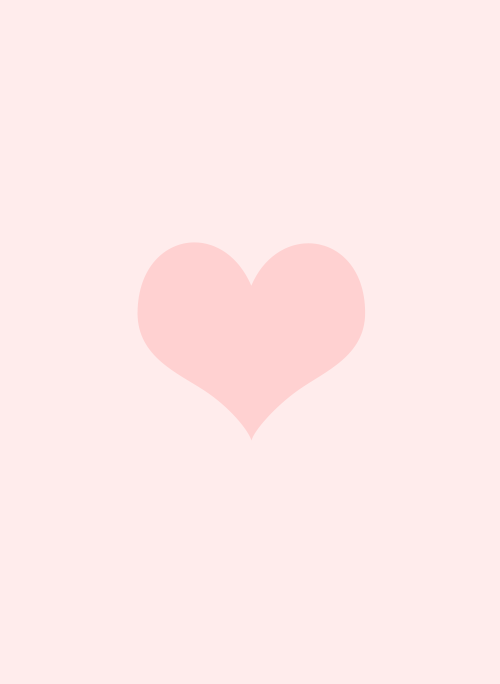“町で、北の外れにある洋菓子店よ”
母親の声が、耳に蘇ってきて、メイはまた少し涙が出た。
すぐ隣から聞こえるみたいに、鮮明に声を憶えているのに。
もう、ママには会うことも叶わないのだから。
メイは目元を拭って、一歩一歩、山を下りる。自分が生まれ育った村をおいてけぼりで。
まだ、心配そうに自分を見守り続けている親友、マーリンの視線を背中に感じながら。
村が全く見えないところまで進んでようやく、メイは後ろを振り返った。
「仕事を見つけないといけないもん」
半ば自分に言い聞かせるように、そう独り言をこぼせば、その切羽詰まった状況を思い出した。
メイのただ一人の肉親である母、ライザは、1週間前に亡くなった。
心臓が弱いライザが、冷え込んだ朝にベッドで冷たくなっていることに気がついたとき、メイは、自分の中の何かも一緒に死んでしまったように感じた。
でも、いつまでも、泣き暮らしているわけにはいかなかった。
元より貧しかったメイの家は、貯えなどない。つまり、すぐに自分自身で稼ぐ必要に迫られているのだ。
折しも18歳で、学校を卒業したところ。本格的な春を待つ暇もなく、メイは、わずかな手持ちで、町まで仕事を探しに行くのだ。
あてなど、全くなかった。
ずっと山で育ったメイには、町にも親戚はない。
それでも、自給自足に近い暮らしぶりの山で、少女が一人で暮らしていくことは困難であることは、メイにもよくわかっていた。
残る選択肢は、町に下り、住み込みで働ける場所を見つけることだった。
「洋菓子店、かぁ」
ぽつりと呟く声はやはり幼い。
ときどきママが、仕事のついでにマドレーヌを買ってきてくれたお店は、町の外れにあるらしい。
久し振りに、食べたい。
母の思い出が胸に迫り、メイは、仕事よりも先に、その店を探してみることにした。
「わあ!」
森が途切れると、はるか下ではあるけれど、町が見えた。
童話に出てくるような、可愛らしい家や店が立ち並び、たくさんの人の姿が見える。
活気に満ちた様子に見慣れた頃、自分がわずかに息切れしていることに気付いた。
こんな長く続く坂道を、弱った心臓を抱えたママは行き来してたんだ。
メイの胸がまたちくんと痛んだ。
「は…」
町の中へ踏み込むと、今度は圧倒された。
老いも若きも、男も女も、皆こざっぱりした小綺麗な服を着ている。
その上、往来は馬車や物売りで、賑やかなこときわまりない。
メイは、あっと言う間に、心が萎んでくるような気がして、慌てて目当ての洋菓子店を探した。
「いいにおい」
くん、と鼻を鳴らして、メイは立ち止まる。
そんなときにも、幼い頃から花の香りを好んだメイに、「匂いに敏感ね」と微笑むライザを思い出しながら。
甘い香りの出所と思われる洋菓子店にたどり着いたメイは、その洒落た外観と大きさに、ますます緊張する羽目になる。
ローランド洋菓子店?
看板の名前を目にして初めて、母親から洋菓子店の名前を聞いていなかったことに気がついた。忘れているだけだろうか。
そうなると、いっそう怖気づいて、しばらくの間、ドアの前でもじもじしていた。
…いや、でも、やっぱり、あのマドレーヌが食べたい。
その一念で、決意すると、行動も早いメイは、えいやっ、と店のドアを開けた。
「いらっしゃいませ!」
元気のいい声に、思わずメイは顔を上げた。
店頭に立っているのは、メイくらいの年頃の男の子で、彼はメイと目が合うとにこっと笑った。
少し肩の力が抜けたメイは、マドレーヌをひとつ買った。
店のテラス席で食べられるとの説明を受けて、メイは椅子に腰掛け、皿に載せてもらったマドレーヌを愛しい気持ちでしばらく眺めた。
ママと、庭で紅茶を飲みながら、よく食べたことを思い出す。
ママとの思い出の味を、一口パクリと口に含むなり、メイは見る間に表情を曇らせた。
「違う」
おいしくない、わけではない。いつものメイだったなら、喜んでパクパク食べるであろうおいしいマドレーヌだ。
でも、頭の中に明確に思い描いていた味と違っていたせいで、咀嚼する一口一口がだんだんぱさぱさと乾いて、喉を通りにくくなってくる。
「これじゃ、ない」
無意識のうちに独り言をこぼしていたメイの声を拾って、隣のテーブルの片付けに来ていた少年が、首をかしげた。先ほどは店頭に立っていた少年だ。
「どうかしました?」
そう声を掛けられて初めて、メイは心の内で思ったことが口から洩れていたことに気がついた。
「いえ、ああ、あの」
恥ずかしくて顔を赤くしたものの、メイはふと思いついて訊ねた。
「あの、失礼なことを聞きますけど、この町には、お菓子屋さんはここ1軒だけでしょうか」
同業者のことを訊ねるのは、気が引けるけれど、一番情報を持っている気がして。
「ああ…、いいえ」
そう答えた少年が、ゆっくりと笑みを消して、じいっとメイを見つめた。
「もう1軒、北の外れにありますよ。ただ、お勧めはしませんが」
彼の声も幾分低くなった気がして、メイはこくんと喉を鳴らした。
どうやら、ママが気に入っていたお店は、ひと癖あるらしいと本能的に悟りながら。
ひょっとしたら、幽霊が住んでるのかもしれない。
メイは、さっきのローランド洋菓子店とは違う理由で、その洋菓子店の前で立ち止まり、生唾を飲み込んだ。
なぜなら、その店が纏う雰囲気は暗く、看板はおろか、照明一つない。人の気配すらないのだ。
町の中心からずいぶん離れたことは確かだけれど、ここはまた極端に人通りが少ない。おそらく町の最北端なのだろう。さらに北側には、もう木々が立ち並んでいるだけだから。
お店と言うよりも、廃屋だな。
メイはそう思うけれど、ローランド洋菓子店の少年が、「この道をこの方向にまっすぐ進んで最後に見えた建物」と言ったその通りの場所に、今立っていることは間違いないのだ。
えーい、マドレーヌのためだ!
勇気を奮い立たせて、メイはそのドアを勢いよく開いた。
「こんにちは」
はっきりと声を出したつもりはあったけれど、静かすぎる店舗には不自然なくらいに大きく響いて、メイははっと息を止めた。
「びっくりしたわぁ」
やはり、一応は洋菓子店らしく、薄暗い店内のショーケースの上から、ふくよかなおばさんが顔をのぞかせた。
「北の外れの洋菓子屋さんって、こちらでしょうか」
メイがドキドキしながらそう尋ねると、おばさんが少し首をかしげながら答えた。
「そうだけどね、珍しいわ、お客さんなんて」
「はあ?」
今度はメイが首をかしげ、ふと暗いショーケースの中に目を走らせた途端、唖然とすることになる。
「マドレーヌ、ないんですか!?」
メイは、半ば呆然としながらも、売り子のおばさんに尋ねた。
ショーケースの中には、どう見ても、地味な色合いのチョコレート菓子が何品か入れられているだけだ。しかもそれは、陳列と言う言葉よりもむしろ、放置という言葉がぴったりなくらいの、無造作な置かれ方で。
「え、ええ」
メイの勢いに気圧されたように、おばさんは目をぱちくりさせた。
「いつもは、何時くらいに焼き上がりますか?」
「いつもって…、ここしばらくは…。いいわ、ちょっと待ってて」
言い淀んでいたおばさんは、決意したかのように、店の奥に姿を消した。
もう売り切れてしまったんだろうか。
不安になって、店内をうろうろしていると、奥から聞こえる話し声のうち、片方が次第に大きくなってくることに気が付いた。
店頭に立っていたおばさんの声だ。もう一方はぼそぼそと小さくて聞き取れない。
「全く話にならないわ!今日という今日は頭にきた!辞めさせてもらいます!!」
顔を真っ赤にしたおばさんが奥のドアをと蹴破らんばかりの勢いで戻って来たと思ったら、ショーケースに乱暴に何かの紙切れを叩きつけて、出入口のドアから出て行った。
ぽかんと口を開けていたメイは、数分後、鼻息荒く戻って来たおばさんからこう告げられる。
「こんなダメ職人、マドレーヌなんて焼けやしないから、諦めな!!」
再びパタンと閉じられた出入口を、メイはどのくらいの間眺めていただろうか。ドアの木目にある小さな節を、無意識のうちに16、17…、と数えていたところだった。
「あ?」
低い声が鼓膜を震わせたように感じて、メイは微かに身震いしながらゆっくりと振り返った。
「ひっ。で、で、出たぁ…!」
好き勝手に伸びたグレーの髪の間から、きらりと二つの瞳が瞬いているのを、視覚で確認した瞬間、メイは腰を抜かしてしまった。
あわあわ言っているうちに、その化け物は、ゆらりとショーケースの脇を通り抜けて、メイを上から見下ろした。
「幽霊じゃねーよ」
ぺちっと額を叩かれて、ようやくメイは正気に返った。
「『客』?」
「は、ぁ」
さっきのおばさんと言い、この幽霊風の人物と言い、なぜ客にいちいち驚くのかわからない。
「あー、マドレーヌ?」
「んえ」
「しゃべれてねーぞ」
くすりと甘く微笑みをこぼしたのを見て、初めてメイは、それが端正な顔立ちの男の人だということにようやく気がついた。
かあっと頭の中が沸いたような気がして、火照った頬のままで、メイはその人に叫んだ。
「私にマドレーヌを売ってください!!」
すると、彼はなぜか、こめかみを押さえてがっくりと頭を垂れる。
「あ、あ、れ?どうしたんですか?まさか、心臓が弱いとか!?」
慌てて顔を覗き込もうと彼の下に潜り込んだ。
「ぷっ」
おろおろするメイに噴き出しながらも、彼はまだこめかみをぐりぐりと圧迫しつつ、こう言うのだった。
「二日酔い」
「はああ!?」
「だーかーら、その声、二日酔いの頭にガンガン響く。帰れ」
「はああああ!?」
メイは、久しぶりに心の底から怒りが沸いてくるのを感じた。
何、その態度。仕事に対する姿勢。村からの長い道のりで、母が仕事のためにそこを往復した日々を思って、胸を痛めた直後だったこともあるだろう。メイは、自分の気持ちを抑えることができなかった。
へらへら笑っている男の襟首を掴んだ。
「真面目に働け!仕事中に飲酒だなんて、言語道断!!」
「へー、へー」
言われ慣れた様子で、相変わらずのらりくらりとかわす男に、メイは一層こみ上げる怒りを必死で抑えているのだけれど。
「そりゃお客さんも来ないよ!!」
「へへっ」
「褒めてないっつーの!」
「ほう」
ああ、こいつとしゃべってるだけ、時間が無駄だ。これだけ気持ちを込めて訴えかけてるのに、一度も視線が交わらないことに、メイは気づいた。
「とにかく、マドレーヌ1個だけでいいから焼いてよ!!」
「んあ?」
間抜けな返答の男の声のせいか、自分の声がやけに悲痛な響きを持っているように聞こえたメイは、一瞬喉を詰まらせた。
「…それ買ったら、帰るから」
「んー」
それでもほとんど反応のない男に、メイは強硬手段に出た。
「マドレーヌ売ってくれるまで帰らないからねえぇぇ!!」
「ぐえっ」
耳元で叫んでやれば、ようやく男は、いくらか感情を浮かべた瞳で、恨めしげにメイを睨んだ。
「ふん。いい顔できるじゃん」
全然怖くないけどね、と言い募るメイの視線が、先ほど店を飛び出したおばさんの叩きつけた紙切れに止まる。
「“売り子募集”、……“住み込み可”!?」
断る、と暗い声で呟く男を押しのけて、メイは意気揚々と奥のドアを開けたのだった。
「あれ、君、ついてきちゃったの?」
メイは、勝手に上がりこんだ店の2階で、荷物を下ろしたとき、その中からぴょんと飛び出した小人に驚いた。
「てっきり、村に住んでいる守り人か何かかと思ってた。ママの守り人だったのかなぁ。ママの代わりにあたしにくっついてくれたのかなぁ」
メイが手のひらを差し出すと、小人はそこに上って、座った。ぱくぱくと口を動かして、その後ぷくりと頬を膨らませる。
「ん?ここは居心地が悪いの?」
可愛い男児の姿の小人は、ふくれっ面をするといっそう愛らしくて、メイは気持ちが和らいでいくのを感じた。
うん、と言うように大きく頷いて見せるから、メイはくすくす笑う。彼の声は、メイの耳にだって、全く聞こえないのだけれど、表情や仕草で、なんとなく意思は伝わるのだ。
「でも、どうしても、マドレーヌを食べたいんだもん」
子供じみた声だと思う、自分でも。
メイは、ここまでこだわる理由は、自分でもよくわからないけれど、諦めることができなかった。
「食べたら、出て行くってば」
相変わらずぷりぷり怒っている様子の小人に、メイはそう囁いた。
慣れないことばかりで、疲れていたのだろう。
勝手に上がりこんだ廃屋のような建物の2階、カビ臭いベッドに横になったら、すぐにメイの意識は飛んだ。
はっ、と目が覚めたときには、窓の外が微かに明るくなってきていた。
…トイレ。
2階にそれらしいところがなかったので、1階に下りてみると、甘い香りが次第に強くなり、メイはドキドキした。
昨日強引に通り抜けた、店の奥のスペースは、厨房だ。あの時は死んだように静まり返っていたその場所が、今は温かな灯りのもとで、息を吹き返している。
「何作ってるの?」
好奇心に負けて、思わずそう話しかけると、驚きもしないで肩越しにちらりと振り返った男は、「雇ってねーぞ」と余計な一言。
ムッとしたメイはドアのところから遠慮がちに覗くのをやめて、その手元が見えるところまで進んだ。
「また、チョコレートか」
1センチ角ほどのサイズのチョコレートが、トレイに無造作に転がっている。
バターの香りがした気がするのにな、と思いながら、メイは残念そうにトレイを見下ろしている。
「ただのチョコじゃねーぞ」
「…酒臭いチョコ?」
二日酔いだと言っていたにもかかわらず、瓶から直接アルコールを摂取している男に呆れて、メイがそう言うと、「ぶっ」と男が噴き出した。
「失礼だけど、正解でもあるな。特別に1個食わしてやる」
「あれ?昨日よりはまともにしゃべれるね」
「迎え酒すると頭痛が消えるからな。酒は神様だ♪」
「……」
呆れて言葉が出ないメイの口に、男がその四角いチョコレートを一つ、押し込んできた。
「ん、ん!?」
独特の刺激に、メイは涙目になっている。
チョコの表面が溶けた瞬間、中から液体がとろりと滲み、メイの舌を痺れさせ、喉を焼き、鼻を痛めた。
「あ、あた、あたし、未成年だってば!」
お酒のにおいがするだけかと思っていたのに、しっかり液体そのものを包みこんでいたからびっくりしているメイ。
「へー」
「っ。もうっ」
再度抗議を試みようとしたメイは、胸をひたひたと鎮めていた悲しみの冷たさが、引いていることにふと気付いた。
「……あれ?」
ママを失った、寂しさ。
それが、消えたわけじゃないけれど、溺れそうなほどじゃない気がする。
「リキュール入りのチョコレート。辛い現実を、忘れさせてくれる」
その低い声の意味を認識したら、メイの瞳はうっすらと水の膜を張ったけれど、それが雫となって零れおちることはない。
「なんか、変」
母親の声が、耳に蘇ってきて、メイはまた少し涙が出た。
すぐ隣から聞こえるみたいに、鮮明に声を憶えているのに。
もう、ママには会うことも叶わないのだから。
メイは目元を拭って、一歩一歩、山を下りる。自分が生まれ育った村をおいてけぼりで。
まだ、心配そうに自分を見守り続けている親友、マーリンの視線を背中に感じながら。
村が全く見えないところまで進んでようやく、メイは後ろを振り返った。
「仕事を見つけないといけないもん」
半ば自分に言い聞かせるように、そう独り言をこぼせば、その切羽詰まった状況を思い出した。
メイのただ一人の肉親である母、ライザは、1週間前に亡くなった。
心臓が弱いライザが、冷え込んだ朝にベッドで冷たくなっていることに気がついたとき、メイは、自分の中の何かも一緒に死んでしまったように感じた。
でも、いつまでも、泣き暮らしているわけにはいかなかった。
元より貧しかったメイの家は、貯えなどない。つまり、すぐに自分自身で稼ぐ必要に迫られているのだ。
折しも18歳で、学校を卒業したところ。本格的な春を待つ暇もなく、メイは、わずかな手持ちで、町まで仕事を探しに行くのだ。
あてなど、全くなかった。
ずっと山で育ったメイには、町にも親戚はない。
それでも、自給自足に近い暮らしぶりの山で、少女が一人で暮らしていくことは困難であることは、メイにもよくわかっていた。
残る選択肢は、町に下り、住み込みで働ける場所を見つけることだった。
「洋菓子店、かぁ」
ぽつりと呟く声はやはり幼い。
ときどきママが、仕事のついでにマドレーヌを買ってきてくれたお店は、町の外れにあるらしい。
久し振りに、食べたい。
母の思い出が胸に迫り、メイは、仕事よりも先に、その店を探してみることにした。
「わあ!」
森が途切れると、はるか下ではあるけれど、町が見えた。
童話に出てくるような、可愛らしい家や店が立ち並び、たくさんの人の姿が見える。
活気に満ちた様子に見慣れた頃、自分がわずかに息切れしていることに気付いた。
こんな長く続く坂道を、弱った心臓を抱えたママは行き来してたんだ。
メイの胸がまたちくんと痛んだ。
「は…」
町の中へ踏み込むと、今度は圧倒された。
老いも若きも、男も女も、皆こざっぱりした小綺麗な服を着ている。
その上、往来は馬車や物売りで、賑やかなこときわまりない。
メイは、あっと言う間に、心が萎んでくるような気がして、慌てて目当ての洋菓子店を探した。
「いいにおい」
くん、と鼻を鳴らして、メイは立ち止まる。
そんなときにも、幼い頃から花の香りを好んだメイに、「匂いに敏感ね」と微笑むライザを思い出しながら。
甘い香りの出所と思われる洋菓子店にたどり着いたメイは、その洒落た外観と大きさに、ますます緊張する羽目になる。
ローランド洋菓子店?
看板の名前を目にして初めて、母親から洋菓子店の名前を聞いていなかったことに気がついた。忘れているだけだろうか。
そうなると、いっそう怖気づいて、しばらくの間、ドアの前でもじもじしていた。
…いや、でも、やっぱり、あのマドレーヌが食べたい。
その一念で、決意すると、行動も早いメイは、えいやっ、と店のドアを開けた。
「いらっしゃいませ!」
元気のいい声に、思わずメイは顔を上げた。
店頭に立っているのは、メイくらいの年頃の男の子で、彼はメイと目が合うとにこっと笑った。
少し肩の力が抜けたメイは、マドレーヌをひとつ買った。
店のテラス席で食べられるとの説明を受けて、メイは椅子に腰掛け、皿に載せてもらったマドレーヌを愛しい気持ちでしばらく眺めた。
ママと、庭で紅茶を飲みながら、よく食べたことを思い出す。
ママとの思い出の味を、一口パクリと口に含むなり、メイは見る間に表情を曇らせた。
「違う」
おいしくない、わけではない。いつものメイだったなら、喜んでパクパク食べるであろうおいしいマドレーヌだ。
でも、頭の中に明確に思い描いていた味と違っていたせいで、咀嚼する一口一口がだんだんぱさぱさと乾いて、喉を通りにくくなってくる。
「これじゃ、ない」
無意識のうちに独り言をこぼしていたメイの声を拾って、隣のテーブルの片付けに来ていた少年が、首をかしげた。先ほどは店頭に立っていた少年だ。
「どうかしました?」
そう声を掛けられて初めて、メイは心の内で思ったことが口から洩れていたことに気がついた。
「いえ、ああ、あの」
恥ずかしくて顔を赤くしたものの、メイはふと思いついて訊ねた。
「あの、失礼なことを聞きますけど、この町には、お菓子屋さんはここ1軒だけでしょうか」
同業者のことを訊ねるのは、気が引けるけれど、一番情報を持っている気がして。
「ああ…、いいえ」
そう答えた少年が、ゆっくりと笑みを消して、じいっとメイを見つめた。
「もう1軒、北の外れにありますよ。ただ、お勧めはしませんが」
彼の声も幾分低くなった気がして、メイはこくんと喉を鳴らした。
どうやら、ママが気に入っていたお店は、ひと癖あるらしいと本能的に悟りながら。
ひょっとしたら、幽霊が住んでるのかもしれない。
メイは、さっきのローランド洋菓子店とは違う理由で、その洋菓子店の前で立ち止まり、生唾を飲み込んだ。
なぜなら、その店が纏う雰囲気は暗く、看板はおろか、照明一つない。人の気配すらないのだ。
町の中心からずいぶん離れたことは確かだけれど、ここはまた極端に人通りが少ない。おそらく町の最北端なのだろう。さらに北側には、もう木々が立ち並んでいるだけだから。
お店と言うよりも、廃屋だな。
メイはそう思うけれど、ローランド洋菓子店の少年が、「この道をこの方向にまっすぐ進んで最後に見えた建物」と言ったその通りの場所に、今立っていることは間違いないのだ。
えーい、マドレーヌのためだ!
勇気を奮い立たせて、メイはそのドアを勢いよく開いた。
「こんにちは」
はっきりと声を出したつもりはあったけれど、静かすぎる店舗には不自然なくらいに大きく響いて、メイははっと息を止めた。
「びっくりしたわぁ」
やはり、一応は洋菓子店らしく、薄暗い店内のショーケースの上から、ふくよかなおばさんが顔をのぞかせた。
「北の外れの洋菓子屋さんって、こちらでしょうか」
メイがドキドキしながらそう尋ねると、おばさんが少し首をかしげながら答えた。
「そうだけどね、珍しいわ、お客さんなんて」
「はあ?」
今度はメイが首をかしげ、ふと暗いショーケースの中に目を走らせた途端、唖然とすることになる。
「マドレーヌ、ないんですか!?」
メイは、半ば呆然としながらも、売り子のおばさんに尋ねた。
ショーケースの中には、どう見ても、地味な色合いのチョコレート菓子が何品か入れられているだけだ。しかもそれは、陳列と言う言葉よりもむしろ、放置という言葉がぴったりなくらいの、無造作な置かれ方で。
「え、ええ」
メイの勢いに気圧されたように、おばさんは目をぱちくりさせた。
「いつもは、何時くらいに焼き上がりますか?」
「いつもって…、ここしばらくは…。いいわ、ちょっと待ってて」
言い淀んでいたおばさんは、決意したかのように、店の奥に姿を消した。
もう売り切れてしまったんだろうか。
不安になって、店内をうろうろしていると、奥から聞こえる話し声のうち、片方が次第に大きくなってくることに気が付いた。
店頭に立っていたおばさんの声だ。もう一方はぼそぼそと小さくて聞き取れない。
「全く話にならないわ!今日という今日は頭にきた!辞めさせてもらいます!!」
顔を真っ赤にしたおばさんが奥のドアをと蹴破らんばかりの勢いで戻って来たと思ったら、ショーケースに乱暴に何かの紙切れを叩きつけて、出入口のドアから出て行った。
ぽかんと口を開けていたメイは、数分後、鼻息荒く戻って来たおばさんからこう告げられる。
「こんなダメ職人、マドレーヌなんて焼けやしないから、諦めな!!」
再びパタンと閉じられた出入口を、メイはどのくらいの間眺めていただろうか。ドアの木目にある小さな節を、無意識のうちに16、17…、と数えていたところだった。
「あ?」
低い声が鼓膜を震わせたように感じて、メイは微かに身震いしながらゆっくりと振り返った。
「ひっ。で、で、出たぁ…!」
好き勝手に伸びたグレーの髪の間から、きらりと二つの瞳が瞬いているのを、視覚で確認した瞬間、メイは腰を抜かしてしまった。
あわあわ言っているうちに、その化け物は、ゆらりとショーケースの脇を通り抜けて、メイを上から見下ろした。
「幽霊じゃねーよ」
ぺちっと額を叩かれて、ようやくメイは正気に返った。
「『客』?」
「は、ぁ」
さっきのおばさんと言い、この幽霊風の人物と言い、なぜ客にいちいち驚くのかわからない。
「あー、マドレーヌ?」
「んえ」
「しゃべれてねーぞ」
くすりと甘く微笑みをこぼしたのを見て、初めてメイは、それが端正な顔立ちの男の人だということにようやく気がついた。
かあっと頭の中が沸いたような気がして、火照った頬のままで、メイはその人に叫んだ。
「私にマドレーヌを売ってください!!」
すると、彼はなぜか、こめかみを押さえてがっくりと頭を垂れる。
「あ、あ、れ?どうしたんですか?まさか、心臓が弱いとか!?」
慌てて顔を覗き込もうと彼の下に潜り込んだ。
「ぷっ」
おろおろするメイに噴き出しながらも、彼はまだこめかみをぐりぐりと圧迫しつつ、こう言うのだった。
「二日酔い」
「はああ!?」
「だーかーら、その声、二日酔いの頭にガンガン響く。帰れ」
「はああああ!?」
メイは、久しぶりに心の底から怒りが沸いてくるのを感じた。
何、その態度。仕事に対する姿勢。村からの長い道のりで、母が仕事のためにそこを往復した日々を思って、胸を痛めた直後だったこともあるだろう。メイは、自分の気持ちを抑えることができなかった。
へらへら笑っている男の襟首を掴んだ。
「真面目に働け!仕事中に飲酒だなんて、言語道断!!」
「へー、へー」
言われ慣れた様子で、相変わらずのらりくらりとかわす男に、メイは一層こみ上げる怒りを必死で抑えているのだけれど。
「そりゃお客さんも来ないよ!!」
「へへっ」
「褒めてないっつーの!」
「ほう」
ああ、こいつとしゃべってるだけ、時間が無駄だ。これだけ気持ちを込めて訴えかけてるのに、一度も視線が交わらないことに、メイは気づいた。
「とにかく、マドレーヌ1個だけでいいから焼いてよ!!」
「んあ?」
間抜けな返答の男の声のせいか、自分の声がやけに悲痛な響きを持っているように聞こえたメイは、一瞬喉を詰まらせた。
「…それ買ったら、帰るから」
「んー」
それでもほとんど反応のない男に、メイは強硬手段に出た。
「マドレーヌ売ってくれるまで帰らないからねえぇぇ!!」
「ぐえっ」
耳元で叫んでやれば、ようやく男は、いくらか感情を浮かべた瞳で、恨めしげにメイを睨んだ。
「ふん。いい顔できるじゃん」
全然怖くないけどね、と言い募るメイの視線が、先ほど店を飛び出したおばさんの叩きつけた紙切れに止まる。
「“売り子募集”、……“住み込み可”!?」
断る、と暗い声で呟く男を押しのけて、メイは意気揚々と奥のドアを開けたのだった。
「あれ、君、ついてきちゃったの?」
メイは、勝手に上がりこんだ店の2階で、荷物を下ろしたとき、その中からぴょんと飛び出した小人に驚いた。
「てっきり、村に住んでいる守り人か何かかと思ってた。ママの守り人だったのかなぁ。ママの代わりにあたしにくっついてくれたのかなぁ」
メイが手のひらを差し出すと、小人はそこに上って、座った。ぱくぱくと口を動かして、その後ぷくりと頬を膨らませる。
「ん?ここは居心地が悪いの?」
可愛い男児の姿の小人は、ふくれっ面をするといっそう愛らしくて、メイは気持ちが和らいでいくのを感じた。
うん、と言うように大きく頷いて見せるから、メイはくすくす笑う。彼の声は、メイの耳にだって、全く聞こえないのだけれど、表情や仕草で、なんとなく意思は伝わるのだ。
「でも、どうしても、マドレーヌを食べたいんだもん」
子供じみた声だと思う、自分でも。
メイは、ここまでこだわる理由は、自分でもよくわからないけれど、諦めることができなかった。
「食べたら、出て行くってば」
相変わらずぷりぷり怒っている様子の小人に、メイはそう囁いた。
慣れないことばかりで、疲れていたのだろう。
勝手に上がりこんだ廃屋のような建物の2階、カビ臭いベッドに横になったら、すぐにメイの意識は飛んだ。
はっ、と目が覚めたときには、窓の外が微かに明るくなってきていた。
…トイレ。
2階にそれらしいところがなかったので、1階に下りてみると、甘い香りが次第に強くなり、メイはドキドキした。
昨日強引に通り抜けた、店の奥のスペースは、厨房だ。あの時は死んだように静まり返っていたその場所が、今は温かな灯りのもとで、息を吹き返している。
「何作ってるの?」
好奇心に負けて、思わずそう話しかけると、驚きもしないで肩越しにちらりと振り返った男は、「雇ってねーぞ」と余計な一言。
ムッとしたメイはドアのところから遠慮がちに覗くのをやめて、その手元が見えるところまで進んだ。
「また、チョコレートか」
1センチ角ほどのサイズのチョコレートが、トレイに無造作に転がっている。
バターの香りがした気がするのにな、と思いながら、メイは残念そうにトレイを見下ろしている。
「ただのチョコじゃねーぞ」
「…酒臭いチョコ?」
二日酔いだと言っていたにもかかわらず、瓶から直接アルコールを摂取している男に呆れて、メイがそう言うと、「ぶっ」と男が噴き出した。
「失礼だけど、正解でもあるな。特別に1個食わしてやる」
「あれ?昨日よりはまともにしゃべれるね」
「迎え酒すると頭痛が消えるからな。酒は神様だ♪」
「……」
呆れて言葉が出ないメイの口に、男がその四角いチョコレートを一つ、押し込んできた。
「ん、ん!?」
独特の刺激に、メイは涙目になっている。
チョコの表面が溶けた瞬間、中から液体がとろりと滲み、メイの舌を痺れさせ、喉を焼き、鼻を痛めた。
「あ、あた、あたし、未成年だってば!」
お酒のにおいがするだけかと思っていたのに、しっかり液体そのものを包みこんでいたからびっくりしているメイ。
「へー」
「っ。もうっ」
再度抗議を試みようとしたメイは、胸をひたひたと鎮めていた悲しみの冷たさが、引いていることにふと気付いた。
「……あれ?」
ママを失った、寂しさ。
それが、消えたわけじゃないけれど、溺れそうなほどじゃない気がする。
「リキュール入りのチョコレート。辛い現実を、忘れさせてくれる」
その低い声の意味を認識したら、メイの瞳はうっすらと水の膜を張ったけれど、それが雫となって零れおちることはない。
「なんか、変」