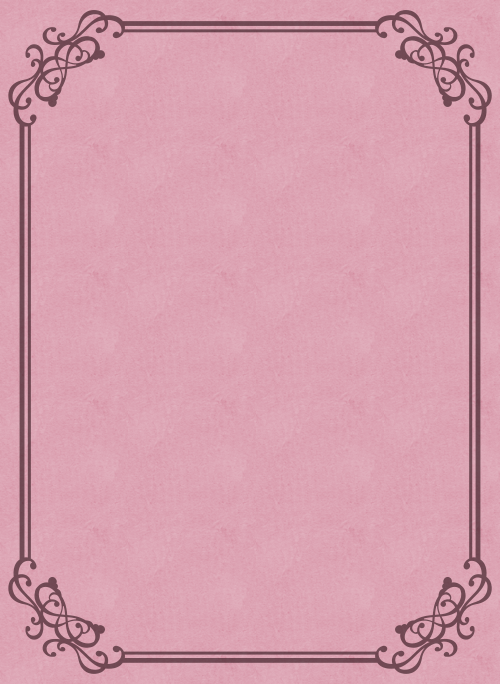顔には皺が刻み込まれているが、瞳はきらきらと輝いている。
孫娘に対して厳しさと優しさを同時に感じさせる口調で話しかけるという離れ業を彼女はこなしていた。
「クリスティアンのことを忘れられないでいるのはわかります。ですが、いつまでもふらふらとしているわけにもいかないでしょう」
侍女たちには給仕をさせず、オクタヴィアは自らの手で茶器を操ってお茶をそれぞれのカップに注ぎ入れた。
「アイラと言いましたか、そなたもそこにお座りなさい」
言われるままにアイラはテーブルについた。エリーシャの宮では当たり前のことなのだが、皇后もこうやって侍女たちとテーブルを囲んだりするのだろうか。
「そなたにお願いがあります」
皇后に言われて、アイラの背が伸びた。
「この娘が夜中にふらふら出歩いているのは知っています――ほどほどのところで連れ帰ってください」
「わたしが、ですか……?」
「他に誰がいるというのです?」
皇后は涼しい顔でお茶を口に運ぶ。アイラは混乱した。
孫娘に対して厳しさと優しさを同時に感じさせる口調で話しかけるという離れ業を彼女はこなしていた。
「クリスティアンのことを忘れられないでいるのはわかります。ですが、いつまでもふらふらとしているわけにもいかないでしょう」
侍女たちには給仕をさせず、オクタヴィアは自らの手で茶器を操ってお茶をそれぞれのカップに注ぎ入れた。
「アイラと言いましたか、そなたもそこにお座りなさい」
言われるままにアイラはテーブルについた。エリーシャの宮では当たり前のことなのだが、皇后もこうやって侍女たちとテーブルを囲んだりするのだろうか。
「そなたにお願いがあります」
皇后に言われて、アイラの背が伸びた。
「この娘が夜中にふらふら出歩いているのは知っています――ほどほどのところで連れ帰ってください」
「わたしが、ですか……?」
「他に誰がいるというのです?」
皇后は涼しい顔でお茶を口に運ぶ。アイラは混乱した。