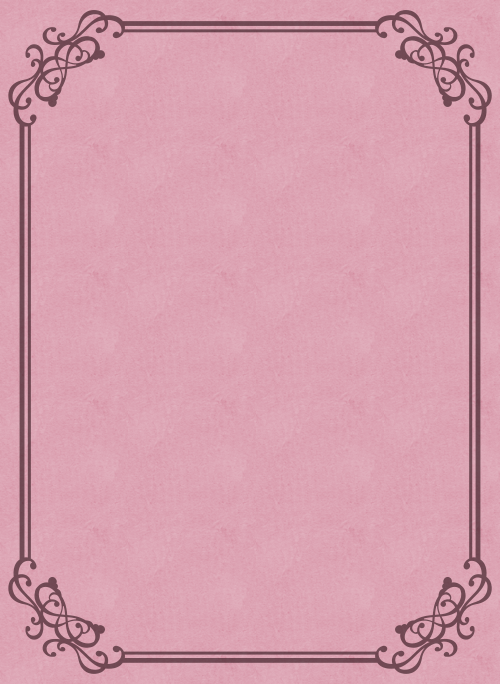「すまないが、団長室まで来てもらえないか――エリーシャ様にはこちらから連絡を入れておく」
首を傾げながら、アイラはイヴェリンについていった。
「悪かったわね、忙しいところを呼びつけたりして」
「いえ、それはいいんですけど。何かご用ですか?」
アイラはこっそり目の前の二人を比べる。
背が高く、ほっそりとした体型のイヴェリンは皇女近衛騎士団の制服に身を包んでいることもあって、知的で優美な男装の麗人といった雰囲気だ。
その夫であるゴンゾルフは、今はアイラのために手ずからお茶を用意しているところだった。慎重に茶葉をはかる手つきも、ポットにお湯を注ぐ手つきも、いたって穏やかなものだ。
がっしりとした体格と、褐色の髪と同色の髭をもじゃもじゃと生やしていることもあって、大きな熊のように見える。
「いつまでかかるんだ」
いらいらとイヴェリンがたずねた。
「ん、もう少し。それでね、アイラ――エリーシャ様のことなんだけど」
首を傾げながら、アイラはイヴェリンについていった。
「悪かったわね、忙しいところを呼びつけたりして」
「いえ、それはいいんですけど。何かご用ですか?」
アイラはこっそり目の前の二人を比べる。
背が高く、ほっそりとした体型のイヴェリンは皇女近衛騎士団の制服に身を包んでいることもあって、知的で優美な男装の麗人といった雰囲気だ。
その夫であるゴンゾルフは、今はアイラのために手ずからお茶を用意しているところだった。慎重に茶葉をはかる手つきも、ポットにお湯を注ぐ手つきも、いたって穏やかなものだ。
がっしりとした体格と、褐色の髪と同色の髭をもじゃもじゃと生やしていることもあって、大きな熊のように見える。
「いつまでかかるんだ」
いらいらとイヴェリンがたずねた。
「ん、もう少し。それでね、アイラ――エリーシャ様のことなんだけど」