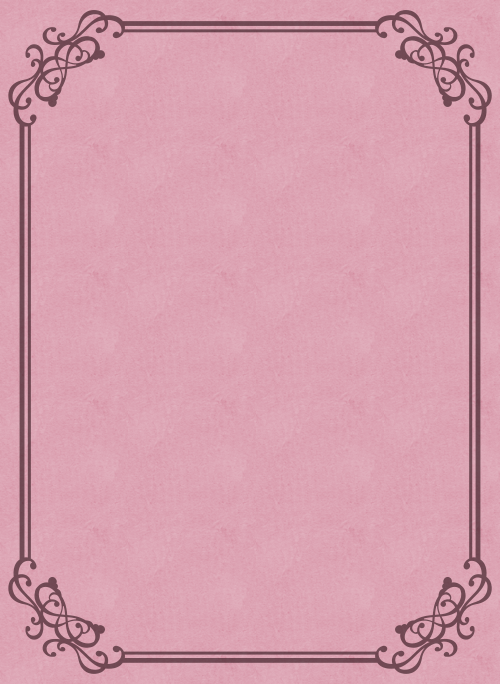「その可能性は、今あなたが否定したじゃないの」
エリーシャは、ジェンセンがあげた可能性に一つ一つ言葉を挟んでいく。
「ですな。わたしに傷を負わせたのは、そのクリスティアン様の可能性がある男ですから。わたしが魔術を学び始めて二年の男に負けるというのは、まあ考えられないでしょう。残る可能性は――」
そこまで言ったにもかかわらず、ジェンセンは黙り込んでしまって口を開こうとはしなかった。沈黙をごまかそうとするかのようにアイラは立ち上がって、新しいお茶をいれる。
「……父さん、お茶」
「悪いな」
家で暮らしていた頃は、こうやってしばしば父にお茶をいれたものだった。皇女宮で使っている茶葉は、むろんアイラが家にいた頃使っていた茶葉よりはるかに上質なものだけれど、同じような穏やかな時間が二人の間に生まれる。
アイラが差し出したカップにたっぷりミルクと砂糖を追加してかきまわしてから、ジェンセンは改めて口を開いた。
「最後の可能性。わたしはこれが一番可能性が高いと思っている――」
「もったいぶらないでさっさと言いなさいよ」
いらいらとエリーシャは先を促した。
エリーシャは、ジェンセンがあげた可能性に一つ一つ言葉を挟んでいく。
「ですな。わたしに傷を負わせたのは、そのクリスティアン様の可能性がある男ですから。わたしが魔術を学び始めて二年の男に負けるというのは、まあ考えられないでしょう。残る可能性は――」
そこまで言ったにもかかわらず、ジェンセンは黙り込んでしまって口を開こうとはしなかった。沈黙をごまかそうとするかのようにアイラは立ち上がって、新しいお茶をいれる。
「……父さん、お茶」
「悪いな」
家で暮らしていた頃は、こうやってしばしば父にお茶をいれたものだった。皇女宮で使っている茶葉は、むろんアイラが家にいた頃使っていた茶葉よりはるかに上質なものだけれど、同じような穏やかな時間が二人の間に生まれる。
アイラが差し出したカップにたっぷりミルクと砂糖を追加してかきまわしてから、ジェンセンは改めて口を開いた。
「最後の可能性。わたしはこれが一番可能性が高いと思っている――」
「もったいぶらないでさっさと言いなさいよ」
いらいらとエリーシャは先を促した。