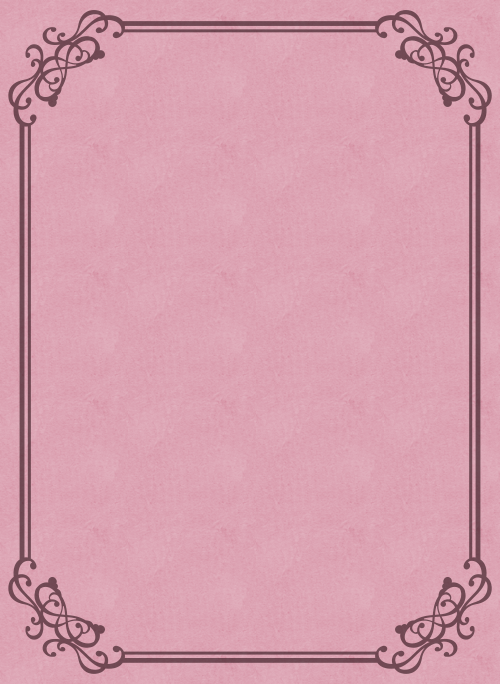「おじさんも首に黄色い布を巻いているでしょう? だから、ひょっとしたら会わせてくれるんじゃないかなって」
「うーん」
それに反して、ケヴィンは渋い表情になったようだった。荷馬車の後方にいるアイラたちからは、彼の表情を伺うことはできなかったけれど。
「それは難しいなぁ」
「……何故……?」
「知らない人間をセシリー様の前に連れて行くわけにはいかないだろ?」
ハンカチで顔を覆うイヴェリンのすすり泣きがますます大きくなる。自分でしゃべろよ、とアイラは心の中で毒づいたのだけれど、話が進まないのでとっととしゃべることにした。
「でも、姉を見てちょうだい。義理の兄があまりにも突然亡くなったから、心の整理ができてないの」
すすり泣くイヴェリンの声がいっそう大きく響きわたる。やり過ぎて嘘っぽく――いや演技なのだが――なっているのだが、幸いにもケヴィンはそれに気づいていないようだった。
「ちょっと死んだ兄さんと話をさせてもらえるだけでいいの。それでも……だめ?」
「それは気の毒だけどなあ」
ケヴィンの荷馬車を引く馬の足取りはゆったりとしたものだ。
「うーん」
それに反して、ケヴィンは渋い表情になったようだった。荷馬車の後方にいるアイラたちからは、彼の表情を伺うことはできなかったけれど。
「それは難しいなぁ」
「……何故……?」
「知らない人間をセシリー様の前に連れて行くわけにはいかないだろ?」
ハンカチで顔を覆うイヴェリンのすすり泣きがますます大きくなる。自分でしゃべろよ、とアイラは心の中で毒づいたのだけれど、話が進まないのでとっととしゃべることにした。
「でも、姉を見てちょうだい。義理の兄があまりにも突然亡くなったから、心の整理ができてないの」
すすり泣くイヴェリンの声がいっそう大きく響きわたる。やり過ぎて嘘っぽく――いや演技なのだが――なっているのだが、幸いにもケヴィンはそれに気づいていないようだった。
「ちょっと死んだ兄さんと話をさせてもらえるだけでいいの。それでも……だめ?」
「それは気の毒だけどなあ」
ケヴィンの荷馬車を引く馬の足取りはゆったりとしたものだ。