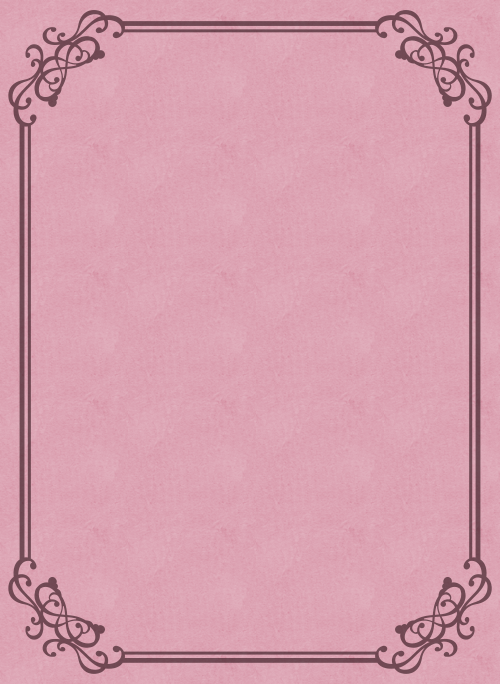「まいったな。彼は使い物にならぬというのが、わたしたちの見立てだったのだが」
イヴェリンは顔をしかめる。アイラを皇女として扱うのも忘れてしまったようだった。
「父の権勢によってぬくぬく生きているぼんぼんだ、と。父の方は野心剥き出しなのだがな」
「――わたしだってそう思っていましたよ!」
アイラはエリーシャの護衛侍女であり、対外的には『一番のお気に入り』ということになっているから、エリーシャが行くところにはどこにでもついていた。
だからこそ、ダーシーとエリーシャが会っている場にも同席していたし、他の侍女たちと比べればダーシーを見かける機会も多かった。
アイラにとっては、ダーシーはぼんやりとした貴族でしかなくて、それはたぶんエリーシャにとっても同じだったはず。
「あいつだけはない。あいつとだけは国を背負うことなんてできない」
と言っていたのだから。
イヴェリンは小さくうなって、額に手を当てた。
「まいったな。さすがに侯爵家ともなると密偵を送り込むのは難しい――」
「……」
イヴェリンは顔をしかめる。アイラを皇女として扱うのも忘れてしまったようだった。
「父の権勢によってぬくぬく生きているぼんぼんだ、と。父の方は野心剥き出しなのだがな」
「――わたしだってそう思っていましたよ!」
アイラはエリーシャの護衛侍女であり、対外的には『一番のお気に入り』ということになっているから、エリーシャが行くところにはどこにでもついていた。
だからこそ、ダーシーとエリーシャが会っている場にも同席していたし、他の侍女たちと比べればダーシーを見かける機会も多かった。
アイラにとっては、ダーシーはぼんやりとした貴族でしかなくて、それはたぶんエリーシャにとっても同じだったはず。
「あいつだけはない。あいつとだけは国を背負うことなんてできない」
と言っていたのだから。
イヴェリンは小さくうなって、額に手を当てた。
「まいったな。さすがに侯爵家ともなると密偵を送り込むのは難しい――」
「……」