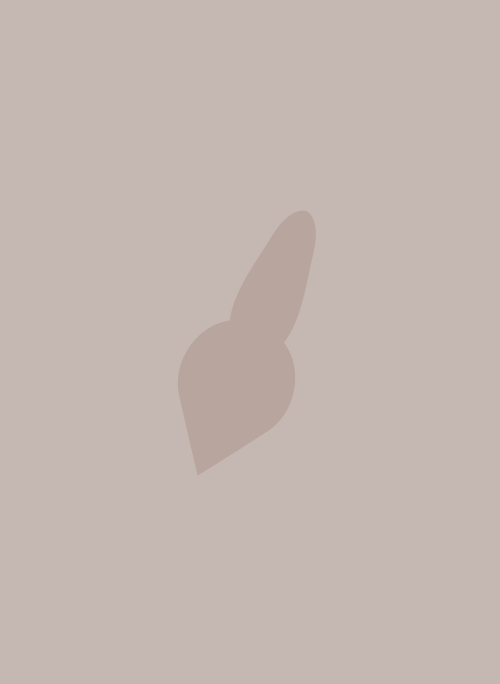「──あの時、俺がちゃんとお前の事を支えられてたらって、後悔してる」
あの時、ってのは、多分朧と別れた時のことだ。
朧と暮らす部屋から飛び出した俺は、陣の所に逃げ込んだ。
朔杜の所へ行ったら、別れたとはいえ朧が何か仕出かすと思ったからだ。
もしもあの時、陣じゃなく朔杜の元へ行っていたら、きっと恭介とは出逢わなかっただろう。
「さく、っ、……待て、って!」
目元、唇、頬、首筋……と、キスを落とされ、嫌でも身体が疼き出す。
このまま、流されるままに相手をしてやれば、朔杜も落ち着くかな……なんて、陥落してしまいそうになる。
抑え込まれていても、狭い車内では少し動くだけで身体がどこかにぶつかるし、駐車場の隅とはいえ、コンビニの明かりが車内を薄く照らしている──行為に及ぶには最悪の場所だけど。