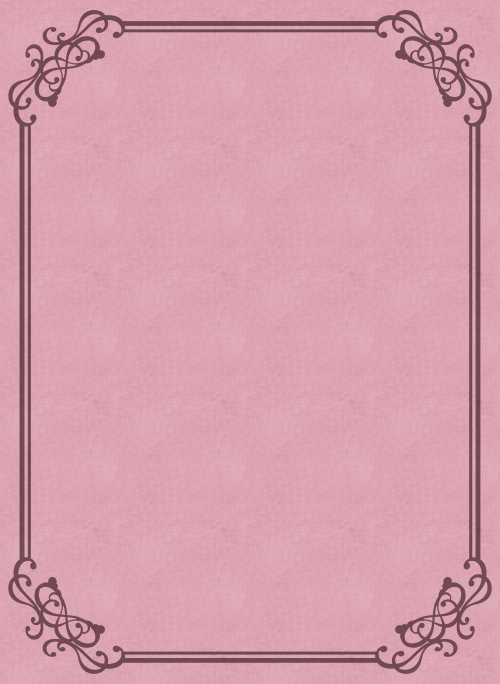「駅まででもいいから、一人にしないで!」
雑居ビルの向こうから一台のタクシーが走り去るのを、星野の肩越しに確認した。
離れてはいるけれど、後ろに乗っているのは確かに彼女だった。
「送る、って言うまで離さないよ。酔ってるせいじゃないんだからっ、わたしだって真剣なんだから!」
星野の頬を伝った細い筋を見て、薄れてた記憶が甦る。
あのファミレスでの、あの日の光景が浮かぶ。あの時もこうやって泣かせたよな、って思いだす。
あの時、想いを受け止められなかったのは、僕が幼かったから。
断るにしたってちゃんと話さなかった。
向き合わなかった。
ひどくつまらない理屈を並べ取り繕って、その答えを正当化したんだ。
子供(ガキ)だった。
そして、いまだって――
「……わかったよ」
呟くように言ったその後、全身を強ばらせていた力を僕はそっと解放した。