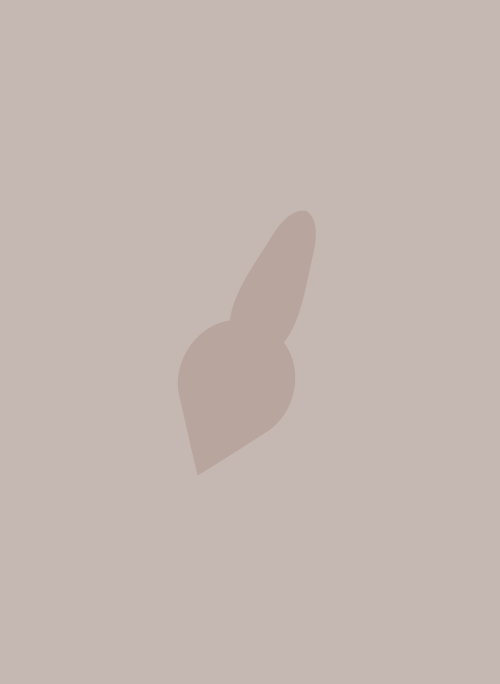女性は私の退学意志が固く動くことがないと分かると、退学手続きの書類を取り出して私の前に差し出し、手続きに必要なことを説明し始めた。
保護者の印だの、担当教官の印だの、本人の印だの、審議会だの、思っていたより複雑なようだ。
説明が終わった頃には嫌気が差して、うんざりし始めていた。
去り際に時計をチラっと確認すると正午を回るところだった。
教務課から解放され、次は指導教官のところに退学の旨を伝えに行く。
教官も教務課の担当者女性と同じように、まず私を説得して思いとどまらせようとした。
けれど、私の決意が固いのを見て取ると
ボソっと低い声で言った。
「残念だな」
そう言うと彼は退学届に捺印した。
そこまでたどり着くまでには時間がかかった。
彼の目には露骨な軽蔑の色と少々の哀れみの色が浮かんでいた。
彼から見れば、きっと私は負け犬なんだ。
保護者の印だの、担当教官の印だの、本人の印だの、審議会だの、思っていたより複雑なようだ。
説明が終わった頃には嫌気が差して、うんざりし始めていた。
去り際に時計をチラっと確認すると正午を回るところだった。
教務課から解放され、次は指導教官のところに退学の旨を伝えに行く。
教官も教務課の担当者女性と同じように、まず私を説得して思いとどまらせようとした。
けれど、私の決意が固いのを見て取ると
ボソっと低い声で言った。
「残念だな」
そう言うと彼は退学届に捺印した。
そこまでたどり着くまでには時間がかかった。
彼の目には露骨な軽蔑の色と少々の哀れみの色が浮かんでいた。
彼から見れば、きっと私は負け犬なんだ。