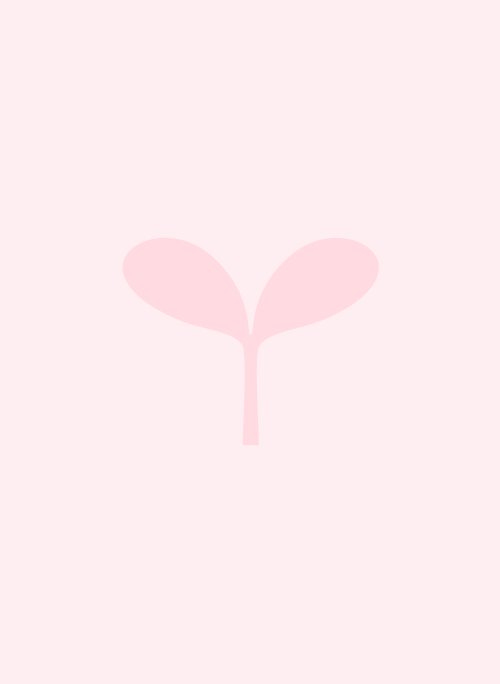「陽子さんって、社長の奥さんの?」
「元々、陽子さんはお父さんが昔勤めていた病院の看護師をしていたんだ。それが、お父さんが育児休暇を取ってる間に病院をやめて、偶然にも仙台の社長のところに嫁いできていた」
懐かしそうに話す親父の横顔を見ながら、私は陽子さんの顔を思い出そうとしていた。
よく知っているはずなのに、なかなか思い出せない。
本を読んでいる姿ばかりがイメージされた。
陽子さんは親父の前ばかりでわたしを可愛がっていた。
そして、ある時わたしを長い時間見つめて、深いため息をついたのを覚えている。
私は陽子さんが苦手だった。
「おまえは陽子さんに育てられたようなものなんだぞ」
「そうなんだ」
「覚えてないのか?お父さんが仕事の間、ずっと面倒を見てもらってたんだぞ」
小さい頃、わたしは親父と一緒に会社に出かけた。
更にそこから仕事場へ向かう親父を見送り、わたしは親父が帰って来るまで陽子さんと一緒にいた。