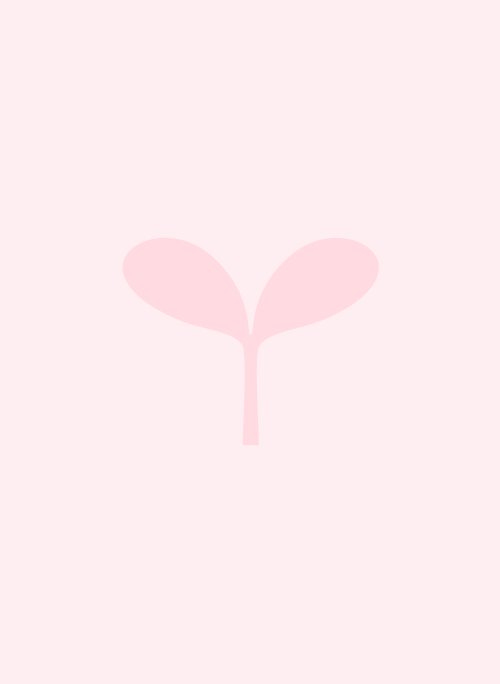「おまえはお父さんの本当の子供じゃない」
そう言われるとばかり思っていた。
「親父の子供だったんだね」
胸の奥が熱くなり、知らず知らず涙が溢れていた。
愛し合う二人から生まれてきた。
もう、それだけで充分だった。
「お母さんのこと、もっと教えて」
「そうだな、愛子は4人兄弟の末っ子だった。3人のお兄さんとは歳も離れていて、お姫様みたいに育ったんだ」
「あっ、それわかる。私のことをお姫様って言ってたのは、お兄さんたちだったんだ」
記憶の断片がどんどんつながっていく。
「親父さぁ、高校のとき、私に父親のことを親父なんて言うなよ、って言ってなかった?」
「そうだったかな。あっ、そうか。そういえば、確かに愛子にそう言った」
親父と目が合った。
そして、ふたり、目でタイミングを計る。
「だって、お兄さんたちも言ってるよ」
いっしょに声を合わせて言うと、いっしょに声を出して笑った。
「おまえ、本当に愛子なんだなぁ」
お母さんもきっと親父のことが好きだったんだよ。
高校の時の記憶なんて、親父がらみばっかなんだもん。