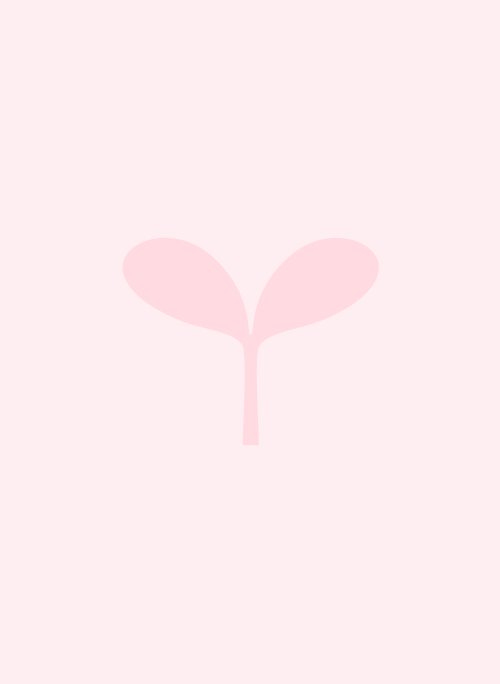空は青く、冷たい空気は澄み渡り、稜線沿いを駆け上ってくる風が気持ちよかった。
「お父さん、あの時どうしてわたしのほっぺたをぶったの?」
「あの時って?」
「わたしがはじめてぷっつんってなったとき」
「ああ、あの時か。・・・覚えてないんだよな」
「うん」
「お父さんが、おやすみのキスしたら、あいかが・・・大人のキスをしたんだ」
「大人のキス?」
「お父さんの首に手をまわして、大人のキスを・・舌をからめてきたんだ」
「わたし、そんなことしてない」
「わかってる。きっと、あいかなが嫌がらせでやったんだろ」
「まさか・・・」
あいかはあいこが最後に残した言葉を思い出していた。
愛する人がちがったから分かれた。
そんなふうに聞こえた。
達哉を愛したアイコがいた。
あいかなを愛したあいこがいた。
だったら、お父さんを愛した愛子がいてもいいじゃないの。
きっと、そうだ。
きっと、そうだよ。
「お父さん、お父さんを愛した愛子がいたんだよ」
それに応えるように、あいかの心の奥で、なにかの疼く気配がした。