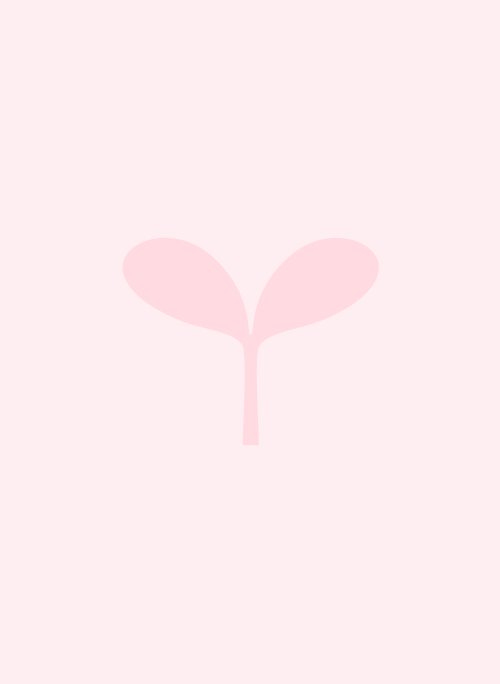思えば愛子の記憶は私を憂鬱にしてきた。
その上、思いだしたばかりの殺戮の記憶は、頭から離れることなく、私を苦しめる。
「私はどうしてここにいるんだろ。
愛子の濡れ衣をはらすため?
そんなことのために私はここにいるの?」
私は親父の肩の上に寄りかかるように頭を置いた。
「そうか、おまえも辛いんだな。でもな、愛子が真犯人じゃなかったら、俺はもちろんのこと、あいかが一番に救われるんだよ」
親父は手を回し、私の頭を撫でた。
「そうだよね。これでよかったんだよね」
「そうさ、何も間違っちゃいない」
私は親父の肩に顔をうずめ、「うん」と頷いた。