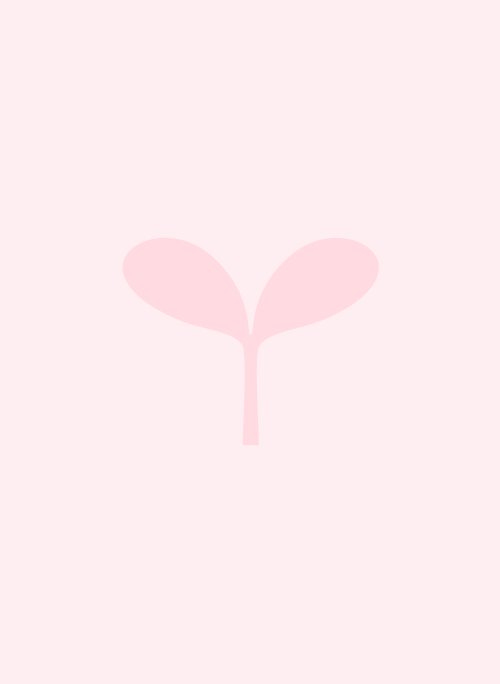『バカっ、何すんだぁっ』
私は金縛りにあったように、再び身体の自由を奪われた。
「い、いてーよぉ」
哀哉は私に取って代わり、起き上がろうとするが、身籠の身体は重く、力も入らないのだろう。
ひっくり返った亀のように、あたふたするばかり。
「き、救急車・・。愛子が死んじまう」
哀哉は部屋の隅まで膝を立てて進むと、つかまり立ちをする幼子のように、ようやく立ち上がった。
「いてぇーよぉ」
顔をゆがめながらも、哀哉は一歩、また一歩と、踏みしめるように足を進める。
ようやくたどり着いたベッドに尻餅をつくように腰掛け、枕元の電話を取った。
「た、たすけて・・、あいこが、あいこが・・・」
そう言うのが精一杯だったのか、哀哉はそのまま後ろへ仰向けに倒れた。