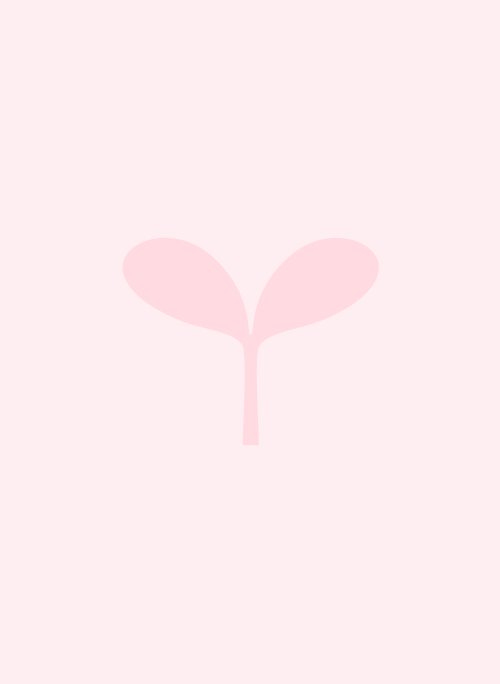目を閉じたくても閉じられなかった。
気を失いたくても失えなかった。
包丁を引き抜くと、ホースに穴が開いたようにピューと血が吹き出した。
顔にあびた真っ赤な血しぶきは妙に生暖かった。
私は引き抜いた包丁をもう一度達哉の胸に押し込んだ。
達哉の手が私の手を捕らえたが、私はかまわず引き抜いて、更にまた刺した。
まるで映画を観ているようだった。
でも、血糊でぬめりつく包丁を持つ手は間違いなく私の手だった。
私は肩で息をしていた。
横たわる達哉は微動だにせず、流れ出た血だけが生き物のようにうごめいていた。